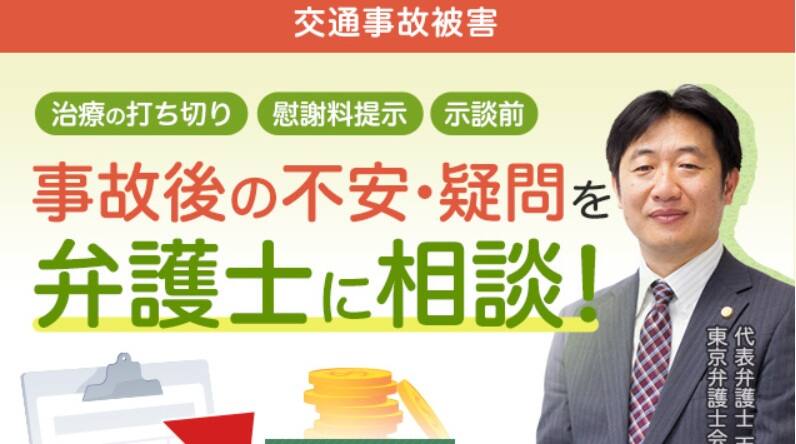最高裁は2020年(令和2年)7月9日、後遺障害による逸失利益の賠償方法について、従来の一時金賠償方式(一括払い)だけでなく、定期金賠償方式(月1回など定期払い)も認められるとの初判断を示しました。最高裁判決の内容と、近年、定期金賠償方式が認められるようになってきた経緯や背景について見ていきます。どうやって定期金賠償方式が認められるようになったか?民法は、「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める」としているだけで(民法417条、722条1項)、支払い方法は、特に定めていません。損害賠償の支払い方法としては、一時金賠償と定期金賠償の2通りの方法があります。実務では、損害は不法行為時に発生したものと解し、将来現実化する損害(逸失利益)についても、中間利息を控除して現在価額に換算し、一括で先払いする一時金賠償方式が採られてきました。なぜ、定期金賠償方式は、採用されてこなかったのでしょうか?定期金賠償方式を採用しなかった理由とは?定期金賠償方式を採用できない主な理由として、次の2つが挙げられてきました。加害者側の資力の悪化による支払い不能に備えた履行確保制度(担保供与制度)がないこと事情の変更により定期金の額が不相当となったときの変更判決制度が存在しないことこのうち、「変更判決制度」については、平成8年の民事訴訟法の改正において、定期金賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを提起できる制度が導入(民訴法117条)されたことで、解決しています。しかし、「履行確保制度」がない問題は、依然として残されています。平成8年の民事訴訟法改正で新たに創設された「変更判決制度」に関する条項は、次の通りです。民事訴訟法 第117条1項口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。ただし、その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。民訴法の改正により、定期金賠償方式も採用され始めた民訴法117条(変更判決制度)が創設されたことにより、将来介護費について定期金賠償方式を採用するケースも出てきました。一時金賠償方式には、被害者と加害者の双方から不満もともと将来現実化する損害を一時金賠償することには、被害者の側だけでなく、加害者の側にも不満がありました。被害者の側は、逸失利益を現在の価値に換算して支払われますから、賠償額が大きく減ることに対する不満があります。他方、加害者の側にも、こんな不満がありました。逸失利益は、67歳まで稼働できることを前提として算出します。将来介護費用は、平均余命いっぱい認めます。ところが、重度の後遺障害の場合、高い金額を得た直後に亡くなってしまうことがあります。つまり、もらい過ぎではないか、というわけです。このようなことから、被害者と加害者の双方が抱える不合理を解消するため、一時金賠償よりも定期金賠償の方が妥当ではないか、という議論が高まってきました。被害者が一時金方式で賠償請求、加害者が定期金賠償を主張した裁判例そんな中、重度の後遺障害を有する被害者が、将来介護費を一般的に行われている一時金方式で賠償請求したのに対し、加害者側が、「被害者は重度の後遺障害であり平均余命生きられない」として、「生存する限り」支払うという定期金賠償を主張して争った裁判がありました。これについて、最高裁は、次のように判断しました。損害賠償請求権者が訴訟上一時金による賠償の支払を求める旨の申立をしている場合に、定期金による支払を命ずる判決をすることはできないものと解するのが相当である。(最高裁判所第二小法廷・昭和62年2月6日)これは、損害賠償請求権者が一時金による支払いを求めている場合には、その意思に反して、裁判所が定期金による支払いを命ずることはできない、とするものです。判決では、その理由を述べていませんが、最高裁調査官は「担保供与及び変更判決制度のない我が国では、定期金方式の採用には慎重でなければならず、少なくとも原告からの定期金方式によるべき旨の申立のない場合には、定期金方式を採用することはできないとの考え方によるものと思われる」と解説しています。この判決が出されたのは昭和62年。当時は、変更判決制度がありませんでした。平成8年の民訴法の改正により(平成10年1月施行)、定期金賠償を命じた確定判決につき、「損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる」(民訴法117条1項)ことになりました。これを受けて、将来介護費について、履行が確保できるときは、定期金賠償を認める裁判例も出てきています。それでは、今回の最高裁判決について見てみましょう。後遺障害逸失利益の定期金賠償を認めた最高裁判決とは?事案は、2007年に4歳で交通事故に遭い、高次脳機能障害を負った被害者とその両親が、運転手や保険会社などを相手取り、月ごとの賠償(定期金賠償)を求めていたものです。この被害者の場合、労働能力を100%喪失し、逸失利益が長期間にわたるため、後遺障害逸失利益は、定期金賠償であれば約2億6千万円なのに、一時金賠償だと中間利息控除によって約6,500万円にまで減ってしまうのです。最高裁は、被害者側の意向にそって、定期金賠償を認めました。また、定期払いの期間中に被害者が死亡した場合、死亡時をもって加害者側が賠償義務を免れることは「公平の理念に反する」とし、本来の支払い期間が終わるまで賠償義務は続き、遺族が受け取りを続けられる、との判断も示しました。最高裁判所第一小法廷(令和2年7月9日)交通事故の被害者が後遺障害による逸失利益について定期金による賠償を求めている場合において、不法行為に基づく損害賠償制度の目的及び理念に照らして相当と認められるときは、同逸失利益は、定期金による賠償の対象となる。交通事故に起因する後遺障害による逸失利益につき定期金による賠償を命ずるに当たっては、事故の時点で、被害者が死亡する原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、就労可能期間の終期より前の被害者の死亡時を定期金による賠償の終期とすることを要しない。定期金賠償が認められたのは、民事訴訟法の改正により、変更判決制度ができたことが大きいようです。ポイントは、ここです。原文通りではありませんが、定期金賠償を認めた理由について要点をまとめると、こうです。後遺障害逸失利益は、将来、その算定の基礎となった事情に著しい変更が生じ、算定した損害額と現実化した損害額との間に大きなかい離が生ずることもあり得る。民法は、不法行為に基づく損害賠償の方法につき、一時金による賠償によらなければならないものとは規定しておらず、他方で、民訴法117条は、定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えを提起することができる旨を規定している。交通事故に起因する後遺障害逸失利益は、現実化する都度これに対応する定期金の支払をさせ、算定した損害額と現実化した損害額との間にかい離が生ずる場合には、民訴法117条によりその是正を図ることができるようにすることが相当と認められる場合がある。つまり、後遺障害逸失利益は、定期金方式で賠償し、必要に応じて民訴法117条を活用して支払額を是正する方法が相当と認められる場合がある、として、定期金賠償方式を認めたのです。なお、被害者の死亡後も賠償金の支払い義務が継続することについて、裁判長が補足意見で、事情変更を理由に裁判を起こし、一時金賠償に変える対応も「検討に値する」としています。まとめ定期金賠償方式は、本来、被害者にとって合理的な賠償方法です。これからは、重度後遺障害で労働能力喪失期間が長期にわたるような場合には、定期金方式による賠償請求が増えるかもしれません。ただし、定期金賠償はメリットばかりではありません。定期金賠償はリスクやデメリットも大きいので、一時金賠償と定期金賠償のどちらを選択するかは、弁護士とよく相談して、慎重に判断することが大切です。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274 ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『交通関係訴訟の実務』商事法務 277~294ページ・『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 74~80ページ・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 126~129ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 109~112ページ・『交通事故事件の実務』新日本法規 56ページ