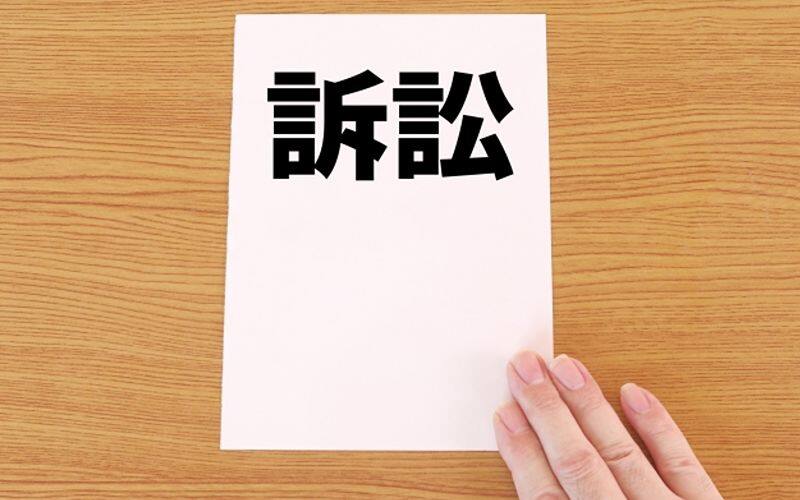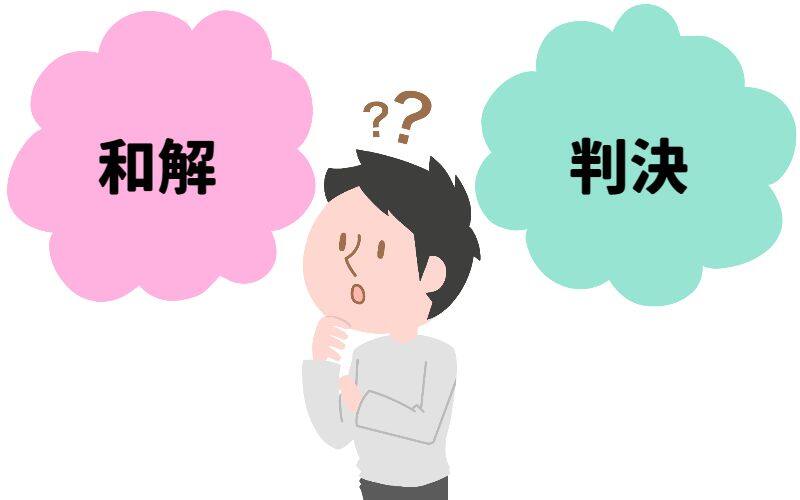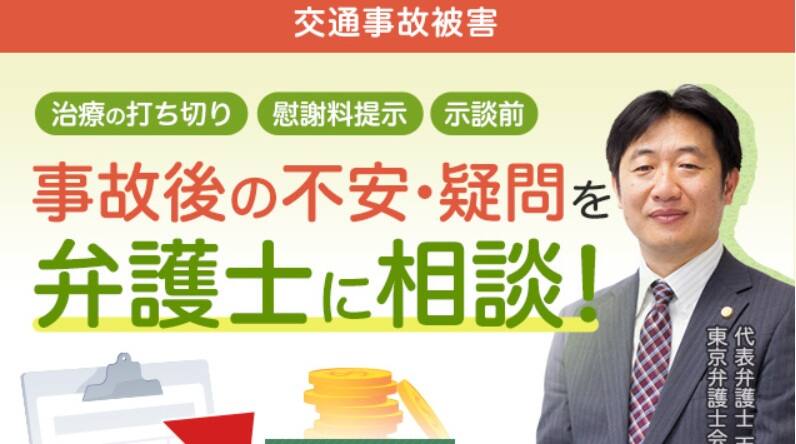※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴えを提起します。本人訴訟という方法もありますが、裁判は、ADR(裁判外紛争解決手続)や調停の申立てと違い、専門的な知識や技術が必要なので、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
ここで紹介する裁判の手続き・流れについては、弁護士に相談すれば、あなた自身が詳しく知らなくても大丈夫です。予備知識として押さえておくとよいでしょう。
損害賠償請求訴訟の手続きと流れの概略
民事裁判は、原告が訴状を提出することで開始されます。
弁護士に委任した場合、あなた自身が裁判所に出頭する必要はほとんどありません。相手方の主張する反論等について、弁護士の事務所などで打ち合わせすることが中心となります。
あなたが裁判所に出頭するのは、当事者尋問の期日と和解等の重要な場面に限られます。
①訴状提出
訴状は、管轄する裁判所に提出します。
訴状には、当事者(原告・被告)、請求する内容(請求の趣旨)とその理由(請求の原因)などを記載します。正本1通と相手方(被告)人数分の副本を作成し、決められた額の収入印紙を貼り、郵便切手を添えて提出します。
収入印紙額は訴額に応じて決まります。郵便切手の額や枚数は、裁判所により異なります。郵便切手は、訴状を相手方に送付したり、呼び出し状を送付したりするのに使用します。この収入印紙と郵券(郵便切手)の額が訴訟費用です。
②訴状審査
裁判所で訴状をチェックします。訴状に形式的な不備があれば原告側に修正を指示します。
不備がなければ訴状を被告側に送達し、口頭弁論期日を指定し、原告と被告に口頭弁論期日に出頭するよう呼び出します。
③口頭弁論
裁判所に訴状を提出した後、およそ1ヵ月~2ヵ月後に、第1回口頭弁論期日が指定されます。第1回口頭弁論では、原告は訴状にもとづき主張を陳述し、被告は事前に提出しておいた答弁書にもとづき主張(認否・反論)を陳述します。
第2回口頭弁論以降は、概ね1ヵ月~2ヵ月に1回のペースで口頭弁論があり、双方が事前に提出する準備書面にもとづき主張を述べます。また、主張を裏付ける証拠を提出します。これを双方の主張が出尽くすまで繰り返します。
なお、主張を述べるといっても、法廷で実際に陳述するわけではありません。法廷ドラマ等でご存知の方もいるかもしれませんが、あらかじめ裁判所と相手方に書面を提出しておき、口頭弁論の期日に法定で本人または代理人が「陳述します」と述べることで、書面に記載した主張の全てを「陳述した」こととされます。
裁判長は、当事者の主張や証拠に矛盾や不明確な点があれば、質問したり、次回期日までに明らかにするよう準備することを命じます。
④準備書面
自分の主張や、相手の主張に対する反論なを準備書面として提出します。証人の申請や鑑定の申請などを含め、すべてを書面で提出するのが原則です。
証拠書類には、原告側からの提出は「甲第○号証」、被告側からの提出は「乙第○号証」という番号を付けます。
⑤争点整理
争点整理は、証拠調べを合理的・効率的に行えるように、争点と証拠を整理する手続きです。
争点整理手続には、法廷で行う「準備的口頭弁論」、法廷以外の準備室等で行う「弁論準備手続」、裁判所に出頭することなく準備書面の提出等により行う「書面による準備手続」の3種類があります。
もっとも多いのは、弁論準備手続です。この手続を通して、双方の主張を整理し、裁判所と当事者との間で、その後の証拠調べによって証明すべき事実を確認します。
⑥証拠調べ
口頭弁論や争点整理手続で争点が明らかになれば、その争点について明らかにするために、書証の取り調べ、証人尋問・当事者尋問を行います。このように、提出された証拠を調べ、証人に尋問するなどの手続きが、証拠調べです。
書証には、当事者の陳述書、医療記録、刑事記録(実況見分証書・供述調書)、現場写真等、ドライブレコーダー、私的鑑定書(事故状況について工学的知見を有する者の意見書、後遺障害の程度等に関する医師の意見書など)があります。
なお、交通事故の民事訴訟では、尋問が行われることはほとんどありません。
申出があった証拠を調べるかどうかは裁判所の判断にゆだねられています。一方で裁判所は、基本的に、原告や被告からの申出がない証拠調べをすることはできません。提出する証拠は極めて重要で、慎重に吟味する必要があります。
⑦和解
審理が進み、どちらの主張がどのくらい認められるかが見えてきた段階で、裁判官から話し合いによる解決を勧められることがあります。これが和解勧告です。
裁判官の和解勧告に従い和解するのが「裁判上の和解」です。和解の場合は、法廷でなく、裁判官室などで記録をとらずに話し合いを続け、双方が譲歩しあい、解決に至ります。
和解が成立すると和解調書が作成されます。和解調書は、確定判決と同じ効力があり、相手が履行しないときは強制執行が可能です。
交通損害賠償事件の約7割が和解によって解決していることは知っておいてください。
特に、証人尋問を行い、証拠調べが終わった段階での和解勧告の内容は、裁判官が判決を書いた場合の内容に近いものとなります。その点を考慮し、裁判官の考えをよく聞いて、和解するかどうか判断するとよいでしょう。
⑧判決
口頭弁論が終結すると、判決が言い渡されます。判決書は、後日送達されます。
訴えを提起する裁判所
訴えを提起するとき、裁判所には管轄があります。大きくは「事物管轄」と「土地管轄」があります。
事物管轄
請求金額(訴額)が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に、訴えを提起します。
請求金額が60万円以下の場合は、簡易裁判所での少額訴訟も利用できます。
| 訴額 | 管轄 |
|---|---|
| 請求金額が140万円を超える場合 | 地方裁判所 |
| 請求金額が140万円以下の場合 | 簡易裁判所 |
土地管轄
民事訴訟法では、原則として、被告の住所地を管轄する裁判所に提訴することとされていますが、交通事故の損害賠償請求訴訟は、原告(被害者)の住所地を管轄する裁判所や、交通事故の発生場所を管轄する裁判所にも、訴えを提起することができます。
一般的には、被害者側が出頭しやすい「原告(被害者)の住所地を管轄する裁判所」を選択することが多いようです。
被告(加害者)の住所地を管轄する裁判所
訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する(民事訴訟法4条1項)と定められています。これを「普通裁判籍」による管轄といい、民事訴訟の土地管轄の基本です。
人の普通裁判籍は住所・居所(民事訴訟法4条2項)、法人の普通裁判籍は主たる事務所・営業所の所在地(民事訴訟法4条4項)を管轄する裁判所の管轄となります。
このほか、次のような「特別裁判籍」も認められています。
原告(被害者)の住所地を管轄する裁判所
「財産権上の訴え」については、「義務履行地」を管轄する裁判所に提起できます(民事訴訟法5条1号)。金銭債権は持参債権となるので、債権者の現住所が義務履行地となります(民法484条)。したがって、被害者の住所地を管轄する裁判所に提訴できるのです。
交通事故の発生場所を管轄する裁判所
「不法行為に関する訴え」については、「不法行為があった地」を管轄する裁判所に提起できます(民事訴訟法5条9号)。交通事故の発生場所が、「不法行為があった地」となり、事故発生場所を管轄する裁判所に提訴できます。
合意管轄
当事者双方が管轄合意すれば、一審に限りますが、本来の管轄とは異なる裁判所を管轄裁判所として、訴えの提起をすることができます(民事訴訟法11条1項)。
被害者・加害者双方に代理人がついて示談交渉が先行している場合、双方の代理人にとって都合が良く、当事者にとっても支障がないような場合に、合意管轄が見られるようです。
併合管轄
損害賠償義務者が2人以上存在し、その全員を共同被告とするときは、そのうちの1人について管轄のある裁判所に他の被告についても訴えを提起できます(民事訴訟法7条、38条前段)。
原告となるのは誰か?
原告となるのは、原則として、傷害事故の場合は被害者本人、死亡事故の場合は相続人です。
死亡事故や重度の後遺障害の場合は、固有の慰謝料請求権を持つ近親者が、被害者や相続人と共に原告となることができます。「固有の慰謝料請求権を持つ近親者」とは、被害者の「父母、配偶者および子」です(民法711条)。法定相続人は「配偶者および子」ですから、近親者と法定相続人は必ずしも一致しません。
被告となる相手方を誰にするか?
交通事故による損害賠償責任については、民法や自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められ、損害賠償義務を負うのは、直接の加害者である運転者だけとは限りません。賠償義務者が複数となる場合もあります。
支払い能力や立証の難易などを考慮して決める
賠償義務者が複数存在する場合、「相手方の支払い能力」や「立証の難易」などを考慮して、被告とする相手方を選択することになります。
被告となる相手方を誰にするか、ごく大まかには次のように言えます。
- 自賠法が適用となる人身事故の場合は、運行供用者と運転者を被告とします。
- 自賠法の適用がない物損事故の場合は、原則として加害者(運転者)を被告とします。加害者の勤務する会社の使用者責任を追及できる可能性があるときは、使用者も被告とします。
一般的には、運行供用者を被告とすれば、運転者を被告とする必要はありませんが、運転者を被告としない場合、将来、その運転者の証言が必要になったときに、転勤や退職などで連絡が取れず困ったことになる場合があります。運転者も被告とするかどうかは、提訴の際に慎重に検討することが必要です。
自賠法でいう「運転者」とは、「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいい、マイカーの運転者は、たいてい「運行供用者」となります。運行供用者と運転者の違いはこちらをご覧ください。
任意保険会社を被告に加える? 加えない?
損害保険は、契約者や被保険者が賠償金を支払ったときに、その損害を填補するものです。
つまり、任意保険会社の責任というのは、被害者と加害者(保険の契約者・被保険者)との間で「示談」「裁判上の和解」「判決の確定」によって、初めて賠償義務を負う停止条項付きの責任です。
ですから、任意保険会社が保険契約の効力を争っているような場合を除き、保険会社を被告に加える必要性は乏しいとされています(『交通損害関係訴訟』青林書院)。
なお、自動車保険約款に、被害者直接請求権を規定している場合、これにもとづく直接請求権を訴訟物として、任意保険会社を被告に加えることもできます。
自賠責保険会社を被告とするケース
次のような場合には、自賠責保険会社を被告として提訴するケースがあります。
- 自賠責保険で無責と判断された場合
- 自賠責保険会社の算定した損害額が保険金額の上限に達しておらず、裁判所基準で算定した損害額が、自賠責保険会社の算定した損害額を上回る場合
1つ目のケースは、相手の損害賠償責任を争う場合です。2つ目のケースについて、簡単に説明しておきましょう。
自賠責保険の保険金額(保険金の支払限度額)は、自賠法13条1項において「責任保険の保険金額は、政令で定める」とし、自賠法施行令2条で定めています(死亡による損害につき3千万円、傷害による損害につき120万円など)。つまり、自賠責保険の保険金額は、法定の金額です。
一方、支払基準は、国土交通省・金融庁の告示として示されています。もちろん支払基準も法律上の根拠(自賠法16条の3)にもとづいて定めたものですが、支払基準は訴訟外で支払う場合の基準であって、裁判所に対する拘束力はありません。法律で定めているのは、保険金額(保険金の支払限度額)のみです。
したがって、被害者は、保険金額の範囲内であれば、自賠責保険会社を相手取って、支払基準により算定した損害額を上回る損害賠償額の支払を求めて提訴することが可能です。
- 保険会社は、保険金等を支払うときは、死亡、後遺障害及び傷害の別に国土交通大臣及び内閣総理大臣が定める支払基準に従ってこれを支払わなければならない。
- 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、前項の規定により支払基準を定める場合には、公平かつ迅速な支払の確保の必要性を勘案して、これを定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
法16条の3第1項の規定内容からすると、同項が、保険会社に、支払基準に従って保険金等を支払うことを義務付けた規定であることは明らかであって、支払基準が保険会社以外の者も拘束する旨を規定したものと解することはできない。支払基準は、保険会社が訴訟外で保険金等を支払う場合に従うべき基準にすぎないものというべきである。
法16条1項に基づいて被害者が保険会社に対して損害賠償額の支払を請求する訴訟において、裁判所は、法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく損害賠償額を算定して支払を命じることができるというべきである。
判決文において法とあるのは、自動車損害賠償保障法のことです。また、法16条1項に基づく請求とは、被害者請求(16条請求)のことです。
まとめ
交通事故の民事裁判(損害賠償請求訴訟)は、本人訴訟も可能です。しかし、訴訟は極めて専門的・技術的な分野なので、自力でやろうとすると、取り返しのつかない不利益を被る危険性があります。
交通事故の損害賠償請求訴訟は、弁護士費用の請求も一部認められるようになっています。任意自動車保険に弁護士費用特約を付けていれば、弁護士費用は保険金で支払うことができます。
交通事故の被害に遭い、損害賠償請求訴訟をお考えなら、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。