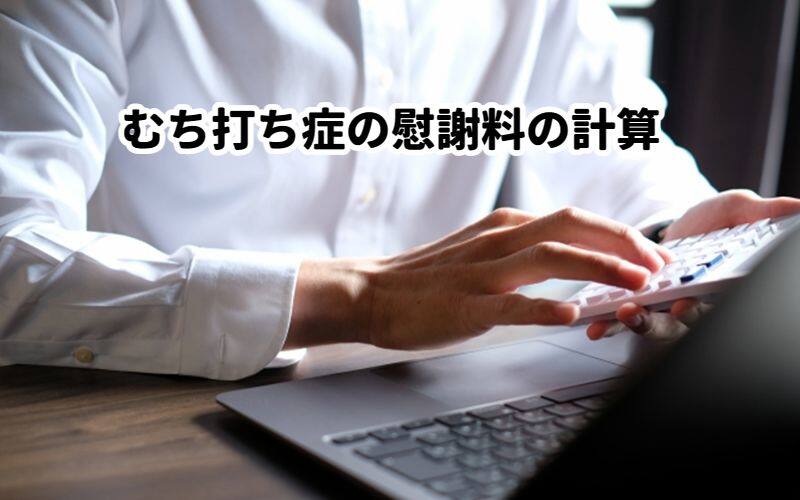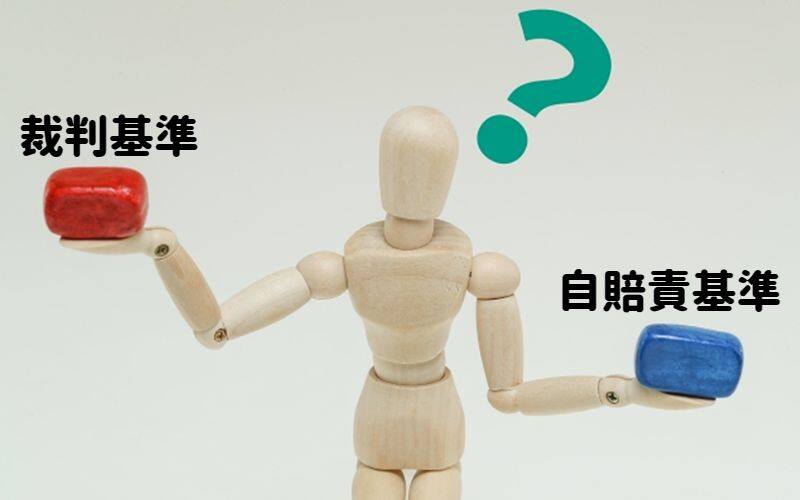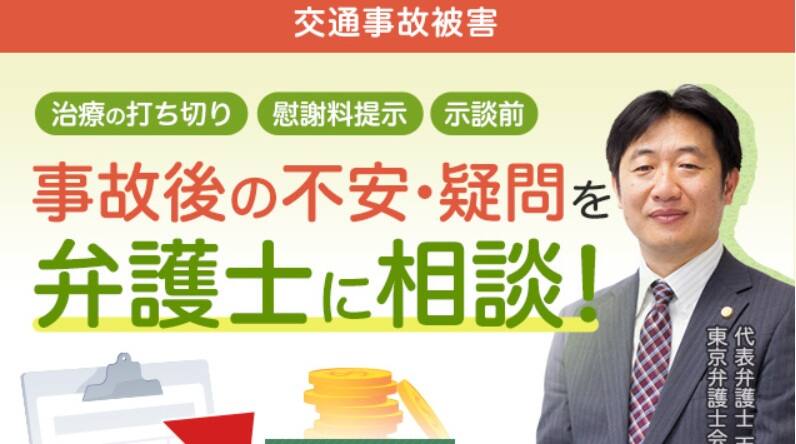※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

交通事故の被害者に「重度の後遺障害」が残った場合は、被害者本人の後遺障害慰謝料とは別に、親族(父母・配偶者・子など)にも「近親者慰謝料」が認められる場合があります。
裁判では、本人慰謝料の2~3割程度の近親者慰謝料が認められるケースが多いようです。
近親者の慰謝料請求権とは?
近親者に対する損害の賠償について、民法では次のように定めています。
民法711条(近親者に対する損害の賠償)
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者および子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
これは、生命を害された被害者の近親者が、慰謝料請求権を有することの根拠規定です。
第三者の不法行為によって被害者の生命が害された場合、民法711条により、被害者の父母・配偶者・子は、たとえ財産上の損害を受けなくても、加害者に対して慰謝料を請求できます。
この民法711条の規定は、被害者が死亡した場合だけでなく、死亡に近い場合にも適用できると解されています。また、父母・配偶者・子以外でも、これに準ずる者も、慰謝料を請求できると解されています。
どんな場合に近親者の慰謝料請求権が発生するか?
最高裁は、父母・配偶者・子のほか、被害者と一定の関係がある者について、被害者の生命を害されたときにも比肩するような精神的苦痛を受けた場合には、「自己の権利」として慰謝料請求権が認められるとする判断を示しています。
「自己の権利」というのは、民法709条、710条にもとづく損害賠償請求権のことです。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由もししくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
民法709条は、不法行為が成立すると、被害者に損害賠償請求権が発生することを定めたものです。民法110条は、精神的な損害の賠償、すなわち慰謝料の請求権が発生することを定めたものです。
近親者の慰謝料請求権を認めた判例
被害者に重度の後遺障害が残り、その家族にも慰謝料請求権が認められた最高裁判例として、次のものがあります。
最高裁判決(昭和33年8月5日)
不法行為により身体を害された被害者の母の慰謝料請求が認容された事例です。
| 裁判要旨 | 不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰藉料を請求しうるものと解するのが相当である。 |
|---|
最高裁判決(昭和39年1月24日)
不法行為により身体の障害を受けた者の父母が自己の権利として慰謝料請求権を有するとされた事例です。
| 裁判要旨 | 12歳の娘が不法行為により身体の傷害を受け、世間並みの幸福な結婚生活をできるかどうかを危惧するなど親として相当の精神的苦痛を味わっている場合、父母は自己の権利として加害者に対し慰藉料の請求ができる。 |
|---|
近親者の慰謝料請求権を認めなかった判例
一方で、後遺障害の程度によっては、近親者の慰謝料請求権を認めなかった判例もあります。
(⇒ 昭和43年6月13日、昭和43年9月19日の最高裁判決)
「被害者が生命を害された場合にも比肩すべきとき」または「生命を害された場合に比して著しく劣らない精神上の苦痛を受けたとき」に限り、自己の権利として慰謝料を請求できるものと解するのが相当である、という判断からです。
父母・配偶者・子以外の慰謝料請求権を認めた判例
民法711条の類推適用により、被害者の父母・配偶者・子以外で慰謝料請求権が認められた事例があります。
最高裁判決(昭和49年12月17日)
被害者の夫の妹に慰謝料請求権が認められた事例です。判決の要旨は、次の2点です。
- 不法行為により死亡した被害者の夫の妹であつても、この者が、跛行(はこう)顕著な身体障害者であるため、長年にわたり被害者と同居してその庇護のもとに生活を維持し、将来もその継続を期待しており、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた等の事実関係があるときには、民法711条の類推適用により加害者に対し慰藉料を請求しうる。
- 不法行為による生命侵害があつた場合、民法711条所定以外の者(条文に明文されてなく、文言上は該当しない者)であつても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、加害者に対し直接に固有の慰藉料を請求しうる。
近親者慰謝料が認められる「重度の後遺障害」とは?
最高裁のいう「被害者が生命を害されたにも比肩するような精神的苦痛を受けた場合」とは、どのような後遺障害が該当するのでしょうか。
後遺障害等級が高位の場合、特に第1級に認定される場合は、ほとんどの判例において、請求すれば認められているようです。
後遺障害等級が低くても、近親者慰謝料を認めた判例もあります。ただし、代わりに、本人分の慰謝料が低くなったり、介護料が認められて当然の場合でも認められなかったりして、残念ながら、高位の後遺障害等級ほどは認められないようです。
重度の後遺障害で近親者慰謝料が認められた判例
重度の後遺障害で、近親者慰謝料が認められた判例をご紹介します。
後遺障害「1級3号」で、近親者慰謝料が認められた事例
45歳・兼業主婦が、四肢不全麻痺等で後遺障害1級3号に認定。傷害慰謝料360万円のほか、後遺障害慰謝料として、本人分2,800万円、夫400万円、子2人各200万円、父母各100万円、後遺障害分合計3,800万円を認めた。
(東京地裁・平成16年5月31日)
後遺障害「併合2級」で、近親者慰謝料が認められた事例
27歳・女性会社員が、右下肢欠損、高次脳機能障害、右股関節機能障害、左大腿部醜状、背部醜状で、後遺障害併合2級に認定。傷害慰謝料321万円のほか、後遺障害慰謝料として、本人分2,500万円、父母各100万円、姉妹2人各50万円、後遺障害分合計2,800万円を認めた。
(横浜地裁・平成23年5月27日)
軽度の後遺障害で近親者慰謝料が認められた判例
軽度の後遺障害で、近親者慰謝料が認められた判例をご紹介します。
- 併合4級の12歳・男子の父母に各100万円を認めた。
(東京地裁・平成6年1月18日) - 高次脳機能障害等(5級)の10歳・男子の父母に各250万円を認めた。
(名古屋地裁・平成25年3月19日) - 左下肢短縮による歩行障害等(7級)の72歳・主婦の夫に100万円を認めた。
(横浜地裁・平成6年6月6日) - 頸部外傷、頭蓋陥没骨折、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜外血腫の傷害を受け、神経障害(12級)の1歳・男子の父母に各30万円を認めた。
(神戸地裁・平成8年5月30日)
近親者慰謝料の額
被害者死亡の場合は、被害者本人の慰謝料請求権を近親者が相続します。そのため、近親者の固有の慰謝料請求をしなくても、本人分と近親者分を合わせて慰謝料総額が変わらないように判断されます(⇒ 死亡慰謝料の詳細はこちら)。
一方、後遺障害の場合は、被害者本人の後遺障害慰謝料に、近親者慰謝料が上乗せされます。ですから、被害者死亡の場合に比べて、後遺障害の場合は、被害者本人分に加え近親者慰謝料を請求すると、認められる慰謝料総額が高額になります。
これは、被害者の日常的な介護などのために、近親者自身の自由が奪われる精神的苦痛が考慮されるからです。
示談交渉はもちろん裁判においても、請求額を超えて慰謝料が認められることはありませんから、被害者の介護などで近親者慰謝料が認められる可能性がある場合は、近親者慰謝料分も算定し、被害者本人の後遺障害慰謝料と合わせて慰謝料請求することが大切です。
なお、近親者慰謝料の金額は、ケースにより異なりますが、被害者本人慰謝料の2~3割程度を認めることが多いようです。
まとめ
後遺障害が残ったときは、被害者本人の慰謝料に加え、家族や親族も慰謝料請求が認められることがあります。そのため、後遺障害の場合の慰謝料総額の方が、被害者死亡の場合の慰謝料よりも高額になることが多くあります。
近親者慰謝料は、被害者の家族や親族が請求しない限り、保険会社みずからが賠償額に算入するものではありません。近親者慰謝料を請求できる可能性がある場合は、交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士と相談して、請求することが大切です。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。