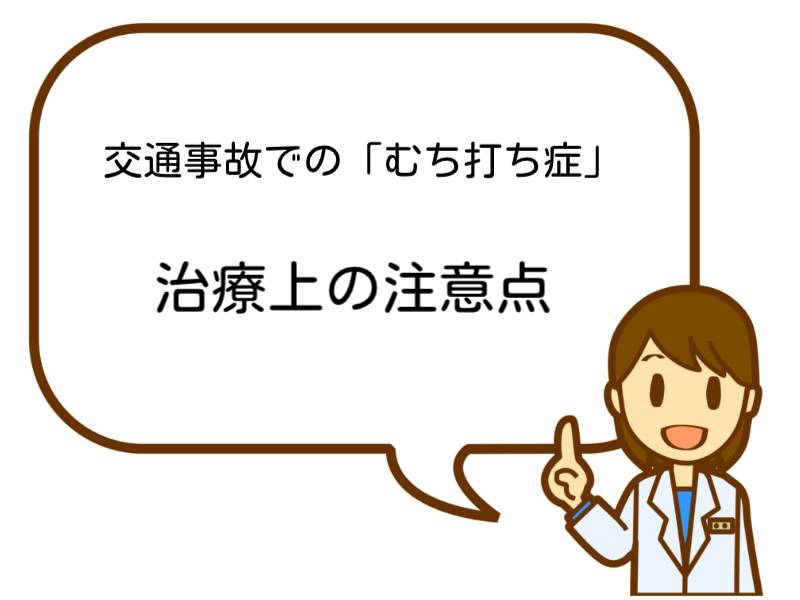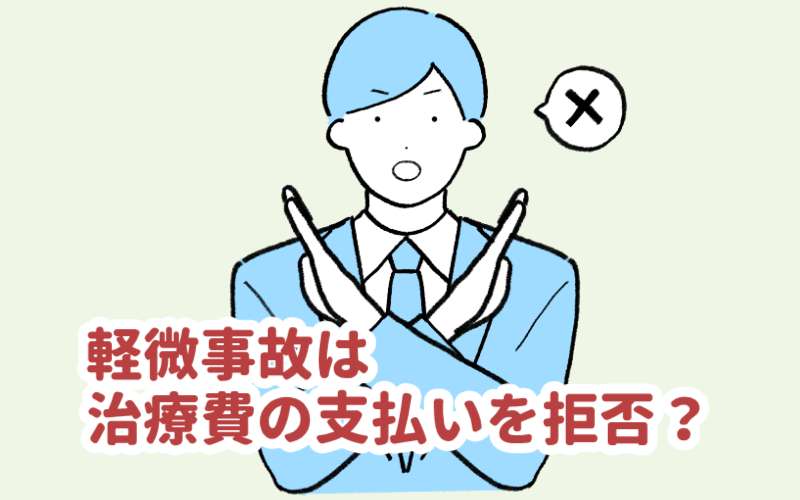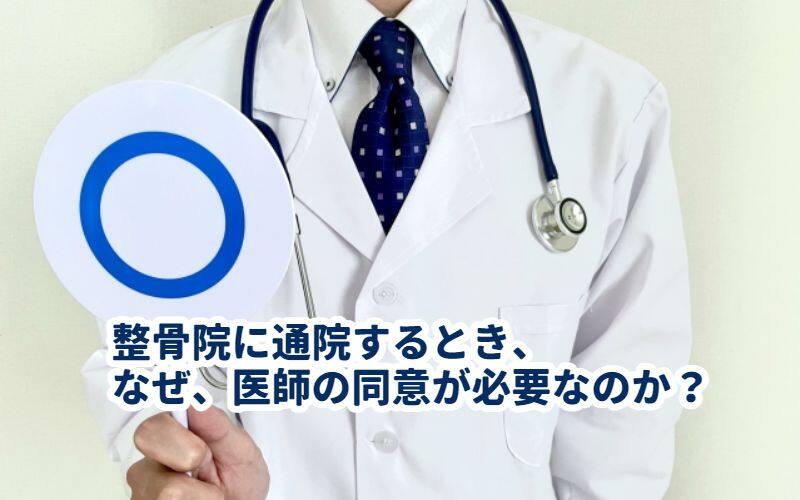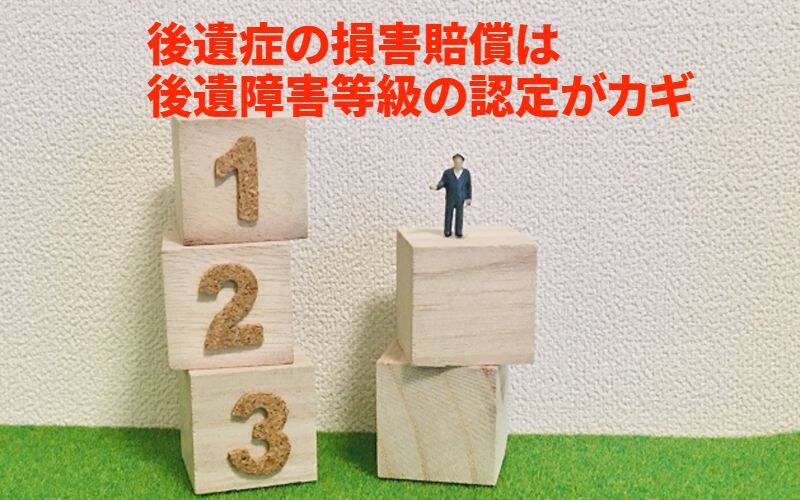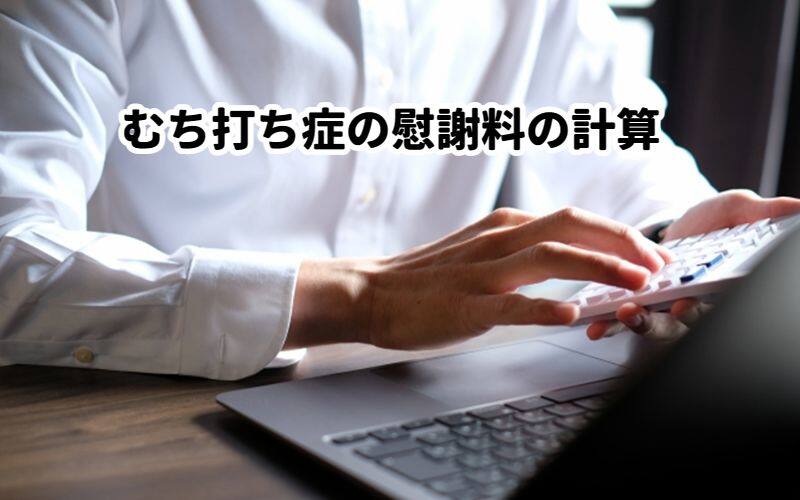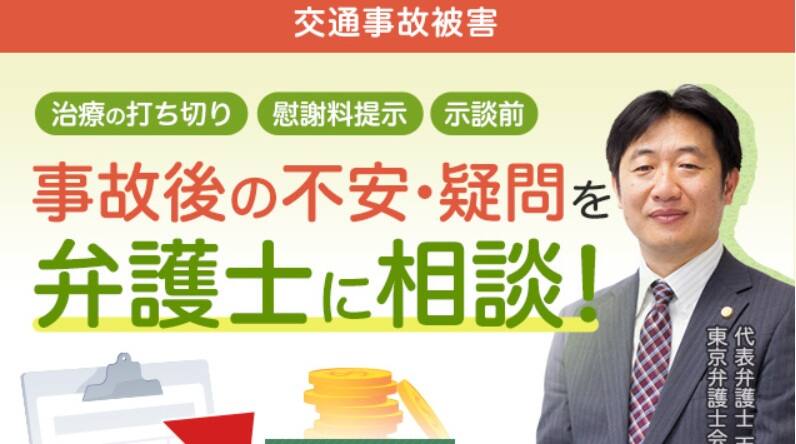ここでは、むち打ち損傷(むち打ち症)とはどういうものか、むち打ち損傷の発生メカニズムや症状について、詳しく解説します。むち打ち損傷(むち打ち症)とは?まず押さえておきたいのは、むち打ち損傷(むち打ち症)とは、診断名・傷病名でなく、受傷の仕方(受傷機転)を示す用語である、ということです。もともと「むち打ち損傷」とは、頭部への慣性外力による頸部の連続的な過伸展(後屈)と過屈曲(前屈)を伴う「むち打ち運動」のために生じる特殊な損傷を意味しています(『賠償科学概説』民事法研究会 109ページ)。その損傷とは、「骨折や脱臼のない、頸部脊柱の軟部支持組織(靭帯、椎間板、関節包および頸部筋群の筋、筋膜)の損傷」(同前)との説明が一般的ですが、軟部組織が損傷したかどうかさえも明らかでありません。臨床的には、事故で「頸部が振られたことによって生じた頭頸部の衝撃によって、X線写真上、外傷性の異常を伴わない頭頸部症状を引き起こしているもの」(『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 6ページ)、つまり、「骨折や脱臼なく、頭頸部症状を訴えているもの」は、広く「むち打ち損傷」と捉えられています(『臨床整形外科2023 Vol.58 №11』医学書院 1303ページ)。診断名・傷病名としては、頸椎捻挫、頸部捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群、外傷性頭頸部症候群、むち打ち関連障害、むち打ち症候群など様々ですが、いずれも、ほぼ同じ病態を指しています。近時は「外傷性頚部症候群」を用いることが多くなっているようです。外傷性頚部症候群とは、自動車事故などの様々な外力によって発生した多様な頸部愁訴を包含する症候群です(『臨床整形外科2023 Vol.58 №11』医学書院 1304ページ)。むち打ち症(外傷性頚部症候群)は、自覚症状としては、頸部痛、頭痛、上肢や手指のしびれ、めまい、など多様ですが、他覚所見に乏しいため、保険金・賠償金めあての「詐病」を疑われやすい傷病でもあります。頸部の構造むち打ち損傷の発生メカニズムや症状の説明の前に、頸部の構造を簡単に見ておきましょう。人間の頭頸部は、「重たい頭」が「細い頸(くび)」にのっている状態で、非常に不安定な構造です。頸部に位置する頸椎は7個の椎骨からなり、その周りを筋肉や靭帯などの軟部組織が取り巻いて、「重たい頭」を支え、安定を保っています。むち打ち損傷は、椎骨の骨折を伴う骨傷ではなく、大半は単純な頸部軟部組織の捻挫であり、それほど重篤なものとは把握されていません。頸椎骨は、上から順に、第1頸椎(C1)から第7頸椎(C7)と呼ばれます。椎骨と椎骨は、軟骨組織である椎間板によって連結されており、椎間板は、骨同士の円滑な動きを確保するとともに、衝撃や圧迫を吸収する緩衝材として機能しています。頸椎骨が重なることで椎孔は管状の脊柱管を構成し、その脊柱管の中に脊髄が通っています。頸椎部分では、脊髄から左右8本の神経根が分岐しており、、神経根内には運動神経と知覚神経が併走しています。神経根が圧迫や刺激を受けると、その神経根の支配領域の身体部位に痛みやしびれ等の神経症状が現れます。(参考:『後遺障害入門』青林書院165~166ページ、『標準整形外科学第14版』医学書院505~509ページ)むち打ち損傷の発生メカニズム急激な加速度・減速度が加わると、頸部は「重い頭」をのせたまま前後に揺れ動きます。それは、あたかも鞭を振り上げて強く打ち付けたような動き(むち打ち運動)です。その結果、頸部が受傷します。これが、むち打ち損傷です。『最新医学大辞典 第3版』(医歯薬出版株式会社)では、むち打ち損傷を「過屈曲過伸展損傷」として説明しています。過屈曲過伸展損傷(むち打ち損傷)典型は、自動車事故での後方からの追突にみることができる。この場合、座席に固定されている体幹は、追突により自動車と同じように急速に前へ押し出されるが、細い頸部につながれた頭部は、慣性で後へ取り残され激しく後屈し、ついで反動で前方へ屈曲する。この一連の動きは、鞭の先の動きに似ているので、むち打ち損傷の名で呼ばれることが多かった。受傷外力を正確に説明する意味では、本名称のほうが正確である。(『最新医学大辞典第3版』医歯薬出版株式会社 267ページ)過伸展・過屈曲とは?頸椎の運動には、屈曲(曲げる運動)、伸展(うしろに反らす運動)、側屈(左右に曲げる運動)、回旋(左右を向く運動)の4種類があります。正常な頸椎の運動の範囲は、屈曲:顎が胸の前面に触れるくらいまで伸展:横から見て下顎の源が水平線から30~40度くらい上向きになる程度まで側屈:耳がかろうじて肩に触れるまで回旋:真横を向けるくらいまでといわれます(『むち打ち症教室』(同文書院55ページ)。『標準整形外科学』では、頸部の関節可動域について、次のように記しています。運動方向参考可動域角度屈曲(前屈)60度伸展(後屈)50度回旋左回旋60度右回旋60度側屈左側屈50度右側屈50度(『標準整形外科学第14版』医学書院942ページ)。車両の衝突などの外力により、屈曲・伸展の正常な可動範囲(生理的可動範囲)を超える運動が頸椎に生じると、過屈曲・過伸展となり、損傷が生じるのです。特に問題となるのが、過伸展です。なぜ過伸展の方が問題なのか?頸椎の屈曲(前屈)は、顎が胸に当たるところで一応は止まります。側屈も、頭が肩に当たるところで一応は止まります。頸椎の動きが、この範囲に止まるくらいの外力であれば、正常な頸椎の可動範囲に近いので、あまり重大な傷害は起こりません。もちろん、屈曲・側屈を強制する外力が強い場合は別です。これに対して、過伸展(後屈)を強制された場合は、頸の後方に、頭の動きを止めるものが何もありません。つまり、後頭部が背中にぶつかるまでは、過伸展を強制する力は止まりません。そのため、外力の程度によっては、骨折、さらには脊髄の損傷をともなう重大な結果を招きやすいのです。(参考:河端正也『むち打ち症教室』同文書院 61~62ページ)むち打ち損傷の発生機序それでは、むち打ち損傷の発生機序(発生メカニズム)について見ていきましょう。従来の説明従来、むち打ち損傷については、こう説明されていました。追突を受けると、その衝撃によって、躯幹(からだ)は座席によって前方へ急激に押し出されますが、重い頭は慣性の法則で後方に取り残され、のけぞるように頸部が過伸展状態(後屈)になり、次の瞬間には、その反動で前方に屈曲(前屈)します。続いてまた伸展というように、前後方向の振動が起こります。ちょうど、鞭を強く振った状態です。これが、むち打ち運動です。このときに、頸部の組織が、正常の限界を超えて引き伸ばされたり、部分的な断裂を起こします。また、このような鞭打ち現象が起こっているときに、頸椎は上下に強く圧縮され、椎骨と椎骨が互いに押しつけられるような状態となります。このため、椎骨と椎骨の間にある椎間関節やその他の部分が損傷されたり、ある場合には損傷された靭帯の間を椎間板が突出してヘルニアを起こすことがあります。(参考:『交通事故における むち打ち損傷問題第3版』保険毎日新聞社340ページ、『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 68~69ページ)むち打ち運動が起きなくても「むち打ち症」は生じる?現在は、頸椎の過伸展を抑制するために開発されたヘッドレストレイントがあり、適正な高さのヘッドレストレイントが装着されていれば、単なる追突事故では「むち打ち運動」は生じにくくなっています。ところが、追突事故などで、いわゆる「むち打ち症」の症状を訴える被害者は減っていません。その発症原因としては、頸部の過伸展・過屈曲(むち打ち運動)というよりも、頭部の急激な後屈を止めるために、後頚部の筋群が反射的に過緊張・収縮したり、後頭部や頸部をヘッドレストレイントで打撲したときなどに軽微な筋断裂や小出血が発生することの方が多いと考えられています(『賠償科学概説』民事法研究会109ページ)。また、ボランティアによる実験から、「低速度車両衝突が、頸椎の過伸展・過屈曲を惹起しないことが明らかになり、頸部のむち打ち状態にならなくとも、むち打ち損傷の症状が出現することがある」ということも分かっています(『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版152ページ)。つまり、事故で頭頸部に「むち打ち運動」が起きていなくても、いわゆる「むち打ち症」の症状が発症することがあり得ます。むち打ち損傷の発生メカニズムは、医学的・工学的に明らかとなっているわけではないのです。むち打ち損傷といわれるようになった理由「むち打ち損傷(むち打ち症)」という言葉は、1928年に米国の整形外科医Crowe(クロウ)博士が、交通事故に起因する新たな頚部傷害例の報告として「whiplash injury(むち打ち損傷)」という言葉を使ったのが最初とされています。河端正也医師が『むち打ち症教室』(同文書院、1990年)で、次のように「むち打ち損傷という名のおこり」について紹介しています。むち打ち損傷という名のおこり1928年、サンフランシスコで開催された西部整形外科学会で、当時はまだ新進気鋭の若手整形外科医であったハロルド・ディー・クロウ博士は、治療に苦労している8例の交通事故によるくびの外傷について報告しました。これらの患者さんは、すべて普通の検査では何ら悪いところが発見されないのに、頑固な頭痛や、めまい、はきけ、頸部(くび)の痛みなどが、交通事故、おもに追突されて以来起こっているのでした。彼がこれらの症例を報告しようとした理由は、どうも自分の手には負えないので、多くの整形外科医の意見を聞きたいということだったのです。報告の中で彼は、これらの外傷の起こったメカニズムを説明するつもりで「whiplash injury(むち打ち損傷)」という言葉を使いました。当然のこととして、彼は、この言葉が病気の名前として受け取られるなどとは夢にも考えていませんでしたし、聴衆の整形外科医たちも、そうだったはずだったのです。ところがどうでしょう。この名前は一般の人々、ジャーナリスト、法律家、ひいては医師たちの間ですら、病名として猛威をふるい、以来40年近く数多くの議論と社会問題を巻き起こしながら、日本にもやってきました。(河端正也著『むち打ち症教室』同文書院 17~18ページ)この説明で注目してほしいのは、2つの点です。1つは、むち打ち損傷とは、外傷の発生メカニズムを説明するために用いた言葉であり、傷病名ではないということ。もう1つは、交通事故による頸部傷害例として、いろいろ検査をしても悪いところは発見されない(他覚的所見がない)のに、頑固な頭痛や、めまい、吐き気、頸部の痛みなどが続く症例が、古くからあったということです。ともすると、加害者・保険会社側は、他覚所見のない「むち打ち症」を賠償金や保険金めあての「詐病」や「神経症」などと決めつけがちですが、賠償金や保険金など全く関係のないケースでも、このような症状が長く続く症例は、古くから存在していたのです。では、むち打ち損傷は、どんな症状が出現するのか、詳しく見ていきましょう。むち打ち損傷の症状と分類日本整形外科学会のWebサイトでは、「外傷性頚部症候群」の症状として、「交通事故などで頸部の挫傷(くびの捻挫)の後、長期間にわたって頸部痛、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれ、などの症状が出て、X線(レントゲン)検査での骨折や脱臼は認められません」と解説されています。「むち打ち症」については、同サイトで、「いわゆる “むち打ち症” は、追突や衝突などの交通事故によってヘッドレストが整備されていない時代に首がむちのようにしなったために起こった頚部外傷の局所症状の総称」と説明されています。なお、外傷性頚部症候群は、頸部が鞭のようにしならない(すなわち「むち打ち運動」が生じない)、軽微な外傷による病変も含まれます(『臨床整形外科2023 Vol.58 №11』医学書院 1341ページ)。したがって、正しくは、外傷性頚部症候群の症状・分類として説明すべきところですが、追突事故などによる頸部の外傷を(むち打ち運動の有無にかかわらず)、いまも一般に「むち打ち症」と呼ばれているため、ここでは、むち打ち損傷の症状・分類として説明します。むち打ち損傷の症状むち打ち損傷による症状の多くは、頸部痛や頭痛です。しかし、むち打ち損傷で生じる症状は、頸(くび)の痛みや頭痛だけではありません。むち打ち損傷による症状は多彩です。事故態様(衝突方向や速度、事故予測の有無、ヘッドレストの位置など)や、被害者の姿勢・頸椎の状態(頸椎症性変化・椎間板膨隆などの有無)など、多くの因子によって傷害発生部位は変化し、症状も異なります。受傷直後、急性期、慢性期、それぞれの症状の特徴を見ていきましょう。受傷直後~急性期むち打ち損傷による症状は、事故直後には痛み等の自覚症状がなく、事故の数時間後、あるいは、事故の翌朝に症状が現われることが多いようです。もっとも、いつ症状が出現するかは一概に言えず、事故から2~3日後に出現することもあれば、もう少し後になって出現することもあります。事故直後もちろん、事故直後から症状が出現することもあります。軽い脳震盪や頸部軟部組織損傷を原因とし、頭がボーッとした状態になったり、項部痛・圧迫感・緊張感、吐き気、意識混濁、頭痛、上肢のしびれ感・脱力感などを感じることがあります。これらの症状は、重症例を除き、大部分のものは数時間以内に消失するといわれています。急性期・初発症状(受傷後数時間~1週間)急性期・初発症状(受傷後数時間~1週間)の自覚症状としては、頸椎支持組織の損傷を原因とし、頸部痛・圧迫感・緊張感、頭痛・頭重感、頸椎運動制限、肩こり、吐き気、上肢のしびれ感、腰痛などがあります。他覚所見としては、頸椎運動制限、項頸部筋の圧痛などが見られます。急性期・後発症状(受傷後2~4週間以後)急性期・後発症状(受傷後2~4週間以後)の自覚症状としては、頭痛、めまい、悪心、耳・眼症状、上肢放散痛などがあります。バレー・リュー症状が出現します。バレー・リュー症状とは、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、視力低下、聴力低下などの自律神経症状を呈するものです。むち打ち損傷では、自律神経症状を併発する場合があります。他覚所見としては、知覚障害や神経根症状などの神経学的陽性所見の増加、椎間板損傷によるX線検査上の椎間腔狭小化や変形性頸椎症所見の出現が見られます。(参考:『改訂版 後遺障害等級認定と裁判実務』新日本法規302ページ、『賠償科学概説』民事法研究会114ページ)慢性期慢性期における症状としては、頸部痛、頭痛、めまい、頭部・顔面領域のしびれ、眼症状、耳鳴り・難聴、吐き気・嘔吐、四肢症状、腰痛、バレー・リュー症候群による脳幹・自律神経症状があります。そのほか、不眠、集中力低下、易疲労感、微熱感、記銘力低下なども報告されています。これらの症状は不定愁訴と捉えられがちですが、軽微な脳損傷が発生している可能性も指摘されています。むち打ち損傷は、軽傷の部類に入るため軽視されがちなところがありますが、くびの痛みだけでなく、自律神経症状や認知機能障害、神経疾患まで幅広く合併する可能性がありますから、注意が必要です。(参考:『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 49~59ページ、『交通事故診療のピットフォール』日経メディカル122~125ページ)なぜ、事故直後は痛みを感じず、あとから痛みを感じるのか?一般的には、「事故直後は、精神的に緊張状態にあり、肉体的にも、損傷を受けた頸(くび)の周囲の筋肉が自動的に緊張して副木をあてたような状態にあるのが、落ち着いてくると、事故のことよりも怪我のことを考える余裕が出てくることによる」と考えられています(河端正也著『むち打ち症教室』同文書院 71ページ)。事故によって器質的な損傷が生じていないにもかかわらず、数時間後に頸部痛が発生し、症状が遷延化するメカニズムとして、頸椎椎間関節内に介在する滑膜組織が、追突による衝撃によって損傷し、数時間後に滑膜炎が惹起され、疼痛・可動域制限を生じる、とする説があります(『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版44ページ)。むち打ち症の平均的な治療期間と保険会社の治療費打ち切りの判断基準むち打ち損傷の分類臨床的には、「むち打ち損傷の診断をするときは、むち打ち損傷によって何が生じているかを考えることが重要」とされます(『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 6ページ)。むち打ち損傷によって生じる傷病には、いくつかの分類方法があります。土屋分類日本で代表的な分類は「土屋分類」です。「土屋分類」によれば、むち打ち損傷は、次のような5類型に分類されます。頸椎捻挫型頸椎捻挫型は、頸部の筋の過度の伸長ないし部分断裂の状態で、頸部周囲の運動制限、運動痛が主症状です。神経症状は認められません。予後良好で、大部分がこのタイプです。根症状型根症状型は、頸神経の神経根の症状が明らかで、頸椎捻挫型に加え、知覚障害、放散痛、反射異常、筋力低下などの神経症状をともないます。バレー・リュー症候群型バレー・リュー症候群型は、自律神経症状や脳幹症状が出現し、頭痛、めまい、耳鳴、眼の疲労、悪心をともないます。神経根、バレー・リュー症状混合型根症状型の症状に加えて、バレー・リュー症状がみられるものです。脊髄症状型脊髄症状型は、深部腱反射の亢進、病的反射の出現などの脊髄症状をともなうものです。この型は、現在ではむち打ち損傷の範疇に含まれず、非骨傷性の頚髄損傷とされるのが一般的です。※ バレー・リュー症候群は、「椎骨神経(頸部交感神経)の刺激状態によって生じ、頭痛、めまい、耳鳴、視障害、嗄声、首の違和感、摩擦音、悪心、易疲労感、血圧低下などの自覚症状を主体とするもの」と定義されています。しかし、その発生原因に関して、定説は確立されていません。ただし、これらの分類は、臨床症状で明確に分類することが難しく、分類別の治療法も確立していません。また、近年は、これらの分類に加え、外傷性胸郭出口症候群、脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)の病態を呈するむち打ち損傷が存在することが報告されています。(参考:土屋分類については『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 6~8ページ)ケベック分類海外では、1995年に発表されたケベック報告による分類(ケベック分類)が普及しています。むち打ち症関連障害(WAD)を症状・重症度により、5段階のグレードに分類したものです。ケベック報告とは、カナダのケベック州自動車保険協会の要請のもとに組織された「ケベックむち打ち症関連障害特別調査団」が、むち打ち症関連障害(WAD)の種々の問題について科学的解析を行い、まとめた報告書です。この報告書にある「むち打ち症関連障害の重症度分類」が、いわゆる「ケベック分類」と呼ばれるものです。頸部愁訴、理学神経学的所見、脊椎の骨折・脱臼の有無からなされた分類です。ケベック分類(WADの重症度分類)grade臨床所見0頸部の愁訴なし、理学的異常所見なしⅠ頸部の愁訴(痛み、こわばり、圧痛)のみ、理学的異常所見なしⅡ頸部の愁訴と、骨・筋肉症状の存在(関節可動域の低下、圧痛点など)Ⅲ頸部の愁訴と、神経学的所見の存在(深部腱反射の低下・消失、筋力低下、感覚障害など)Ⅳ頸部の愁訴と、骨折または脱臼*難聴、めまい、耳鳴り、頭痛、記憶喪失、嚥下障害、顎関節痛などの症状は、どのグレードにも出現し得るとされています。*6ヵ月以上症状を示している場合を慢性化と定義。。(参考:『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 8ページ、『交通事故における むち打ち損傷問題第3版』保険毎日新聞社18ページ、『臨床整形外科2023 Vol.58 №11』医学書院 1304ページ)ケベック分類の「grade0」~「gradeⅡ」が、いわゆる「むち打ち損傷」と認識され、「gradeⅢ」「gradeⅣ」は、外傷性頸髄損傷として分類されます。(『臨床整形外科2023 Vol.58 №11』医学書院 1341~1342ページ)むち打ち損傷で後遺症が問題となるケースむち打ち損傷は、ほとんどの場合、後遺障害を残さずに治癒するとされていますが、事故により受傷した後に、椎間板損傷、神経根症状、バレー・リュー症状、脊髄症状が出現した場合には、その症状が後遺する可能性があるといわれています(『賠償科学概説』民事法研究会 116ページ)。根症状型は、神経根への刺激や圧迫によって、頸部筋、項部筋、肩胛部筋などへの圧痛、頸椎運動制限、運動痛、末梢神経分布に一致した知覚症状、放散痛、反射異常、筋力低下などがみられます。これらの症状の発生原因が他覚所見によって認められれば、後遺障害の等級認定がなされる可能性があります(『改訂版 後遺障害等級認定と裁判実務』新日本法規 303ページ)。バレー・リュー症状型は、その発生原因について定説は確立されておらず、現在においても病態の詳細は不明です。そのため、バレー・リュー症状を他覚的所見によって説明・証明することは難しいとされています(『改訂版 後遺障害等級認定と裁判実務』新日本法規 304ページ)。まとめむち打ち症(むち打ち損傷)は、大半は単純な頸部軟部組織の捻挫で、それほど重篤なものとは捉えられていません。しかし、むち打ち症の発症メカニズムは、いまだ明らかでありません。他覚的所見に乏しく、自覚症状のみのケースがほとんどなので、治療の必要性、症状固定時期や後遺障害の有無をめぐって争いになることが少なくありません。適正な損害賠償を受けるには、治療の段階から早めに、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274 ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『むち打ち損傷ハンドブック第3版』丸善出版 6~9ページ、49~59ページ・『補訂版 交通事故事件処理マニュアル』新日本法規 49~51ページ・『後遺障害入門 認定から訴訟まで』青林書院 164~169ページ・『弁護士のための後遺障害の実務』学陽書房 16~23ページ・『交通事故診療のピットフォール』日経メディカル 122~125ページ・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集―交通事故編―』第一法規 97~98ページ、239~240ページ・『交通事故案件対応のベストプラクティス』中央経済社 26~35ページ、46~62ページ、127~128ページ・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 176~181ページ・『交通事故医療法入門』勁草書房 105~132ページ・『改訂版 後遺障害等級認定と裁判実務』新日本法規 300~304ページ・『交通事故における むち打ち損傷問題 第3版』保険毎日新聞社 11~28ページ・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 132ページ・『賠償科学概説』民事法研究会 108~123ページ