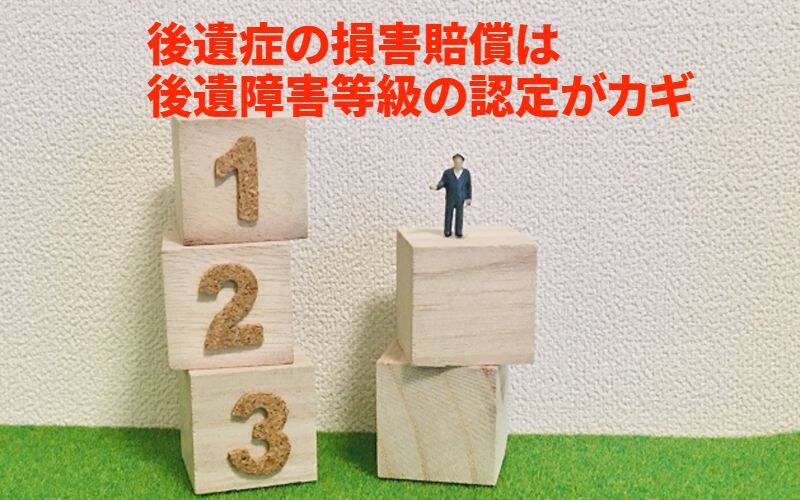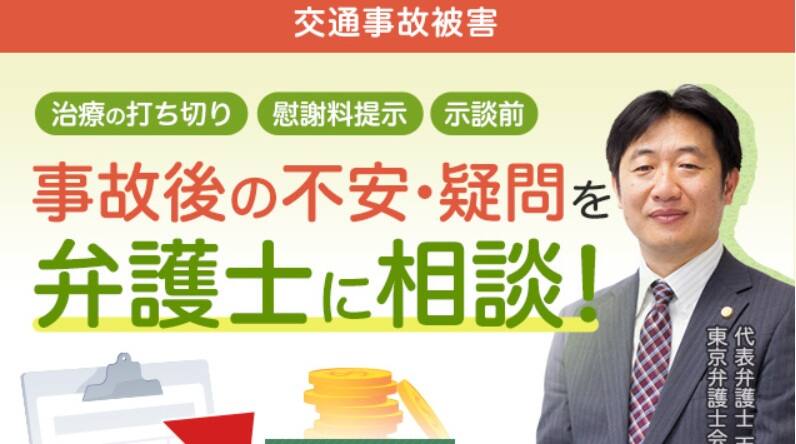「後遺症が残った」というだけでは、後遺症に対する慰謝料等を請求することはできません。後遺症が残ったことで逸失利益や慰謝料を請求するには、自賠責保険において後遺障害等級の認定を受ける必要があります。ここでは、後遺症と後遺障害の違い、後遺障害等級の認定条件、適正な後遺障害等級の認定を獲得するためのポイントについて、解説します。自賠責保険における後遺障害の等級認定は、「原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う」(自賠責保険の支払基準)とされています。また、勤務中の交通事故は、労災補償の対象です。ですから、労災保険の障害補償も参照しながら説明していきます。「後遺症」と「後遺障害」の違い治療しても完全に回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残る場合があります。このような治療終了後に残存する身体・精神の不調を一般的には「後遺症」と呼んでいますが、損害賠償の分野では「後遺障害」と呼びます。「後遺障害」という呼び方が特別に意味をもつのは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)や労災保険(労働者災害補償保険)の支払手続においてです。自賠責保険制度における後遺障害自賠法(自動車損害賠償保障法)は、後遺障害を「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」と定め(自賠法施行令第2条1項2号)、障害の程度に応じて第1級から第14級までの14等級に区分し、各等級ごとに保険金額(支払限度額)を決めています(自賠法施行令第2条別表)。「治ったとき」とは、症状固定に至ったときです。すなわち、症状固定後に残存する障害が後遺障害です。労災補償制度における後遺障害労働基準法は、「労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、……障害補償を行わなければならない」と定めています(労基法77条)。この「傷病が治ったときに身体に存する障害」が後遺障害で、「治ったとき」とは症状固定に至ったときです。労災保険における障害補償も、障害の程度に応じて第1級から第14級までの14等級に区分し、各等級ごとに保険給付額を定めています。そもそも自賠責保険の後遺障害等級が、労災保険の障害等級に準拠したものです。後遺障害は補償対象を規定する法律上の概念後遺症が残った場合、それが自賠責保険や労災保険に定める後遺障害として認定されなければ、原則として保険金は支払われません。後遺症が残ったときは、それが後遺障害に該当するか、どの等級に認定されるか、が重要なのです。このように、「後遺障害」とは、労災補償制度や自賠責保険制度において、補償対象を規定する法律上の概念であり、「等級」は、支払限度額を決定するための格付けです。後遺症も後遺障害も、どちらも「症状固定後に残存する身体・精神の不調」を意味するものですが、後遺障害に該当するか否かによって、保険金(損害賠償額)の支払いを受けられるかどうかが決まります。後遺症が残ったとき、その後遺症が、後遺障害に該当すれば、保険金(損害賠償額)が支払われますが、後遺障害に該当しなければ、保険金(損害賠償額)は支払われません。さらに、認定される後遺障害の等級によって、支払われる保険金額(上限額)が決まります。後遺症と後遺障害の関係は、次のようなイメージです。後遺症後遺障害(保険による補償対象)では、後遺症のうち、どのようなものが後遺障害に該当するのでしょうか?後遺障害の認定条件自賠責保険の後遺障害認定は、労災保険の障害認定の基準に準じて行われます。労災保険における「障害補償の対象」は、「傷病(負傷または疾病)が治ったときに残存する当該傷病と相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復が困難と見込まれる精神的または身体的毀損状態(=障害)であって、その存在が医学的に認められ、労働能力の喪失を伴うもの」としています(『労災補償障害認定必携第17版』労災サポートセンター69ページ)。これを交通事故の場合に当てはめると、①事故による受傷の結果発生した障害(精神的または身体的毀損状態)であって、②永続残存性があり、③その存在が医学的に認められ、④労働能力の喪失を伴うものが、自賠責保険による補償対象である後遺障害ということになります。すなわち、後遺障害に該当するためには、次の4つの条件を満たす必要があります。なお、この4つの条件は、後遺障害の該当性を判断する基本的事項であり、各障害等級ごとの認定基準は別途定められています。後遺障害 4つの条件事故による受傷との間に相当因果関係がある将来においても回復が困難と見込まれる医学的に存在が認められる労働能力の喪失を伴うそれぞれ見ていきましょう。事故による受傷との相当因果関係後遺障害の1つ目の条件は、事故による受傷が原因で残存した障害であるということ、すなわち、事故と相当因果関係があることです。事故により発生した損害の賠償ですから、事故との相当因果関係が要求されます。例えば、既存の障害のある人が、事故で増悪した場合、事故との相当因果関係が争いとなることがあります。永久残存性後遺障害の2つ目の条件は、永久残存性です。後遺障害という用語には、「回復しない」という性質が前提にあります。将来においても機能回復しないだろうと見込まれる状態を念頭においているのです。将来も回復せず障害が残るとして後遺障害が認められると、将来の逸失利益について損害賠償を受けることができます。逆にいうと、障害状態が永久には続かないだろうと見込まれる場合には、後遺障害とは評価されないということです。例えば、頸椎捻挫(むち打ち損傷)による神経症状などは、時間が経てば改善すると考えられ、後遺障害「非該当」と判断されることが多く、仮に後遺障害が認められても、永久残存性が否定され、逸失利益発生期間(労働能力喪失期間)を比較的短期間に限定されるのが一般的です。むち打ち症の後遺障害等級と労働能力喪失期間の問題医学的に存在が認められる後遺障害の3つ目の条件は、障害の存在が医学的に認められることです。医学的に認められるとは、障害の存在を「医学的に証明できる」あるいは「医学的に説明できる」ということです。医学的に証明できるというのは、レントゲン写真などの他覚的所見により、障害を他覚的に証明できることです。医学的に説明できるというのは、他覚的に証明することまではできないけれども、受傷態様や治療経過などから、障害が残存していてもおかしくはない、と医学的見地から合理的に推定できるということです。いくら自覚症状を訴えても、医学的に説明すらできなければ、後遺障害とは認められません。医学的に「証明できる」と「説明できる」の違いについて詳しくはこちら労働能力の喪失後遺障害の4つ目の条件は、労働能力の喪失を伴うということです。そもそも労災保険における障害補償は、障害による労働能力の喪失に対する損失填補を目的とした制度であり、自賠責保険の逸失利益に対する保険金(損害賠償額)の支払いも同趣旨ですから、労働能力の喪失を伴うということは大前提といえます。なお、ここでいう労働能力とは、「一般的な平均的労働能力」をいい、被害者の年齢・職種・利き腕・知識・経験等の職業能力的諸条件は、損害の程度を決定する要素とはなっていません(『労災補償 障害認定必携 第17版』70ページ)。その後遺障害によって労働能力がどの程度失われるのかについては、後遺障害等級に応じて、所定の労働能力喪失率が認められる仕組みです。自賠責保険と労災保険で、後遺障害等級の認定に差が出る?交通事故が労災事故でもある場合、同じ後遺障害であっても、自賠責保険と労災保険とで認定に差が出ることがあります。自賠責保険も労災保険も、同じ「労災補償の障害認定基準」を使用しますが、一般的に、自賠責保険による認定の方が、被害者にとって厳しい結果となるようです。これは、労災保険が本来的には「補償」の性格を有するのに対し、自賠責保険は「賠償」の性格を有する、という制度趣旨の違いに由来していると考えられています(『詳説 後遺障害』創耕舎60ページ注37)。適正な後遺障害等級の認定を受けるためのポイント適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、次の点が重要なポイントとなります。提出書類が後遺障害を裏付けるものとなっているか事前認定でなく被害者請求する交通事故に詳しい弁護士に相談する提出書類が後遺障害を裏付けるものとなっているか自賠責保険における後遺障害等級の審査は、基本的に書面審査です。審査にあたって、被害者本人に状態を聞くこともなければ、診療医から話を聞くこともありません。提出する書類が全てです。ただし、外貌醜状障害などは、面接して醜状を確認します。ですから、後遺障害等級の認定を受けるには、自賠責保険に提出する書類が、後遺障害の存在を裏付けるものとなっていることが大事です。重要なのは、後遺障害診断書と他覚的所見です。自賠責保険において後遺障害として認定されるには、主治医に後遺障害診断書を作成してもらって、自賠責保険に提出します。この後遺障害診断書こそが、症状固定時の残存症状を記載した書類であり、後遺障害申請手続きにおいて最も重要な書類です。後遺障害診断書の見本後遺障害診断書の記載で注意が必要なのが、「自覚症状」と「①精神・神経の障害/他覚症状および検査結果」の欄です。むち打ち症など局部の神経症状の場合には、これらの記載が特に重要です。よくあるのが、簡単な記載にとどまっているケースです。後遺障害の認定が不利になります。もっとも、記載するのは医師ですから、医師に任せるしかありませんが、残存する自覚症状については、医師にしっかり伝えることが大切です。大事なのは、自覚症状が詳しく記載され、その自覚症状を裏付ける他覚症状や検査結果が整合性をもって記載されることです。さらに、それを画像検査などの他覚的所見で客観的に裏付けることができれば、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。こういった点に注意しながら後遺障害診断書を作成してくれる医師ならよいのですが、現実には、そこまで後遺障害診断書の書き方を熟知している医師は多くありません。ここまでやるには、あとで説明するように弁護士の力が必要です。事前認定でなく被害者請求する自賠責保険における後遺障害等級の認定手続には、任意保険会社による「事前認定」と、被害者による「直接請求」(被害者請求)の2つの方法があります。事前認定は、任意保険会社が事務的に自賠責保険に書類を提出するだけです。任意保険会社は、積極的に後遺障害等級の認定獲得を目指すわけではありません。任意保険会社が必要な書類をそろえて手続をしてくれるので被害者は楽なのですが、提出した書類の内容を被害者側で把握することはできません。これに対し、被害者請求は、自賠責保険に提出する書類の内容を精査し、必要なら補足資料を追加で提出することもできるので、適切な後遺障害等級が認定される可能性が高くなるのです。事前認定と被害者請求の違いについて詳しくはこちら交通事故に詳しい弁護士に相談する後遺障害等級の認定には、医師の作成する後遺障害診断書等が重要な役割を果たします。ところが、ここで深刻な問題があります。医師は、傷病の治療については専門ですが、「どうすれば後遺障害等級が認定されるか」ということについては専門ではありません。また、治療費が保険会社から支払われますから、保険会社と揉めたくないという思いが先に立ちます。そのため、保険会社に逆らってまで、被害者のために行動してくれる医師は、残念ながら少ないのです。そもそも後遺障害は賠償上の概念ですから、この分野の専門は弁護士なのです。どのように後遺障害診断書や経過診断書が記載されていれば後遺障害等級が認定されるか、後遺障害等級の認定に必要な検査所見は何か、といったことを判断できるのは、医師ではなく弁護士なのです。ですから、弁護士に相談して的確なアドバイスを受けることで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まるのです。ただし、交通事故の問題は、弁護士にとっても特殊な法律分野となるため、弁護士なら誰でも対応できるわけではありません。交通事故の損害賠償請求に詳しい弁護士に相談することが大切です。関連いつ・どのタイミングで弁護士に相談すればよいか弁護士に依頼する5つのメリット・1つのデメリット交通事故被害者が知っておきたい弁護士選び3つのポイントまとめ後遺症に対する慰謝料などは、後遺障害等級によって決まります。適正な後遺障害等級の認定を受けることが大切です。むち打ち症などは、後遺傷害の認定を受けるのが難しいので、治療中の早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。自賠責保険で後遺障害「非該当」となったり、想定していた後遺障害等級よりも低い等級となった場合は、異議申し立てができます。後遺障害等級の異議申し立てについてはこちら交通事故による被害・損害の相談は 弁護士法人ステラ へ弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!交通事故の被害者専用フリーダイヤル 0120-221-274 ( 24時間・365日受付中!)無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。評判・口コミを見てみる公式サイトはこちら※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。【参考文献】・『労災補償 障害認定必携 第17版』一般財団法人労災サポートセンター69~70ページ・『弁護士のための後遺障害の実務』学陽書房4~14ページ・『交通事故案件対応のベストプラクティス』中央経済社91~100ページ・『詳説 後遺障害』創耕舎19~21ページ、60~63ページ・『後遺障害入門』青林書院3~5ページ、17~19ページ・『改訂版 後遺障害等級認定と裁判実務』新日本法規2~16ページ・『新・現代損害賠償法講座 5交通事故』日本評論社156~159ページ