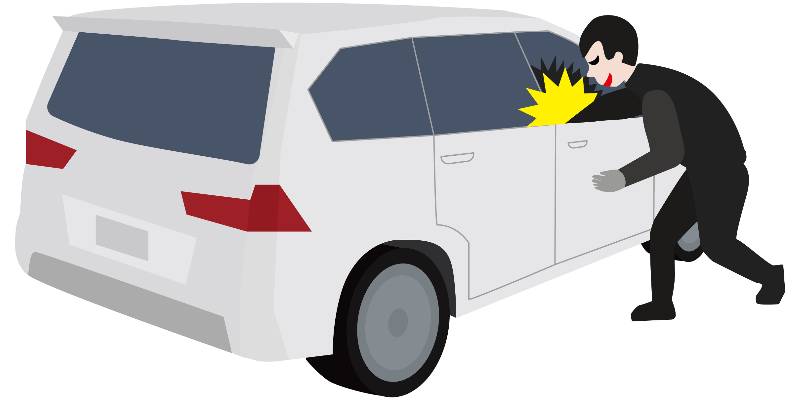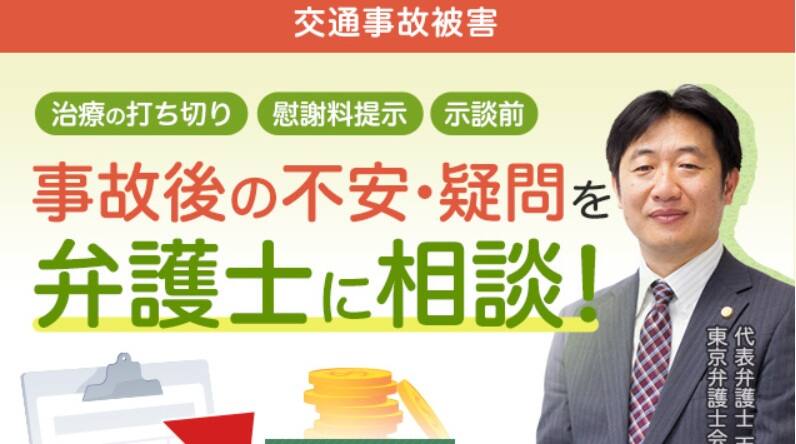※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

会社の車を従業員が無断使用して事故を起こした場合でも、会社の責任を問い、損害賠償請求することができます。
相手の運転者が会社の車を運転していた場合、会社の業務で運転していたのか、無断使用していたのか、客観的には判別できません。そのため、被害者保護の観点から、従業員が会社の車を運転していたことをもって、会社の責任が広く認められる傾向にあります。
会社の責任が否定されるのは、業務外での会社の車の使用を形式的にでなく名実ともに禁止し、車の管理をきちんとしていたにもかかわらず、鍵を壊して持ち出されたようなケースぐらいです。
- 従業員が私用のため会社の車を無断で運転していて交通事故を起こした場合も、会社の責任を問えます。
- 会社の責任が否定されるのは、泥棒運転のようなケースぐらいです。
詳しい解説
さらに詳しく見ていきましょう。
会社の車で従業員が事故を起こしたときの会社の責任
会社の車を従業員が使用して交通事故を起こした場合の会社の責任については、運行供用者責任(自賠法3条)と使用者責任(民法715条)が問題になります。
特に、会社所有の自動車による人身事故については、会社が、事故を起こした自動車の運行について支配と利益があるとされる場合は、被害者の人身損害について運行供用者責任を負います。
また、人身事故に限らず、会社は、従業員が事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する使用者責任を負います。物損事故など運行供用者責任を問えない場合は、会社の使用者責任を追及することになります。
従業員が業務中に起こした事故であれば、運行供用者責任であれ、使用者責任であれ、原則として会社に責任が発生します。
問題となるのは、従業員が会社の車を私用目的で無断で運転して事故を起こした場合ですが、こういうケースも、裁判所は、会社の責任を認める傾向にあります。会社の責任が認められるか、会社の責任が否定されるか、ポイントは次の点です。
【ポイント①】業務で会社の車を運転する形態・頻度
会社の車を無断で使用し事故を起こした従業員が、会社の運転手(運転を職務としている者)や営業で常に会社の車を運転している従業員などの場合と、普段あまり会社の車を運転しない従業員の場合とでは、考え方が少し異なります。
会社の運転手が会社の車を運転中に事故を起こした場合は、それが休日で無断私用運転であったとしても、会社の責任を問えます。運転手という職務は、会社が、運転手に会社の車の管理を全面的に任せている、と考えられるからです。
それに対して、会社の車を普段あまり運転しない従業員が、会社の車を無断私用運転して事故を起こした場合に、会社の責任を問えるかどうかは、次のように車の保管・管理の状況がポイントになります。
【ポイント②】車の保管・管理は適切だったか
車に鍵をかけず放置していたなど、保管・管理がズサンであった場合は、会社の責任を問えます。
一方、車を車庫に入れ、鍵をかけていたのに、「鍵をこじ開けて持ち出された」というような場合は、会社の責任が否定されることがあります。
【ポイント③】業務外での会社の車の使用を禁止していたか
会社の車を業務外で使用することを容認していたなら、会社の責任が生じます。
業務外で会社の車の使用を禁止している場合は、無断使用を許さない措置が厳格にとられていたかどうか、がポイントになります。
形式的に業務外での無断使用を禁止していたとしても、しばしば従業員が私用目的で勝手に持ち出していたような場合は、会社の責任を問うことができます。
会社の責任は「行為の外形」により広く解釈される
従業員が会社の車を私用目的で無断運転して事故を起こした場合、その車の運行は会社の業務ではないので、会社に責任はないように思えるかもしれません。
しかし、従業員が会社の車を運転していた場合、私用であっても、外観は業務で運転している場合と何ら変わらず、業務で運転していたのか、私用で運転していたのか、客観的には判別できません。
そのため、被害者保護の観点から、会社の責任は広く解釈され、行為の外形により事業の執行かどうか判断され、従業員が会社の車で事故を起こしたこと自体をもって、会社の責任を認める傾向にあります。
会社が責任を逃れるためには、従業員の無断私用運転だったこと、その従業員の日常業務が車の運転と無関係であること、無断使用を禁止し無断使用させないための対策を講じていることなど、自動車の管理を尽くしていたことを立証する必要があります。
従業員が会社の車を無断使用して起こした事故について、会社の責任を認めた判例には、次のようなものがあります。
従業員の無断私用運転で運行供用者責任を認めた事例
農業協同組合の運転手が、組合所有の自動車を無断運転して帰宅する途中に起こした事故について、組合の運行供用者責任を認めた事案です。
組合は、就業時間外に無断で自動車を使用することを形式的には禁じていましたが、自動車と鍵の管理は従来から必らずしも厳格ではなく、就業時間外に無断運転した例も稀でありませんでした。
事故発生当時の自動車の運行は、運転手の無断運転によるものにせよ、自動車の所有者と運転手の間に雇用関係など密接な関係があり、日常の自動車の運転・管理状況からして、客観的外形的には組合のためにする運行と認めるのが相当であるとしました。
最高裁判決(昭和39年2月11日)
従業員の無断私用運転で使用者責任を認めた事例
従業員が、勤務終了後に、私用で会社の第一種原動機付自転車を勝手に運転して起こした事故について、会社の使用者責任を認めた事案です。
従業員は、自動車助手として雇われ、平素貨物自動車に乗って荷物の積み卸しに従事していたほか、社長から業務上急用の際には事故車を運転使用してもよいとの許諾を得ていて、その鍵を自由に持ち出せる状況にあり、3日に1度位の割合で、随時鍵を自由に取り出して事故車を業務のために運転していました。
事故当時も、自由に鍵を持ち出せる状況のもとにこれを用い、会社の自転車置場に置いてあった事故車を運転して、事故を起こしました。
こうした事実を認定した上で、最高裁は、事故当時の従業員の事故車の運転は外形上その職務の範囲内の行為と認められ、したがって、本件事故による損害は事業の執行につき生じたものであるとして、運送会社は、本件事故につき使用者責任を負うべきである、と判示しました。
最高裁判決(昭和46年12月21日)
従業員のマイカー使用中の事故についての会社の責任
従業員のマイカーは会社の所有ではないので、従業員がマイカーで事故を起こしても会社は責任を負いませんが、業務や通勤にマイカーの使用を認めていた場合は、会社の責任を追及できる場合があります。
業務や通勤にマイカーの使用を禁止していた場合
業務や通勤にマイカーを使用することを禁止し、現に使用を許していなかった場合は、業務に従業員がマイカーを使用して事故を起こしたとき、会社は責任を負いません。
従業員がマイカーで出張中に起こした交通事故について、会社の使用者責任が否定された事例として、次のようなものがあります。
会社の使用者責任を否定した事例
従業員が工事現場へマイカーを利用して往復し、その帰りに事故を起こした事案です。
会社では、従業員がマイカーを利用して通勤したり、工事現場に往復したりすることを禁止し、県外出張の場合にはできる限り汽車かバスを利用し、マイカーを利用するときは直属課長の許可を得るよう指示していました。
この従業員もこのことを熟知しており、これまで業務にマイカーを利用したことはありませんでした。
本件出張についても、列車の利用が可能だったのに、会社に届け出ずマイカーを利用して出張し、その帰りに事故を起こしたのです。
最高裁は、本件出張につきマイカーの利用を許容していたことを認めるべき事情がなく、従業員の運転行為は、会社の業務の執行にあたらないと判示しました。
最高裁判決(昭和52年9月22日)
業務や通勤にマイカーの使用を認めていた場合
マイカーを業務に使用させていた場合の業務中の事故や、マイカー通勤を認めていた場合の通勤途中の事故については、会社に運行支配と運行利益が認められ、運行供用者責任を負うことがあります。
会社の運行供用者責任を認めた事例
会社が、通勤や工事現場への往復にマイカーの使用を認め、ガソリン手当等を支給していた場合に、帰宅途中に起こした事故について、会社に運行支配と運行利益があるとして、会社の運行供用者責任を認めた事例があります。
最高裁判決(昭和52年12月22日)
会社が従業員のマイカー使用を禁止していたとしても、その運用がルーズな場合は、マイカーの使用を黙認していたとして、会社の責任を追及することができます。
逆に、従業員のマイカーが会社の業務に使用されていたとしても、私用目的での運転中に起こした事故については、会社の責任を問えないこともあります。
いずれにしても、個別に具体的に判断する必要があります。
まとめ
従業員が起こした自動車事故については、運行供用者責任(自賠法3条)と使用者責任(民法715条)が問題となります。
従業員が会社の車を業務外に私用目的で無断運転し、交通事故を起こした場合でも、会社の責任を問い、損害賠償請求することができます。
会社の責任が否定されるのは、会社が車の管理をきちんと行っていたにもかかわらず、鍵をこじ開けるなどして泥棒運転に近い状況にあったようなケースぐらいです。
従業員がマイカーを使用中の事故でも、会社の責任を問える場合があります。
被害者保護の観点から会社の責任が広く認められる傾向がありますが、判断が難しい場合は、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
関連
【参考文献】
・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 81~82ページ
・『交通事故の法律知識 第4版』自由国民社 16ページ、23~24ページ
・『交通事故と示談のしかた 第3版』自由国民社 98~100ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 39~42ページ
・『交通事故損害賠償保障法 第2版』弘文堂 56~59ページ