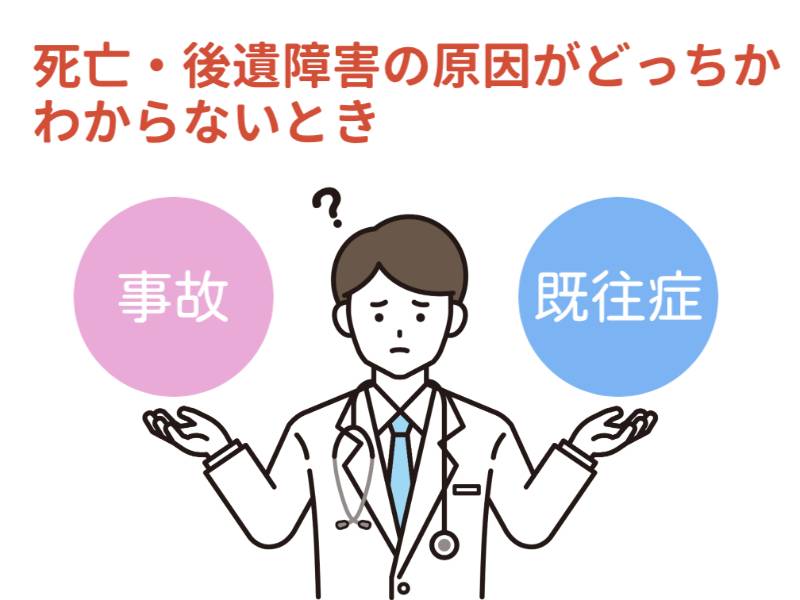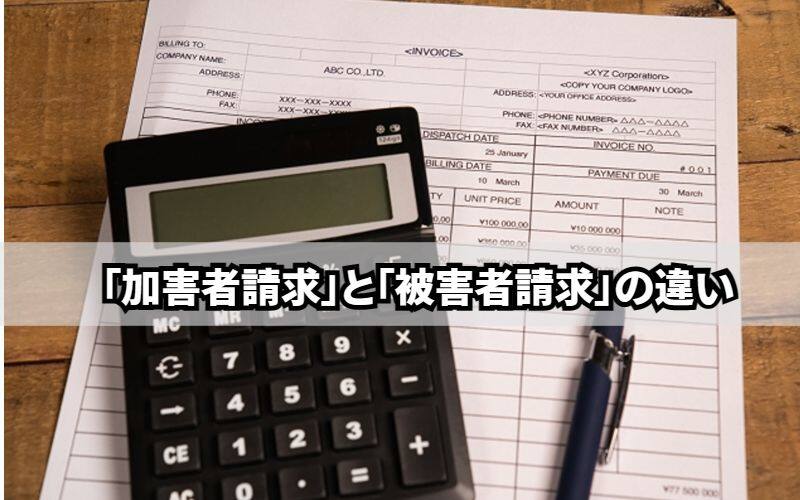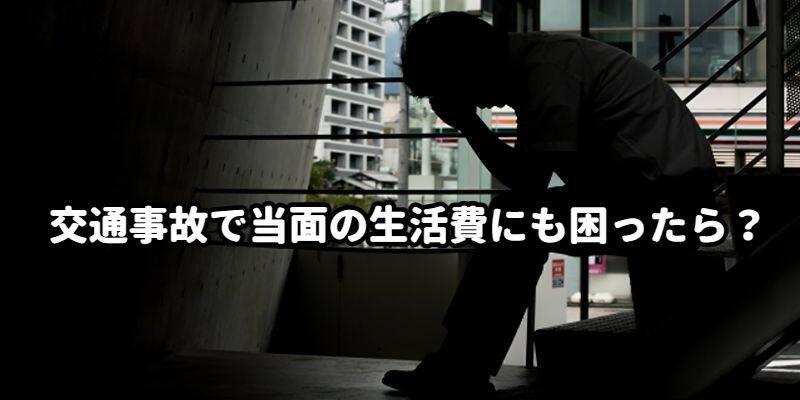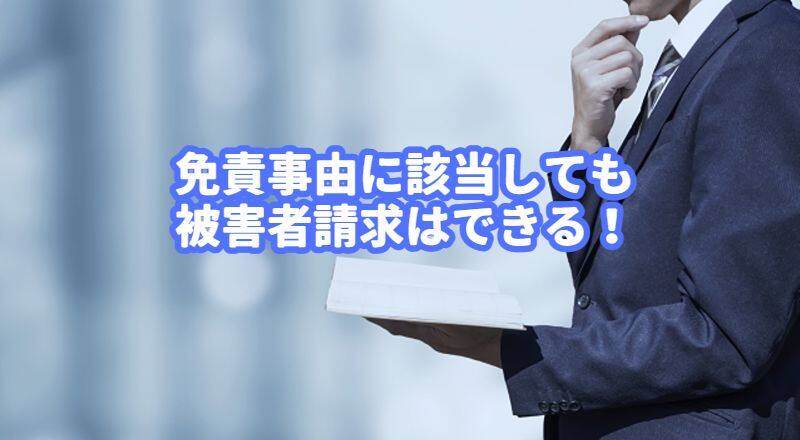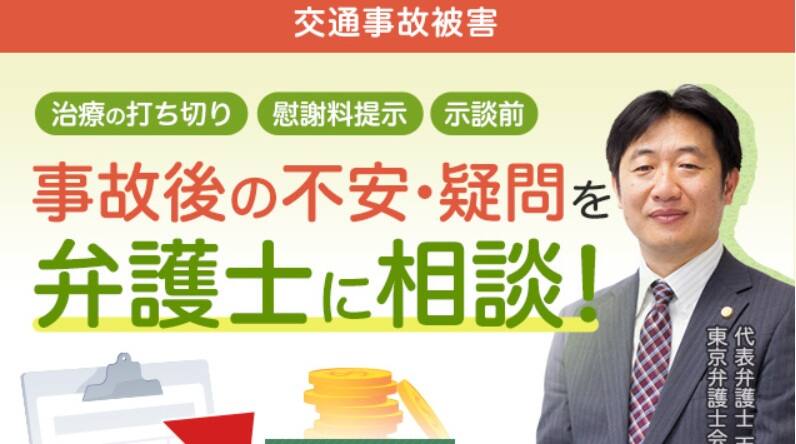※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

自賠責保険金がどんな場合に支払われるかは、法律(自動車損害賠償保障法=自賠法)で定めています。どんな場合に支払われ、どんな場合に支払われないのか、詳しく見ていきましょう。
自賠責保険金が支払われる事故とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、被保険者が被害者に対して自賠法3条に定める損害賠償責任を負担することによって被る損害について、一定額を限度として填補する保険です(『民事交通事故訴訟の実務Ⅱ』ぎょうせい20ページ)。
「自賠責保険金が支払われるのはどんなときか?」というのは、「自賠責保険の保険事故(保険会社が保険金を支払う原因となるもの)は何か?」ということです。
自賠責保険における保険事故とは?
自賠法(自動車損害賠償保障法)は、責任保険(自賠責保険)と責任共済(自賠責共済)の契約について、次のように規定しています。
- 責任保険の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を保険会社がてん補することを約し、保険契約者が保険会社に保険料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
- 責任共済の契約は、第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
第1項が自賠責保険、第2項が自賠責共済についての規定です。自賠責共済では、「保険」が「共済」に、「保険会社」が「組合」に変わるだけで、あとの文言は同じです。
「第3条の規定」とは、運行供用者責任についての規定です。「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」(自賠法3条)と定めています。
つまり、自賠法3条の規定による保有者の損害賠償責任の発生、すなわち保有者が運行供用者責任を負ったという事実が、自賠責保険における保険事故です。
逆にいえば、保有者に運行供用者責任が発生しない場合には、自賠責保険における保険事故にあたらないので、自賠責保険金は支払われません。
では、保有者と運行供用者責任について、詳しく見ていきましょう。
保有者とは?
保有者とは、「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するもの」と定義されています(自賠法2条3項)。
①自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者であり、②自己のために自動車を運行の用に供するもの(=運行供用者)が、その自動車の保有者です。図で表すと次のようになります。

「自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者」という集合と「運行供用者」という集合の重なる部分が、「保有者」です。
保有者がどういう人かは、保有者の集合から外れる人(すなわち保有者に当たらない人)を考えると、イメージしやすいでしょう。
自動車の所有者であるけれども保有者でない人とは、所有権留保売買における所有者や、自動車を盗まれた所有者です。これらの人は、自動車の所有者ではありますが、自動車を運行の用に供するにあたっての責任はない(運行供用者ではない)ので、保有者には当たりません。
運行供用者であるけれども保有者でない人とは、自動車を盗んで運転していた泥棒運転者です。泥棒運転者は、自己のために自動車を運行の用に供しているため運行供用者ではありますが、所有権も正当な使用権もなく運転しているので、保有者には当たりません。
盗難車両による事故で、保有者の運行供用者責任を問えない場合は、自賠責保険から保険金(損害賠償額)の支払いを受けることはできません。こういう事故の被害者は、政府保障事業の保護対象となります。
運行供用者責任とは
運行供用者責任については、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と定めています(自賠法3条)。
「自己のために自動車を運行の用に供する者」を運行供用者といいます。運行供用者は、自動車の運行によって、他人の生命・身体を害したとき、損害賠償責任を負います。これが運行供用者責任です。
運行供用者責任が発生するためには、①自動車の運行による事故であり、②他人の生命・財産を害したことが要件となります。
要件①:自動車の運行による事故であること
まず、「自動車」の「運行」「による」事故であることです。自動車の運行によらない事故は、自賠責保険の対象外です。
ちなみに、任意自動車保険は、自動車の運行による場合だけでなく、「被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害すること」を対人事故と定義し、広くカバーしています。
さらに詳しくは、次のページをご覧ください。
要件②:他人の生命・身体を害したこと
次に、「他人」の「生命・身体を害した」ということです。物損は自賠責保険の対象外であり、また、マイカーを運転中に事故を起こして自分が怪我をしても自賠責保険の対象外です。自賠責保険金が支払われるのは、「他人」を死傷させた場合です。
では「他人」とは、どういう人が該当するのか?
自賠法にいう「他人」とは、運行供用者及び運転者以外の人です(最高裁第二小法廷判決・昭和42年9月29日)。したがって、マイカーを運転中、同乗していた家族が負傷した場合、家族であっても「他人」に当たり、自賠責保険金が支払われるケースがあります。有名な「妻は他人」判決というものがあります(最高裁第三小法廷判決・昭和47年5月30日)。
交通事故被害者を保護するため、歴史的に運行供用者の概念が広げられ、逆に「他人」の範囲が狭まってきました。そのため、運行供用者が複数いる事故が増えてきました。
そんな中で、運行供用者(及び運転者)以外の人を「他人」というのが原則ではあるものの、運行供用者が複数いて、中心的に運行している人と、そうでもないような人がいるとき、そうでもない人が怪我をしたのであれば、その人は被害者(自賠法上の「他人」)として認めてあげてもいいのではないかとする議論があり、そういう判決も出ています(最高裁第二小法廷判決・平成9年10月31日)。
自賠責保険の被保険者は保有者と運転者
自賠責保険の保険事故は、保有者に、自賠法3条規定の損害賠償責任(=運行供用者責任)が発生することですが、自賠法は、この保有者に加え運転者も被保険者と定めています(自賠法11条)。
自賠法における「運転者」とは、一般的な意味での運転者ではなく、「他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者」をいいます。(自賠法2条4項)。例えば、運送会社の業務で運転している人、バスの運転手や車掌、クレーン車の玉掛け作業をしている人などです。
自賠法が、なぜ運転者を自賠責保険の被保険者にしているかというと、被保険者にしておかないと、保有者に運行供用者責任が生じ、運転者も直接の加害者として賠償責任を負うときに、運転者が保有者から求償(民法715条3項)されたり、保険会社から代位求償(保険法25条)されたりすることがあるからです。
そういう理由から、運転者を被保険者の仲間にいれているのであって、運転者が本来的に賠償責任を負う人だというわけではありません。
自賠法が規定する運行供用者・保有者・運転者・被保険者の違いについてさらに詳しくはこちらをご覧ください。
自賠責保険金が支払われない事故とは?
自賠責保険が支払われるためには「保有者が運行供用者責任を負うこと」が必要ですから、これに該当しない事故の場合、すなわち、①運行供用者責任が発生しない場合、②運行供用者責任は発生するが、保有者に生じるのではない場合には、自賠責保険による保険金(損害賠償額)の支払いはありません。
このほか、③免責になる場合や、④そもそも自賠責保険契約が存在しない場合にも、当然支払われません。
- 運行供用者責任が発生しない場合
- 運行供用者責任は発生するが、保有者に生じるのではない場合
- 保有者に運行供用者責任が発生するが免責となる場合
- 自賠責保険契約が存在しない場合
それぞれ見ていきましょう。
運行供用者責任が発生しない場合
運行供用者責任は、運行供用者が、自動車の運行によって、他人の生命・身体を害したときに発生します。したがって、次のような場合には運行供用者責任は発生しません。
- 「運行によって」にあたらない(運行起因性がない)場合
- 被害者が「他人」にあたらない場合
- 自損事故(単独事故)の場合
- 物損事故の場合
- 自賠法3条但書免責が成立する場合
自動車からの落下物による事故や荷物の積み降ろしによる事故などの場合には、運行起因性が認められないケースがあり得ます。
「他人」とは自賠法上の「他人」です。すなわち、運行供用者(及び運転者)以外の者です。
自損事故・単独事故とは、当該車両の保有者・運転者が怪我をした場合です。もっとも、同乗者がいて怪我をした場合、同乗者に対しては運行供用者責任が発生し得ます。
他人の「生命・身体を害したとき」が対象ですから、物損については対象外です。
自賠法3条ただし書免責とは、次のようなものです。
自賠法3条は運行供用者責任について、「ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない」と定めています。
つまり、①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと、この3つをすべて立証できたときは、運行供用者責任を負わない、ということです。これが「3条ただし書き免責」です。
運行供用者責任は発生するが、保有者に責任が生じるのではない場合
泥棒運転がそうです。泥棒運転者は、運行供用者責任を負いますが、車を盗まれた所有者(保有者)には責任がないので、自賠責保険上の保険事故は発生していないのです。
ただし、自動車の保管状況等から、所有者(保有者)の運行供用者責任が認められることがあり、この場合は、自賠責保険から保険金(損害賠償額)が支払われます。詳しくはこちらをご覧ください。
保有者に運行供用者責任が発生するが免責となる場合
「保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害」については免責となり、自賠責保険金は支払われません(自賠法14条)。
ただし、免責となるのは、被保険者(加害者)が保険金を請求する場合であって、被害者が損害賠償額の支払いを請求する場合には、相手方自賠責保険会社は免責を主張できません。つまり、被害者が直接請求する場合には、自賠責保険から支払ってもらえます。
関連
自賠責保険契約が存在しない場合
そもそも自賠責保険契約が存在しない場合には、当然支払われません。自賠責保険は強制保険ですから、自賠責保険契約が存在しないというのはあってはならないことですが、車検が切れ自賠責保険契約が切れていた、ということがあり得ます。
こういう場合、自賠責保険金は支払われませんが、被害者は政府保障事業に請求することで、自賠責保険による損害賠償額とほぼ同等の損害の填補を受けることができます。
自賠責保険が出ないとき任意保険に請求できるか?
同じ自動車保険でも、自賠責保険と任意対人賠償責任保険とでは、保険事故が異なります。
例えば、自賠責保険は、自動車の「運行によって」起きた事故が対象ですが、対人賠償責任保険は、自動車の「所有、使用または管理」上の問題があって起きた事故なら支払われます。しかも、対人賠償責任保険は自賠責保険の上積み保険ですから、自賠責保険が出ない場合でも、任意保険から損害の全額が補償されるということもあり得るのです。
「運行によって」と「所有、使用または管理」の違いはこちらをご覧ください。
ただし、任意保険は、自賠責保険よりもカバーする範囲は広いのですが、免責事由は自賠責保険よりも多いので注意が必要です。対人賠償責任保険の免責事由はこちらをご覧ください。
なお、自賠責保険にしろ任意保険にしろ、被保険者が損害賠償したことによって発生する損害を填補する保険ですから、そもそも損害賠償責任が生じていない場合には、保険金は支払われません。
まとめ
自賠責保険から保険金(損害賠償額)が支払われるのは、自動車の保有者に運行供用者責任が発生した場合です。
自賠責保険が出ない場合でも、政府保障事業に請求したり、任意自動車保険に請求したりすることができる場合があります。お困りのときには、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『民事交通事故訴訟の実務Ⅱ』ぎょうせい 20~24ページ
・『新Q&A自動車保険相談』ぎょうせい 6~8ページ、35~37ページ
・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社 47~51ページ