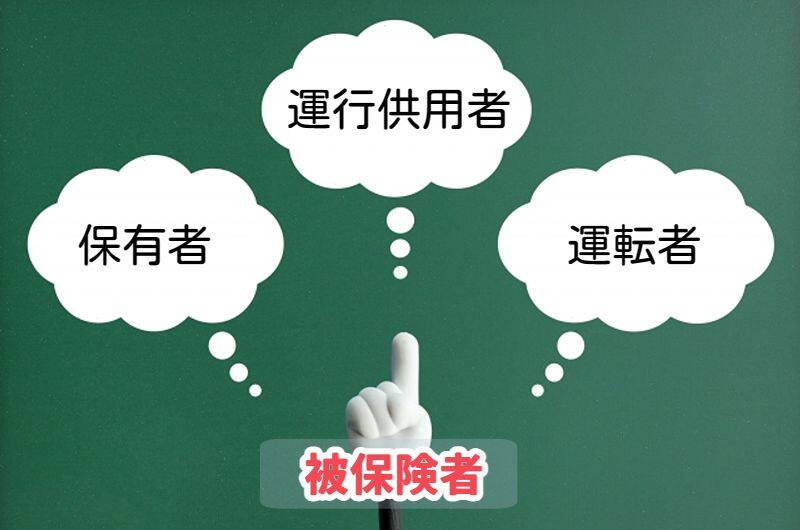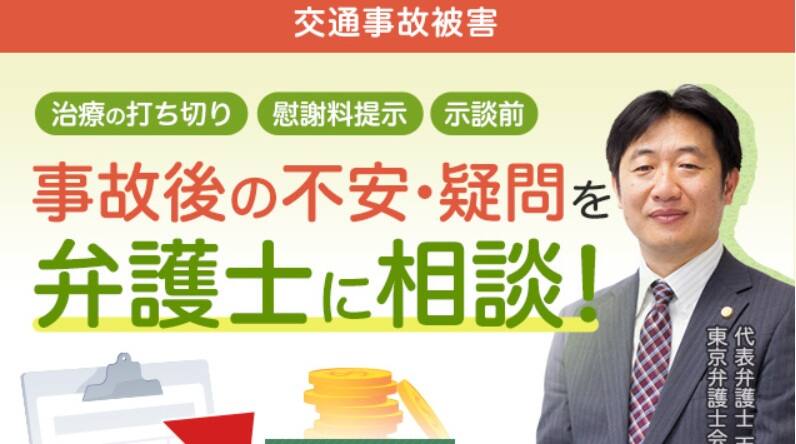※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

自動車の運行による人身事故で怪我をした被害者は、加害車両の運行供用者に対して、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条に基づき、損害賠償を請求できます。
このとき問題になるのは、運行供用者はだれか、ということです。
運行供用者とは?
どんな人が運行供用者にあたるのか?
運行供用者に該当するかの判断基準は?
裁判例の動向もふまえて、詳しく見ていきましょう。
運行供用者とは?
自賠法は、自動車で人身事故を起こしたときの損害賠償責任について、次のように定めています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。
この条文中の「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、いわゆる「運行供用者」です。
ただし、自賠法には、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)の定義規定がなく、運行供用者がどのような者であるか、一義的には明らかでありません。そのため、損害賠償請求する相手方である運行供用者について、判例に基づいて判断することになります。
では、運行供用者とは、どんな人が該当するのか?
運行供用者の判断基準
自賠法の立案担当者の考え方や最高裁判例をもとに、運行供用者の判断基準について、見ていきましょう。
自賠法立案担当者の考え方
運行供用者について、自賠法の立案担当者は、こう説明しています。
「自己のために」というのは、自動車の運行についての支配権とそれによる利益が自己に帰属するということを意味する。従って、この者は、通常自動車の保有者であり、例えば、会社の業務のために自動車を運行している場合には、運行供用者は、運転していた者ではなく、会社になる。
(国土交通省物流・自動車局 保障制度参事官室監修『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 35ページ)
通常自動車の所有者または使用者等のように、自動車の使用について支配権を有し、かつ、その使用によって利益を受ける者を指している。
(運輸省自動車局編『自動車損害賠償保障法の解説』大蔵省印刷局1955年 29ページ)
最高裁判例による判断基準
最高裁は、次のような判断基準を示しています。
自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する。
この判決は、最高裁が「自己のために自動車を運行の用に供する者」について、「自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者」と明示して判断の枠組みを提示した点で、実務上重要な意義があります。
運行供用者が損害の賠償責任を負う根拠は、「危険責任」と「報償責任」にあると理解されています。運行支配は「危険責任」から、運行利益は「報償責任」から導かれる要素であり、このことから、運行支配と運行利益を有する者が、運行供用者とされているのです。
| 危険責任 | 危険物の管理者は、危険物から発生した損害に責任を負うべきという考え方です。自動車の運行という危険性を有するものを支配している者が、損害賠償責任を負うということです。 |
|---|---|
| 報償責任 | 利益を上げる過程で従業員等が他人に与えた損害は、利益を得る者が負担すべきという考え方です。自動車を運行することによって利益を受ける者が、損害賠償責任を負うということです。 |
このように、運行支配と運行利益の2つの要素から運行供用者性を判断する考え方は「二元説」と呼ばれ、その後の裁判例でも踏襲されており、自賠法の立案担当者の考えていたところにも沿うもので、現在の判例・通説となっています。
ただし、運行支配と運行利益の2つの要素を運行供用者性の判断基準とするとしても、具体的にどのように判断すべきか、運行支配と運行利益の内容が問題となります。さらに最高裁判例を見ていきましょう。
運行供用者は被害者保護の観点から広く認められるように
運行支配と運行利益は、現実的な支配や利益である必要はなく、その内容は抽象化され、広く認められるようになってきています。
運行支配の判断
運行支配の内容については、当初は「直接的・現実的支配」を要するとしていましたが、被害者保護の観点から、次第に拡大して解されるように変化しています。
上記の最高裁判決(昭和43年9月24日)は、子が所有する自動車を父親が借り受け、父親が自己の営業に常時使用していて事故を起こした事案について、運行支配と運行利益を判断基準として明示し、子は「自動車の運行自体について直接の支配力を及ぼしえない関係にあった」として、加害車両の所有者である子の運行供用者性を否定しました。
しかし、このように支配の直接性を要求すると、被害者を救済できないことになり、被害者保護のために損害賠償責任を「加害運転者」でなく「加害車両の運行供用者」に負わせることとした意味が失われてしまいます。
その後の判例では、自動車の運行を直接的・現実的に支配していなくても、間接支配・支配の可能性で足り、客観的・外形的支配、事実上の支配、自動車の運行について指示・制御をなしうべき地位にあればよい、というふうに運行支配の内容が修正されていきます。
さらに、自動車の運行を事実上支配・管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視し、監督すべき立場にある場合や、第三者による運転を容認していた場合にも、客観的外形的に運行支配に当たると解して、運行供用者に該当すると判断しています。
おもな最高裁判例を挙げておきましょう。
貸金の担保として自動車を預かった者(A)の従業員(B)が無断でその車を運転し、事故を起こした事案です。
(A)は「事実上本件自動車の運行を支配管理し得る地位にあった」といえ、従業員(B)が無断で私用運転して事故を起こした場合でも、「客観的には(A)による運行支配可能な範囲に属し、(A)は右運行により起こった事故につき保有者としての賠償責任を免れない」としました。
自動車修理業者が修理のため預かっていた自動車を、その従業員が私用のため無断で運転して事故を起こした事案です。
「自動車修理業者が修理のため自動車を預かつた場合には、少なくとも修理や試運転に必要な範囲での運転行為を委ねられ、営業上自己の支配下に置いているものと解すべきであり」、その被用者による運行は「客観的には使用者たる修理業者の支配関係に基づき、その者のためにされたものと認めるのが相当であるから」、修理業者は「本件事故につき、自動車損害賠償保障法3条にいう自己のために自動車を運行の用に供する者としての損害賠償責任を免れない」としました。
父と子(兄・妹)が同居し、家族で雑貨店とガソリンスタンドを営業。妹が、近所の怪我人を病院へ運ぶため、兄所有・家業にも使用している自動車を独断で運転し、事故を起こした事案です。
自動車の所有者である兄はもとより、一家の責任者として家業を総括していた父も、「自動車の運行について指示・制御をなしうべき地位にあり、かつ、その運行による利益を享受していたものということができる」として、父および兄の両名が運行供用者に当たるとしました。
レンタカーを借りた者が事故を起こした事案です。
レンタカー業者が、利用申込者につき、運転免許その他一定の利用資格の有無を審査し、契約において、使用時間や方法の定め、料金額の定め、走行区域や制限走行距離の遵守などの義務づけがあるときは、レンタカー業者は「本件自動車に対する運行支配および運行利益を有していたということができ、自賠法3条所定の運行供用者としての責任を免れない」としました。
「自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となつた者が、登録名義人となつた経緯、所有者との身分関係、自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし、自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にある場合には、右登録名義人は、自動車損害賠償補償法3条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると解すべきである」と、判断の枠組みを示しました。
そのうえで、父と同居して家業である農業に従事する20歳の子が所有し、父の居宅の庭に保管されている自動車につき、子が父の了解を得ることなく父を所有者登録名義人とし、その後了承を得ていたところ、子が事故を起こしたという事案につき、父は「本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったのであって、右自動車の運行供用者に当たると解するのを相当とする」としました。
Aが、父親B所有の自動車に友人Cを乗せて深夜バーに赴き、Cと共に飲酒。Aが泥酔して寝込んでしまったので、Cがバーのカウンター上に置かれていたキーを使用してAを同自動車に乗せて運転し、事故を起こした事案です。
Aによる「運行はBの容認するところであったと解することができ」、飲酒したAが「友人等に本件自動車の運転を委ねることも、その容認の範囲内であったと見られてもやむを得ないというべきである」として、所有者Bは「客観的外形的に見て、本件運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である」としました。
Aは、生活保護を受けていたため、自動車を購入する際、自己の名義で所有すると生活保護を受けられなくなるおそれがあると考え、弟Bに名義貸与を依頼。Bの承諾のもと、Aは自動車を購入し、所有者および使用者の名義をBとしました。その自動車をBが運転中に、事故を起こした事案です。
AとBは、住居・生計を別にし、疎遠で、Bは、本件自動車を使用したことはなく、その保管場所も知らず、本件自動車の売買代金、維持費等を負担したこともありませんでした。
このような事実関係のもと、BのAに対する「名義貸与は、事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし,自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また、BがAの依頼を拒むことができなかったなどの事情もうかがわれない。そうすると、…… BとAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、Bは、Aによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあったというべきである。したがって、Bは、本件自動車の運行について、運行供用者に当たると解するのが相当である」としました。
運行利益の判断
運行利益の内容についても、現実的・具体的に運行による利益を享受するかどうかでなく、客観化・抽象化されています。
また、運行供用者に該当するかについては、運行支配と運行利益の2つの要素を判断基準としつつも、実際には、運行支配を中心に運行供用者性を判断しているといえます。
重要な判例として、昭和46年7月1日の最高裁判決がよく挙げられます。無断私用運転中の事故でも、所有者に運行利益があるとした事例です。運行利益について、運行を全体として客観的に観察して、所有者のためにされていれば足りるとし、二元説でも、運行支配が重要であることを明らかにしたのです。
小規模の信用協同組合の常務理事Aが、長期出張に際し、同組合営業部長Bに、A所有の自動車を修理に出すよう委託し、修理工場への往復にはBの指示により組合従業員が運転にあたることを予想しつつ、不在中の自動車の管理をBに一任。Bから指示を受けた組合従業員Cが、組合の見習で自動車運転の業務にも従事していたDと相談のうえ、自動車を無断使用したのち組合事務所に届けておくこととし、Dが、修理の終わった自動車を修理工場から受け取り、Cを同乗させ運転して私用に赴いたのち、翌朝組合事務所への帰途に事故を起こしたという事案です。
「運行を全体として客観的に観察するとき、本件自動車の運行がAのためになされていたものと認めることができる」とし、無断私用運転中の事故でも、所有者Aに運行利益があるとされました。
「原判決が運行利益の帰属の有無について判断をしていないことを違法」とする主張に対し、最高裁は、「原判決も、このような趣旨において、前示事実関係を判示することにより、とくにAへの運行利益の帰属につき説示することがないとしても、おのずから、これを肯定したものと解することができる」としました。
運行支配と運行利益の関係については、次のような指摘があります。
自動車事故による損害に対する責任として重視されるべきは、自動車という危険物の利用に係る危険責任であり、自動車の運行を支配し、または支配し得べき立場にある者は、通常、その自動車の運行により何らかの利益を得ているはずであるから、運行支配に重点を置き、運行利益は補完的なもとの捉えることができる。
(佐久間邦夫=八木一洋編『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院45ページ、森冨義明=村主隆行編著『交通関係訴訟の実務』商事法務88ページ)
運行供用者に当たるか否かが問題となる主なケース
運行供用者に該当するかが問題となる主なケースについて、判例がどのような判断を示しているか、まとめておきます。
レンタカー業者
レンタカー業者は、一般的に運行供用者に当たります(最高裁昭和46年11月9日判決、最高裁昭和50年5月29日判決)。この場合、レンタカー利用者も運行供用者に当たるので、運行供用者は複数いることになります。
ただし、利用者が返却期限を大幅に超えて自動車を返却せず、レンタカー業者の支配管理可能性が失われたと認められる場合には、レンタカー業者の運行供用者性が否定されることもあります。
リース会社
リース会社は、基本的に運行供用者に当たりません。自動車の所有権はリース会社にありますが、単に割賦金の支払いを担保するためであり、ユーザーが自動車の管理支配権を全面的に有していると考えられるからです。
ただし、契約にリース会社が自動車の運行を管理し得るような条項が含まれていたり、リース会社とユーザーとが一体のものと評価し得るような事情が存在するような場合は、リース会社も運行供用者に当たり得ます。
自動車修理業者
自動車が修理のために自動車修理業者に預けられている間は、修理業者がその運行を支配すると解され、修理を終えた自動車が修理業者から注文者に返還されたときには、特段の事情のないかぎり、その引渡の時以後の運行は注文者の支配下にあるものと解されます。
したがって、自動車修理業者が修理のため預かった自動車を、その従業員が運転して事故を起こした場合には、それが従業員による無断私用運転であったとしても、修理業者が運行供用者責任を負います(最高裁昭和44年9月12日判決)。
割賦販売における留保所有権者
所有権留保特約付割賦販売契約によって売買された自動車が事故を起こした場合、所有権留保権者である自動車販売会社や信販会社の運行供用者性は、原則として否定されます(最高裁昭和46年1月26日判決)。
所有権を留保した割賦販売業者(留保所有権者)は、代金債権の確保のために所有権を留保しているに過ぎず、自動車を引き渡して以降は、自動車に対する運行支配をしていないし、運行により利益を得ているわけでもないからです。
使用貸借における貸主
車の所有者から無償で車を借り受けたものが事故を起こした場合、原則として貸主(所有者)は運行供用者となります。
貸与期間が比較的短期間で、その間に事故を起こした場合には、貸主(所有者)の運行供用者性が肯定されています(最高裁昭和46年1月26日判決)。他方、予定された貸与期間を著しく経過し、所有者が返還を求めて具体的な行動を起こしていたような場合には、貸主の運行支配は失われ、運行供用者ではなくなると考えられます(最高裁平成9年11月27日判決)。
自動車を無償で貸与し、借主が事故を起こした場合の貸主の運行供用者責任については、貸主と借主との関係、貸与の目的、貸与期間の長短、返還期限の到来の有無、到来後の経過期間等の諸事情を総合考慮し、貸主の運行支配がどの程度及んでいるか、という観点から判断されます。
借主のさらに友人が運転して事故を起こした場合にも、その運行が貸主(所有者)の容認の範囲内にあったと認められる場合には、貸主(所有者)の運行供用者性が肯定されています(最高裁平成20年9月12日判決)。
なお、借主は運行供用者となるので、貸主も運行供用者となる場合には、運行供用者は複数いることになります。
さらに詳しくは、次をご覧ください。
無断運転された所有者
無断運転者が、自動車の所有者と雇用関係や親族関係にある場合、客観的・外形的に所有者の権限に基づく支配内での運行といえ、所有者のための運転といえることから、特段の事情がない限り、運行供用者責任を免れないとする傾向にあります。無断私用運転というだけでは、特段の事情に当たらないとされています(最高裁昭和44年9月12日判決)。
また、所有者に客観的容認があったと評価されてもやむを得ないような事情があれば、運行供用者性が肯定されます(最高裁平成20年9月12日判決)。
容認の内容については、所有者が自動車を他人に使用させる意思を有していた場合(=主観的容認)だけではなく、客観的・外形的に容認していたと評価されてもやむを得ない事情がある場合(=客観的容認)も含まれると解されており、容認は、客観化・抽象化されています。
なお、無断運転者も、運行供用者となります。
さらに詳しくは、次をご覧ください。
泥棒運転された所有者
第三者による泥棒運転の場合、盗難被害にあった車両の所有者は、盗難被害車の運行を指示制御すべき立場になく、運行利益も帰属していないため、原則として、運行供用者責任を負わないとされていました(最高裁昭和48年12月20日判決)。
現在は、盗難場所(第三者が容易に立ち入れる場所であるかなど)、車両管理状態(ドアロックやエンジンキーの状況など)、事故の状況(盗難から事故発生までの時間的・場所的関係など)、盗難発覚後の被害者の行動(警察への被害届の提出など)により判断し、所有者の運行供用者性が肯定されることがあります(最高裁昭和57年4月2日判決)。
駐車場所、車両の管理状況、泥棒運転の経緯・態様などを総合的に考慮し、客観的に見て、所有者において第三者が車両を運転するのを「容認」したのと同視し得るような状況がある場合には、所有者の運行供用者性が肯定されます。
なお、車を盗んで運転した泥棒運転者は、運行供用者に当たります。
さらに詳しくは、次をご覧ください。
名義貸与者
名義貸与の依頼を承諾して、自動車の名義上の所有者兼使用者となった者(名義貸与者)は、「自動車の運行を事実上支配管理することができ、社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視監督すべき立場」にある場合には、運行供用者責任が肯定されます(最高裁昭和50年11月28日判決、最高裁平成30年12月17日判決)。
従来、購入資金等の関係で名義を貸しているだけの者は、運行供用者責任を負わないとする裁判例がありましたが、現在は、名義貸与者が運行供用者責任を免れるのは難しくなっています。
なお、すでに自動車を売却して引き渡しも終えている、単なる名義残り(名義書換未了)の場合は、名義人の運行支配・運行利益は認められず、運行供用者責任は否定されます。
運転代行業者
運転代行業者は、自動車の使用権を有する者の依頼を受けて、その者を同乗させ、自動車を同人の自宅まで運転する業務を有償で引き受け、代行運転者を派遣して業務を行わせるものですから、運行供用者として認められます(最高裁平成9年10月31日判決)。
従業員がマイカーで事故を起こしたときの雇用主
従業員のマイカーの使用は、基本的には雇用主が関与しないところですから、従業員がマイカーで仕事中や通勤途中に事故を起こした場合、雇用主の運行供用者責任は、原則として否定されます。
ただし、その車両が日常的に会社の業務に利用され、雇用主もこれを容認していたような事情がある場合には、雇用主の運行供用者責任が肯定される傾向にあります(最高裁昭和52年12月22日判決、最高裁平成元年6月6日判決)。
まとめ
運行供用者とは、自動車の運行について運行支配と運行利益が帰属する者とされています。自動車の運行を支配し、運行によって利益を享受する者が、運行供用者です。
ポイントとなるのは運行支配・運行利益の内容ですが、現実的な支配や利益である必要はなく、かなり抽象化されています。
運行支配については、直接的・現実的な支配が認められなくても、客観的・外形的に見て、事故車両を事実上支配ないし管理制御できる地位、あるいは規範的に見て間接的な支配ないしその可能性があれば足り、運行利益についても、何らかの社会的な利益があれば足りるとし、被害者の保護を厚くする方向で判断されています。
運行供用者であるか否かが争点となることは、現在では多くはありません。自動車の所有者を相手に賠償請求すれば、運行供用者責任が否定されることは、まずないからです。
運行供用者に該当するか否かが問題となる場合は、裁判例に基づき検討する必要がありますから、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『実務精選100 交通事故判例解説』第一法規 2~25ページ
・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 254~261ページ
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 66~69ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 44~51ページ
・『交通事故判例140』学陽書房 8~13ページ
・『交通事故損害賠償法 第3版』弘文堂 28~69ページ
・『新版 交通事故の法律相談』学陽書房 10~13ページ、39~68ページ
・『判例タイムズ№228』115ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 87~98ページ
・『三訂 逐条解説 自動車損害賠償保障法』ぎょうせい 35~36ページ、83~95ページ
・『逐条解説 自動車損害賠償保障法 第3版』光文堂 20~40ページ
・『交通事故実務入門』司法協会 36~38ページ
・『改訂版 交通事故事件の実務―裁判官の視点―』新日本法規 11~26ページ
・『実例と経験談から学ぶ 資料・証拠の調査と収集―交通事故編―』第一法規 63~65ページ
・『交通事故紛争解決法理の到達点』第一法規 206~252ページ