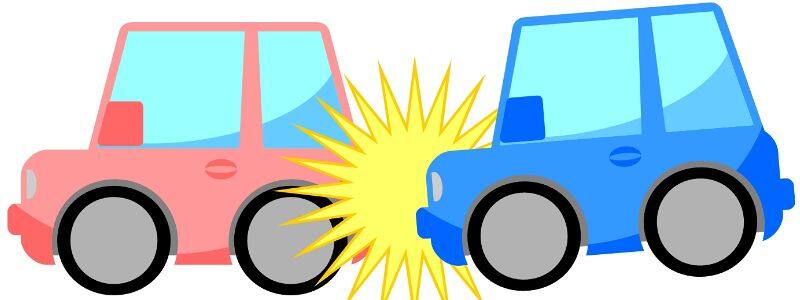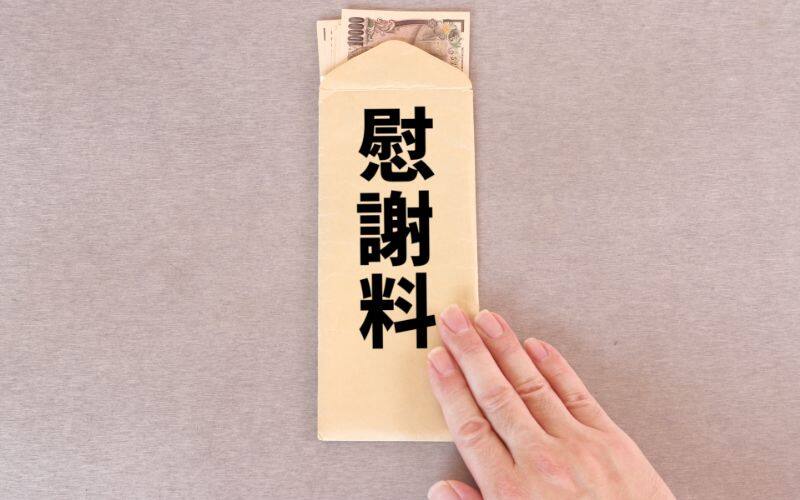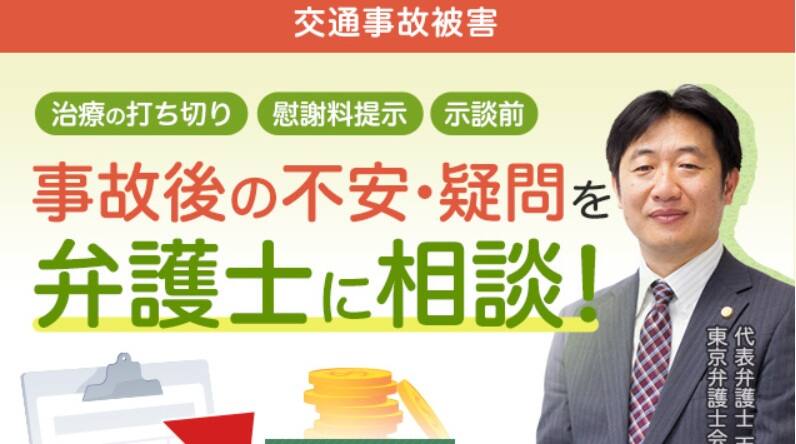※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

物損は自賠法が適用されないほか、損害算定の方法や損害賠償請求権に物損特有の考え方があり、人損の損害賠償請求とは異なる点があります。人身事故の場合は、人損と物損の両方が発生しますから特に注意が必要です。
物損の損害賠償請求権と消滅時効
人身事故では、たいてい人損と物損の両方が発生します。同一の事故であっても、人損と物損は、損害賠償の請求権は別個のもので、消滅時効も異なります。
物損の賠償請求権の方が、先に時効が完成します。気が付いたら、物損について損害賠償請求権が時効で請求できない、ということにならないよう、注意が必要です。
交通事故被害の損害賠償請求権の消滅時効は、物損が3年、人損が5年です。時効起算点も異なります。消滅時効について詳しくはこちらをご覧ください。
さらに、物損の損害賠償請求権は、侵害された財産権ごとに生じます。複数の財産権が侵害された場合は、財産権ごとに損害賠償請求権が別です。ちなみに、人損には財産的損害(治療費や逸失利益など)と精神的損害(慰謝料)がありますが、損害賠償の請求権は、1個とされています。
同一事故により生じた同一の身体傷害を理由とする財産上の損害と精神上の損害とは、原因事実および被侵害利益を共通にするものであるから、その賠償の請求権は一個であり、その両者の賠償を訴訟上あわせて請求する場合にも、訴訟物は1個であると解すべきである。
(最高裁第一小法廷判決 昭和48年4月5日)
| 人的損害 | 物的損害 | |
|---|---|---|
| 消滅時効 | 5年 | 3年 |
| 請求権 | 1個 | 財産権ごと |
物損特有の損害算定の論理
物損は、財産権の侵害による損害ですから、その損害賠償は、財産上の損害を事故前の状態に回復させることです。したがって、修理をするにしろ、買替えをするにしろ、損害賠償額は、事故時における時価額の範囲となります。
車両損害で考えてみましょう。
被害車両が修理可能の場合は、修理をして、かかった修理費を損害賠償請求するのが原則です。修理可能であるのに、買替えを求めても認められません。
修理不能の場合は、全損(物理的全損)と判断され、車両の買替えが認められます。ただし、損害として認められるのは、被害車両の時価相当額です。
なお、修理可能でも、修理費が被害車両の時価額を上回る場合は、経済的全損と判断され、買替が相当となり、損害賠償額は被害車両の時価相当額です。修理費のうち、車両時価額を上回る部分は、相当因果関係のある損害と認められません。
このように、物損の場合は、修理費もしくは時価額のいずれか低い方の額が、損害賠償額となります。原則は修理による原状回復ですが、買替える方が安いなら、その方が経済的に合理的というわけです。
実況見分調書がなく事故状況を立証する客観的資料が乏しい
物損事故の場合には、警察に事故の届出をしたとしても、通常、実況見分調書は作成されず、簡易な物件事故報告書が作成されるだけです。
しかも、事故後、車両を修理し、車両の損傷状況が証拠として保存されていないこともあります。
そのため、後日、過失割合が争いとなったとき、事故態様を客観的に証明する資料を欠く場合が少なくないのです。
ですから、事故後、記憶が鮮明なうちに、事故現場の道路状況や双方の車両の動静などをできる限り正確に記録した図面を作成しておくことが大切です。
双方の車両の損傷状況を写真撮影し、どのように衝突・接触したのかの資料を確保しておく必要があります。
最近は、ドライブレコーダーを搭載している車両も多くなってきています。事故時のドライブレコーダーの動画がある場合は、動画のデータを確保し、保存しておくことが大事です。
物損事故の場合、軽く考え、警察への届出をしないこともあります。しかし、警察へ事故を届出していないと、後日、交通事故証明書の発行を受けられず、事故の発生自体が争いとなりかねません。必ず事故の届出をしておくことが大切です。
損害賠償額が比較的少額にとどまる
物損事故は、人身事故に比べて損害賠償額が比較的少額にとどまります。物損には、人損における逸失利益や慰謝料がなく、損害項目が限られます。
車両の損害であれば、原則は修理ですが、修理費は車両の時価額までしか認められません。修理費が時価額を超える場合は、時価額までしか損害賠償を受けられません。そのため、想定した修理ができないような賠償額にとどまることも多く、お詫び的な金銭の支払いもないので、法的には適正な賠償額であったとしても、被害者の心情的には、納得できないケースも少なくありません。
損害賠償額に納得できないからといって、弁護士に依頼しても、時価額を大幅に超える損害賠償を受けることは期待できません。物損の場合は、人損のように損害算定基準が、保険会社と弁護士とで違うということがないからです。
物損の場合は、そもそも受け取れる損害賠償額が多くはなく、弁護士が介入することで増額できる余地も少ないため、弁護士に依頼しても、弁護士費用の負担を考えると、費用対効果の点でメリットがないのです。
最近は、弁護士保険に加入している方も増えています。弁護士保険を利用すれば、法律相談料を含め、弁護士費用が保険から支払われますから、弁護士保険を利用するのであれば、物損であっても弁護士に相談・依頼するメリットはあります。
まとめ
物損は財産権の侵害に係る損害であるため、修理でも買替でも損害賠償額の上限は時価額です。慰謝料や逸失利益は認められません。そのため、物損の損害賠償額は、一般的に少額にとどまります。
また、人損であれば、保険会社と弁護士とで損害算定基準に大きく差がありますが、物損には、そういった違いもありません。
なので、物損のみの場合、弁護士費用の負担を考えると、弁護士に相談・依頼するメリットは、あまりありません。弁護士に依頼する場合は、費用倒れにならないよう注意が必要です。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 426~429ページ
・『民事交通事故訴訟の実務Ⅱ』ぎょうせい 332~334ページ
・『物損交通事故の実務』学陽書房 2~7ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 3~6ページ