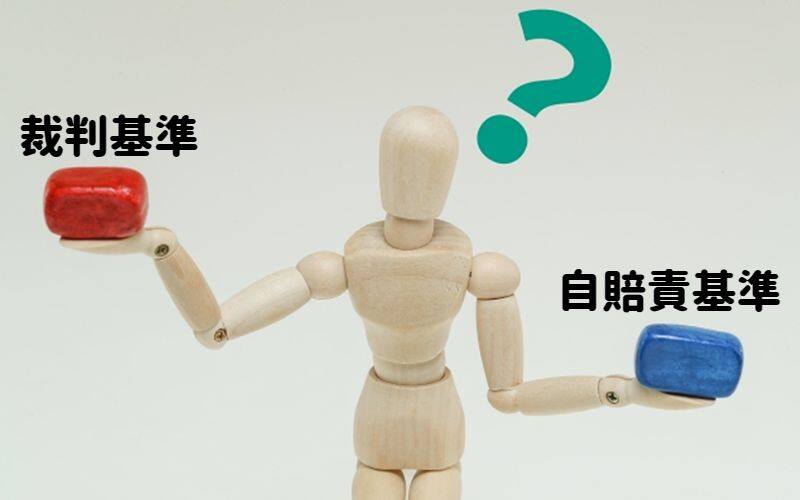※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

後遺症(後遺障害)による逸失利益は、「差額説」にもとづくか「労働能力喪失説」にもとづくかによって、損害の発生が認められるか否か、結果が異なる場合があります。
「差額説」と「労働能力喪失説」の違いが逸失利益の算定にどう影響するのか、裁判例の動向をふまえて解説します。
差額説とは?
差額説は、賠償の対象となる損害を「交通事故がなければ被害者が得られたであろう収入」と「事故後に現実に得られる収入」との差額とみるものです。損害論における伝統的な見解とされています。
差額説にもとづくと、事故による後遺症で労働能力が失われたとしても、現実に減収とならなければ逸失利益は認められないことになります。
※後遺症による逸失利益の算定方法はこちらをご覧ください。
例えば、無職者(主婦、幼児、学生等を含む)が被害者の場合や、被害者本人の努力等によって事故前の収入が維持されている場合には、減収がないため、逸失利益の発生が認められない、ということになります。
しかし、被害者が後遺症による不自由や苦痛に耐え、通常以上の努力を払って減収を食い止めているのに、「減収がないから損害は発生していない」として加害者が賠償を免れるのは、妥当ではないでしょう。ちなみに、幼児・生徒・学生、専業主婦など場合は、賃金センサスの平均賃金を用いて逸失利益を算定します(⇒「三庁共同提言」)。
差額説本来の考え方は、不法行為前の財産額と不法行為後の財産額の差をもって損害と考えるものであり、収入額の差が損害だとするものではありません。差額積算過程の一要素として収入における差額に着目したのが、逸失利益における差額説です。
(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 128ページ)
労働能力喪失説とは?
労働能力喪失説は、人間の労働能力を一種の資本財とみて(収入はこの資本財から生まれます)、労働能力の全部または一部の喪失(=被害者の保有する労働力商品が破損して機能不全の状態となったこと)を財産的損害と捉え、現実に収入が失われたかどうかは、労働能力の低下(=労働力商品の価値低下)の程度を評価するための参考資料にすぎないとする見解です。
労働能力喪失説にもとづけば、現実の減収がなくても、労働能力の喪失があると評価できれば、損害の発生を認めることになります。
理論的には、労働力の市場価格を想定して価格の下落を損害と捉えるのであれば、財産状態の差を損害と考えるのに等しいので、労働能力喪失説は差額説の亜種ともいえます。
(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 129ページ)
差額説と労働能力喪失説の違いが損害算定に影響する場合とは?
「差額説」をとるか「労働能力喪失説」をとるかによって損害算定に違いが生じるのは、後遺症の逸失利益の算定において、後遺障害による労働能力の喪失があるが、収入の減少がない場合です。
差額説からすれば、現実に収入の減少がない以上、「損害の発生はない」ということになります。他方、労働能力喪失説からすれば、労働能力に影響が出る後遺障害がある以上、「損害の発生は認められる」ことになります。
理論上、後遺障害等級が認められ、労働能力の喪失があるにもかかわらず、現実に減収がない場合は、差額説と労働能力喪失説では、結論が違ったものとなるのです。
なお、裁判例においては、差額説をとるか否かはともかく、ほとんど労働能力喪失説による算定方法をとっているため、実質的な差は現れず、差額説と労働能力喪失説の対立は、あまり結論に影響を与えることはないとされています(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 130ページ)。
減収がない場合に逸失利益が認められるかどうかは、主張・立証の仕方にかかっています。減収がない場合の逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。
休業損害に関しては、「差額説」vs「労働能力喪失説」のような学説上の対立はありません。「不就労の状態がある以上、減収がなくても休業損害は認めるべき」とする見解が説かれたことはないとされています。
逸失利益が「どうなるか分からない将来の収入額」を論じるのに対し、休業損害は、いわば過去の収入額に関することです。「現実の金銭の減少額を明確にイメージできるから、観念的な損害発生を肯定する発想がしにくいからであろう」と考えられています(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 127~128ページ)。
減収がない場合の休業損害はこちらをご覧ください。
逸失利益の算定に関する裁判例
裁判例は、原則として差額説に立ちつつも、最近は事案に即した柔軟な判断を示しているといわれています。
「最高裁判例が差額説か労働能力喪失説か」に関してよく取り上げられるのは、次の最高裁判例です。
- 最高裁第二小法廷判決(昭和42年11月10日)
- 最高裁第三小法廷判決(昭和56年12月22日)
- 最高裁第一小法廷判決(平成8年4月25日)
- 最高裁第二小法廷判決(平成8年5月31日)
- 最高裁第一小法廷判決(平成11年12月20日)
昭和42年11月10日判決
昭和42年最高裁判決は、最高裁が「差額説」の立場に立つ実例として引用されるものです。
交通事故によって左大腿複雑骨折等の障害を負った被害者Aが、事故後も勤務を継続し、格段の収入減が生じていなかったケースにおいて、労災保険法によってAに補償を行った国が、Aに代わって加害者に対して損害賠償請求を行ったものです。
第一審、原審ともに労働能力喪失による逸失利益について否定。国が上告しました。
最高裁は、上告を棄却しました。次の通りです。
損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合には、それを理由とする賠償請求ができないことはいうまでもない。
原判決の確定した事実によれば、Aは本件交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけたが、その後従来どおり会社に勤務し、従来の作業に従事し、本件事故による労働能力の減少によって格別の収入減を生じていないというのであるから、労働能力減少による損害賠償を認めなかった原判決の判断は正当であって、所論の判例に反するところもない。
このように最高裁は、労働能力の喪失・減退にもかかわらず損害が発生しなかった場合の損害賠償を否定しました。昭和42年最高裁判決は、最高裁が差額説に立つことを明らかにした判例と解釈されています。
昭和56年12月22日判決
昭和56年最高裁判決は、純然たる「差額説」を修正したものとして評価されています。
旧通産省の技官として勤務していた被害者Xが、歩行中に、Y運転の普通乗用車に衝突され、14級の腰部挫傷後遺症による局部の神経症状の後遺障害を負い、事故前のかなり力を要するプラスチック成型加工業務から、座ったままできる測定解析業務に従事するようになったが、給与面において格別不利益な扱いは受けていないというケースです。
原審(東京高裁昭和53年12月19日判決)は、事故による労働能力の減少を理由とする損害を認定するにあたっては、事故によって生じた労働能力喪失そのものを損害と観念すべきものであり、被害者に労働能力の一部喪失の事実が認められる以上、たとえ収入に格別の減少がみられないとしても、その職業の種類、後遺症の部位程度等を総合的に勘案してその損害額を評価算定するのが相当であるとの見解に基づいて、労働能力喪失率表を参酌のうえ、労働能力喪失率2%、喪失期間は7年間と認めるのが相当とし、Xの年収を基準として34万円余の逸失利益を認定しました。
これに対し、Yが上記「昭和42年最高裁判決」を引用して上告しました。
最高裁は、労働能力喪失説的な考え方を取り入れる余地があるかのような表現をとりつつ、結論的には、事故後に経済的不利益が発生していないことを指摘して、逸失利益の発生を消極視する判断をし、原審を破棄差戻にしました。
かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在または将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。
ところで、被上告人(X)は、研究所に勤務する技官であり、その後遺症は身体障害等級14級程度のものであって右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動障害はなく、事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというのであるから、現状において財産上特段の不利益を蒙っているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。
この判決のもつ意義は、次の3つです。
- 仮に、事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、「後遺症の程度が比較的軽微」であり、「被害者の職業の性質からみて現在または将来における収入の減少も認められない」という場合には、特段の事情のない限り、労働能力の喪失を理由とする財産上の損害は認められない、ということです。
- その特段の事情として、①本人が労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をし、その努力がなければ収入の減少を来している場合、②昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがある場合、を例示していることです。
- 減収を損害と観念するか、身体的機能の喪失自体を損害と観念するかにかかわらず、身体的機能の一部を喪失しても、労働能力の喪失を理由とする財産的損害が認められない場合があるということです。
昭和56年最高裁判決は、減収がない場合について損害の発生を消極視していますが、「後遺症の程度が比較的軽微」であって「職業の性質からみて現在または将来における収入の減少が生じない」場合を前提としているのであって、現時点で減収がないから損害の発生を否定しているのではありません
減収が生じていない場合でも、減収を食い止めるための特別の努力や、昇給・昇任・転職等に際しての不利益な取扱を経済的不利益と把握することで、逸失利益を認める余地を開いたものとして評価されています。
昭和56年最高裁判決の調査官解説は、「本判決が差額説によるものとも、これを捨てたものとも断定することはできないが、身体的機能の喪失自体を損害と観念する余地があるとし、特段の事情が認められるときには減収がなくとも財産上の損害を肯認する余地があるとの含みを持った説示をしている点では、従来の判例に較べて一歩進めた判断を示したものと評価できる」としています(『交通事故賠償における補償・救済システムの現状と課題』保険毎日新聞社78ページ)。
なお、現在においては減収がないとしても、将来において減収が生じる恐れのある場合は、特段の事情を問題とするまでもなく、財産的損害が認められることを当然視しているものと解されています(『交通事故判例解説』第一法規86ページ)。
平成8年4月25日判決
平成8年最高裁判決は、交通事故後に事故と別の原因で被害者が死亡した場合に、逸失利益を認める「継続説」をとるか、逸失利益を認めない「切断説」をとるかの対立についてのものであり、直接的には「差額説」と「労働能力喪失説」の対立と結びつくものではありません。
しかし、この最高裁判決には、逸失利益を労働能力の喪失と捉えているかのような表現があり、労働能力喪失説への接近と評価されています。
交通事故で後遺障害を負った被害者が、その後、別の原因によって死亡し、事故と死亡との間に相当因果関係がない場合、後遺障害逸失利益の算定期間を死亡時までと解するのか、死亡時以降も継続すると解するのかが問題となります。死亡時までと解するのが「切断説」、死亡時以降も継続すると解するのが「継続説」です。
Aは、交通事故により脳機能障害の後遺障害が残り、復職もかなわず、リハビリを兼ねて毎日のように自宅付近の海で貝を採るなどしていたところ、貝採りの際に心臓麻痺を起こして死亡(死亡時44歳)。Aの遺族は、Aの症状固定時から就労可能年数67歳までの逸失利益の賠償を求めました。
この事案は、「貝採り事件」と呼ばれます。原審は、Aの死亡の時点までの損害発生しか認めなかったため、遺族側が上告しました。
最高裁は、原審を破棄差戻とし、次のように判示しました。
交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、いわゆる逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。
その理由とするところは、次の点です。
労働能力の一部喪失による損害は、交通事故の時に一定の内容のものとして発生しているのであるから、交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではなく、その逸失利益の額は、交通事故当時における被害者の年齢、職業、健康状態等の個別要素と平均稼働年数、平均余命等に関する統計資料から導かれる就労可能期間に基づいて算定すべきものであって、交通事故の後に被害者が死亡したことは、前記の特段の事情のない限り、就労可能期間の認定に当たって考慮すべきものとはいえないからである。
また、交通事故の被害者が事故後にたまたま別の原因で死亡したことにより、賠償義務を負担する者がその義務の全部又は一部を免れ、他方被害者ないしその遺族が事故により生じた損害のてん補を受けることができなくなるというのでは、衡平の理念に反することになる。
このように最高裁は、逸失利益の算定期間につき「継続説」をとることを示しました。
平成8年最高裁判決のポイントは、問題となっている損害(=後遺症による逸失利益)が「労働能力の一部喪失による損害」であり、「交通事故の時に一定の内容として発生している」という理解を前提とすることで、交通事故の後に生じた事由によってその内容に消長を来すものではない、と判示していることです。
平成8年最高裁判決の調査官解説は、不法行為後の被害者の死亡という事実を逸失利益の算定の上でどのように考慮するかという点は、「差額説」と「労働能力喪失説」の対立と直ちに結びつくものではないが、「平成8年最高裁判決」によって、「最高裁が労働能力喪失説の立場にさらに一歩近づいたものと評価することも可能であろう」としています(『交通事故賠償における補償・救済システムの現状と課題』保険毎日新聞社80ページ)。
平成8年5月31日判決
最高裁は、この「貝採り事件」判決後、平成8年5月31日判決において、交通事故で後遺障害を残し、その後別の事故で死亡した場合についても、同様に「継続説」の立場で判示しました。
ここでも最高裁は、逸失利益を労働能力の喪失と捉えているかのような表現をしています。
交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害のために労働能力の一部を喪失した場合における財産上の損害の額を算定するに当たっては、その後に被害者が死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。
右のように解すべきことは、被害者の死亡が病気、事故、自殺、天災等のいかなる事由に基づくものか、死亡につき不法行為等に基づく責任を負担すべき第三者が存在するかどうか、交通事故と死亡との間に相当因果関係ないし条件関係が存在するかどうかといった事情によって異なるものではない。本件のように被害者が第二の交通事故によって死亡した場合、それが第三者の不法行為によるものであっても、右第三者の負担すべき賠償額は最初の交通事故に基づく後遺障害により低下した被害者の労働能力を前提として算定すべきものであるから、前記のように解することによって初めて、被害者ないしその遺族が、前後二つの交通事故により被害者の被った全損害についての賠償を受けることが可能となるのである。
平成11年12月20日判決
さらに、平成11年12月20日判決では、事故で要介護状態となった被害者が、事故と無関係な原因で死亡した場合につき、逸失利益については、上記平成8年4月25日、5月31日の判決と同様に継続説を採り、介護費用の賠償については「死亡後の期間に係る介護費用を交通事故による損害として請求することはできない」とし、切断説を採用しました。
この最高裁判決においても、「損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され…」とする指摘があります。
交通事故の被害者が事故に起因する傷害のために身体的機能の一部を喪失し、労働能力の一部を喪失した場合において、逸失利益の算定に当たっては、その後に被害者が別の原因により死亡したとしても、右交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、右死亡の事実は就労可能期間の認定上考慮すべきものではないと解するのが相当である。
しかし、介護費用の賠償については、逸失利益の賠償とはおのずから別個の考慮を必要とする。
すなわち、(一)介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるからにほかならない。ところが、被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果となり、かえって衡平の理念に反することになる。
(二)交通事故による損害賠償請求訴訟において一時金賠償方式を採る場合には、損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され、交通事故後に生じた事由によって損害の内容に消長を来さないものとされるのであるが、右のように衡平性の裏付けが欠ける場合にまで、このような法的な擬制を及ぼすことは相当ではない。
(三)被害者死亡後の介護費用が損害に当たらないとすると、被害者が事実審の口頭弁論終結前に死亡した場合とその後に死亡した場合とで賠償すべき損害額が異なることがあり得るが、このことは被害者死亡後の介護費用を損害として認める理由になるものではない。
以上によれば、【要旨】交通事故の被害者が事故後に別の原因により死亡した場合には、死亡後に要したであろう介護費用を右交通事故による損害として請求することはできないと解するのが相当である。
判決は、「損害は交通事故の時に一定の内容のものとして発生したと観念され、交通事故後に生じた事由によって損害の内容に消長を来さない」としています。
この前提に立てば、介護費用についても、逸失利益と同様に継続説を採ることが理論的帰結になるはずですが、切断説を採用しました。逸失利益は継続説、介護費用は切断説を採ることの合理性については、逸失利益と介護費用の性質上の違いから説明されます。
- 逸失利益が消極損害に関わるものであるのに対し、介護費用は積極損害に関わるものである。
- 逸失利益が、被害者の親族(遺族)の扶養利益に転嫁され得るものであり、実質上この扶養利益の喪失を補填する役割を果たすのに対し、介護費用は、そのような扶養的な性質を有してはおらず、あくまで被害者において現実に支出すべき費用を補填するものである。
- 被害者死亡後も遺族の扶養に関係のない介護費用を支払うことは、遺族に不当な利益を与えることになり、衡平上好ましくない。
これら一連の最高裁判例により、「最高裁判例の発想は、消極損害については身体の毀損状況そのものを損害と評価しつつ、積極損害については現実的経済的負担の存在を損害と評価するもの」と考えられています(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 132ページ)。
一般的に「最高裁は、損害概念について差額説の立場を採っている」と説明されますが、裁判例から明らかなように、様々な修正が試みられているのです。
まとめ
差額説を採るか、労働能力喪失説を採るか、が問題となるのは、後遺障害による労働能力の喪失があるにもかかわらず、現実に収入減少がない場合です。
厳格に差額説によると、減収がなければ逸失利益は認められないことになりますが、近時、最高裁も労働能力喪失説に親和性のある考え方を取り入れており、事案に即した柔軟な判示をしています。。
保険会社が逸失利益を認めないときは、交通事故の逸失利益に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
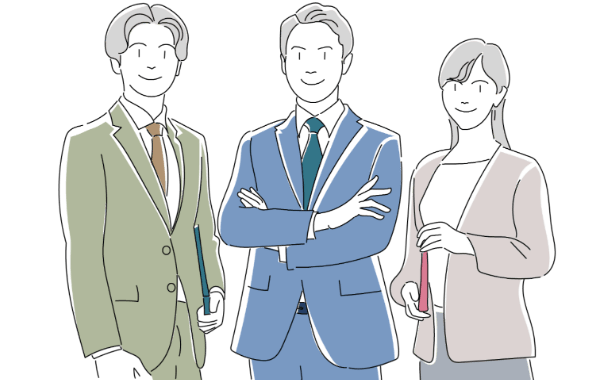
 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
関連
【参考文献】
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 148~149ページ
・『要約 交通事故判例140』学陽書房 203~206ページ
・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 146~150ページ
・『交通事故賠償における補償・救済システムの現状と課題』保険毎日新聞社 70~83ページ
・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 127~129ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 181~183ページ
・『交通事故判例解説』第一法規 60~61ページ、68~71ページ、86~89ページ
・『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 127~132ページ
・『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい 36~38ページ、175~178ページ