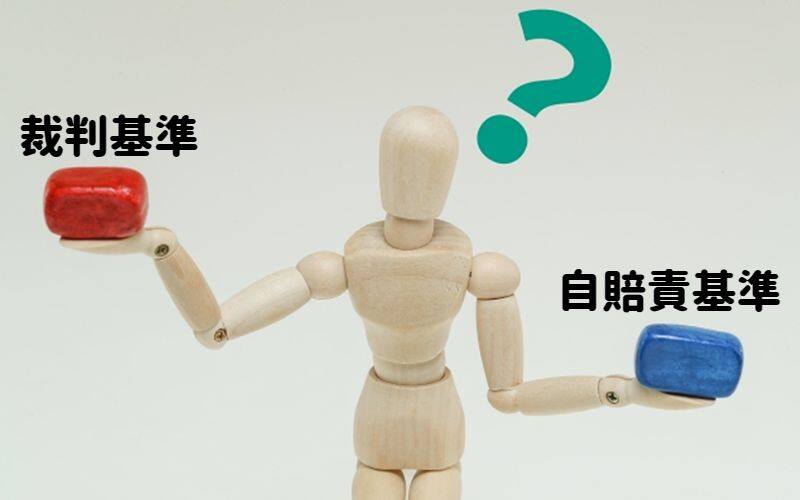※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

事故により後遺症が残り、後遺障害等級が認められても、事故後に収入減少がない場合、保険会社は後遺障害逸失利益を否定する傾向があります。
これに対し裁判所は、減収がない場合に逸失利益を否定する裁判例もありますが、逸失利益を認める裁判例の方が多数です。減収がなくても、後遺障害が残り、将来収入面で不利益になる可能性が高い場合は、逸失利益が認められます。
後遺障害等級が認定されても減収がない場合の逸失利益の算定方法、保険会社に逸失利益を請求するときの主張・立証のポイントについて、解説します。
「減収がない場合の逸失利益」を裁判基準ではどう考えるか?
まず、「減収がない場合の逸失利益」を裁判基準ではどう考えるか、についてです(赤い本・青本の基準は、『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 207~208ページを参照しています。)。
後遺障害逸失利益は、事故による後遺症(後遺障害)によって労働能力が低下し、将来の収入が喪失・減少することを損害(消極損害)と捉え、補償しようというものですから、そもそも収入の減少がなければ、逸失利益は発生しないことになります。
保険会社は、減収がない場合、たいてい逸失利益を否定しますが、裁判基準では、減収の有無は、逸失利益の算定における考慮要素の1つであって絶対的なものではありません。後遺障害が残存したことにより、将来、収入面で不利益になる蓋然性が高い場合は、たとえ現時点で収入減少がなくても、逸失利益が認められる可能性があります。
「赤い本」基準
赤い本では、「逸失利益の算定は、労働能力の低下の程度、収入の変化、将来の昇進・転職・失業等の不利益の可能性、日常生活上の不便等を考慮して行う」との基準を打ち出し、収入の変化(すなわち減収の有無)は、考慮要素の1つであり、絶対的に重視すべきものではないことを示しています。
これは、「後遺障害等級や喪失率、減収の有無といった数値化された目安や事故前後の単純な比較に飛びつくことなどによって、事故後に被害者に生じた具体的な不利益を十分考慮することなく、基準を機械的に当てはめて逸失利益を算定することへの警鐘ともいうべきもの」とされています(『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 208ページ)。
「青本」基準
青本も同様に、労働能力喪失率認定に当たり考慮すべき諸要素の1つとして「減収の有無・程度」を掲げる形を採っています。
また、「事故後の比較的短期間における減収の不発性のみを捉えて逸失利益の不発性を推定するという考え方は明らかに不適切なものであり、事故後の短期間の目に見える減収の不発性の事実を損害算定に直結させるべきではない」としています(『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい112ページ)。
東京地裁交通部における実務
東京地裁民事第27部(東京地裁交通部)における実務については、次のように説明されています。
いわゆる差額説の立場を前提とすれば、逸失利益が認められるためには、後遺障害が生じる前の収入よりも後遺障害が生じた後の収入が減少したことが必要となり、被害者に後遺障害が残存していても実際に減収が生じていない場合には、逸失利益が認められないことになろう。
しかし、後遺障害の程度から見て、通常であれば、収入への影響が予想され、減収が生じていないのは被害者本人の努力による結果であるとみられるようなときには、後遺障害による損害がある程度認められる余地はあろう。
このようなときには、被害者の源泉徴収票あるいは確定申告書控え等被害者の所得の変動に関する証拠を参考に、職業、年齢、後遺障害の内容等を考慮し、後遺障害による損害を具体的に算定している。
(東京地裁民事第27部における民事交通訴訟の実務について『別冊判例タイムズ38』15ページ)
「減収がない場合の逸失利益」についての最高裁判例
「減収がない場合にも後遺障害逸失利益を認めるか?」についての最高裁判例は、次の2つがあります。裁判要旨をご紹介します。
交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によって格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償を請求することができない。
交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。
(最高裁判所Webサイトより)
どちらも、減収がないときは逸失利益を否定するものですが、昭和56年判決は、減収がなくても「特段の事情」があるときは逸失利益が認められる余地がある旨を判示しています。
昭和56年最高裁判例とは?
昭和56年判決について、詳しく見ていきましょう。
通産省工業技術院繊維高分子材料研究所に技官として勤務していた被害者が、14級の腰部挫傷後遺症による局部の神経症状の後遺障害を負い、事故前のかなり力を要するプラスチック成型加工業務から、後遺症のため座ったままできる測定解析業務に従事するようになったものの、給与面において格別不利益な扱いは受けていない。
この事案につき、最高裁は
かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。
とし、続けて
被上告人は、研究所に勤務する技官であり、その後遺症は身体障害等級14級程度のものであって右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動障害はなく、事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというのであるから、現状において財産上特段の不利益を蒙っているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであって、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であっても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。
と判示しています。
つまり、後遺症の程度が比較的軽微であって、被害者の職業の性質からみて現在または将来における収入の減少もない場合には、原則的には後遺症による逸失利益は認められないが、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情があれば、例外的に、減収が生じていない場合でも逸失利益が認められる余地があるということです。
では、「後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情」、すなわち、減収がない場合でも逸失利益の発生が認められる「特段の事情」とは何か?
減収がなくても逸失利益が認められる「特段の事情」とは?
「特段の事情」については、上記の判決文において例示しています。
- 本人が労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしており、この本人の努力がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合
- 本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合
このような「特段の事情」がある場合には、後遺障害による収入の減少が生じていなくても、逸失利益を認める余地があるとされています。
最近の裁判例
減収がない場合の後遺障害逸失利益について、最近の裁判例とその特徴についてご紹介します。
現在は、昭和56年最高裁判決が想定する原則・例外の関係は逆転しているともいわれ、減収がなくても、後遺障害により労働能力の喪失がある場合、逸失利益を認める裁判例の方が多数です。ただし、労働能力喪失率については、労働能力喪失率表と同等あるいは低い喪失率を認定しています。
被害者に減収がなく逸失利益を否定した裁判例は少数で、12級ないし14級の神経症状が残存したという比較的軽微な後遺障害の事案です。他方、減収がないことを考慮して労働能力喪失率表より低い喪失率を認定した裁判例は相当数みられ、労働能力喪失率表と同等の喪失率を認定した裁判例とほぼ同数とされています(『交通関係訴訟の実務』商事法務183~184ページ)。
最近の裁判例
減収がない場合でも後遺障害逸失利益を認めた最近の裁判例をご紹介します。
12級難聴、14級ふらつき、併合12級を残す30歳の国家公務員(裁判所書記官)の女性
直ちには減収が生じることはないとしても、現に裁判所書記官としての業務に支障が生じていることが認められ、昇任昇給等の人事評価上不利益を被ることがあり得ること、その不利益が現実化していない部分があるとすれば、作業効率が下がった中での本人の努力によるものというべきであることが認められるとして、事故前年の収入を基礎に、加齢による聴力低下を考慮し、労働能力喪失期間を30年間、労働能力喪失率を10%として、後遺症逸失利益を認めました。
労働能力喪失率表における12級の喪失率は14%です。
12級足指用廃等併合12級を残す33歳の会社員の女性
減収が生じていないのは、本人の努力等が寄与しているとし、配置転換の可能性は否定できず、その際事務職以外への転換が難しく、今後の昇給や昇格に不利益が生じる可能性が否定できないとして、67歳まで10%の労働能力喪失を認めました。
12級手関節機能障害を残す45歳の会社員の男性
事故後増収しているが労働への現実的影響が出ているとして、「12級の労働能力喪失率14%より若干減じた12%とするのが相当である」としました。
「派遣社員の場合は転職の可能性が高いことが考慮される」としました。
12級足指用廃等併合12級を残す24歳の公務員の女性
後遺障害がもたらす経済的不利益を是認するに足る特段の事情が認められるとして、67歳まで12%の労働能力喪失を認めました。
11級脊柱変形等併合10級を残す54歳の国家公務員の男性
定年までは実収入を基礎に喪失率20%、以降9年間は賃金センサス学歴計年齢別平均を基礎に喪失率27%で逸失利益を認めました。
労働能力喪失率表における10級の喪失率は27%です。
(裁判例は、『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社398ページ(注308)より)
裁判例の特徴
減収がない場合の後遺障害逸失利益については、被害者の具体的な症状や職業・収入など被害者の特性、後遺障害の類型的な特性を考慮し、判断します。
被害者の特性を考慮
例えば公務員の場合、民間企業の従業員と比べ、勤務先が安定しており身分保障が手厚いため、事故後も従前どおりの雇用条件が維持される蓋然性が高いという特殊性が考慮されます。
こういう場合、定年までは減収がないことを考慮して、症状固定時から定年までは、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率より低い喪失率を認定しつつ、定年後(就労可能年限の67歳まで)は後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を認定する裁判例が相当数あります。
定年後は、再就職により、それまで減収を免れていた「特別の事情」が消失し、労働能力喪失率表と同等の減収が生じる蓋然性が高いと考えられるからです。
基礎収入についても、定年までは現実収入を認定し、定年後は賃金センサスを用いて算定する裁判例が多いようです。
基礎収入を現実収入とした上で、67歳まで一律の労働能力喪失率を適用する裁判例もあります。そのほとんどが、認定された後遺障害等級に対応する労働能力喪失率より低い喪失率を認定しています。
後遺障害の類型的な特性を考慮
例えば顔面醜状や嗅覚脱失など労働に直結しにくい類型の場合に問題となります。
顔面醜状は、身体的機能を左右するものではないので、直接的には労働に影響を及ぼさず、通常は逸失利益が発生しないと考えられます。
しかし、被害者の性別、年齢、職業等を考慮し、職業選択の幅が狭まるなどといった影響が生じる恐れがある場合には、具体的に顔面醜状が就労にどうマイナスに影響するかを判断し、労働能力喪失を肯定する裁判例も多くあります。
嗅覚脱失は、調理師など特殊の職業を除けば、直接的に労働に影響が生じないのが通例であるから、その逸失利益が問題となる。
主張・立証のポイント
減収がない場合において、後遺症による逸失利益を肯定した裁判例では、個々の事案に即して、「特段の事情」の存在を認めた上で、逸失利益を肯定しています。したがって、「特段の事情」について主張・立証が重要です。
具体的に業務上の支障を主張・立証
「特段の事情」の主張・立証においては、注意点があります。
それは、抽象的に、本人の特段の努力等により収入が維持されているとか、将来における減収の蓋然性を主張するだけでは足りない、ということです。
例えば、「本人の努力」について、単に「痛みを我慢して就労している」と主張するだけでは、「慰謝料に織り込み済み」とされてしまいます。また、「本人の努力」それ自体を立証すれば足りるのではなく、本人の努力がなければ減収していたであろう事実について、具体的な立証が必要となります(昭和56年最高裁判例参照)。
つまり、将来的に減収が顕在化する蓋然性の高い根拠として、後遺症により実際に日常生活や業務において支障が生じている事実や、本人の特段の努力や周囲の配慮の内容およびそれが長期間継続することが合理的に期待できないものであること等について、具体的に主張・立証する必要があるのです。
裁判例において「特段の事情」として考慮され、逸失利益が認められてきた要素とは具体的にどのようなものでしょうか?
「特段の事情」として考慮される要素とは?
裁判例において、「特段の事情」として考慮されている要素としては、次のようなものがあります。
- 本人の特別の努力
- 勤務先の配慮、周囲の支援・協力
- 業務への支障の程度
- 昇進・昇給における不利益
- 退職・転職の可能性
- 勤務先の安定性・給与体系を含めた雇用の継続性
- 日常生活上の支障の有無・程度
(参考:『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 212~213ページ)
それぞれ具体的に次のような内容が、裁判において考慮されています(裁判例については『交通関係訴訟の実務』商事法務184~187ページより)。
本人の特別の努力
- 理学療法、鍼灸マッサージ、ストレッチ、リハビリ等を行っている(千葉地裁平成23年4月12日判決、横浜地裁平成24年12月20日判決)
- 肉体的症状・精神的な苦痛を我慢して勤務している(名古屋地裁平成19年10月26日判決、大阪地裁平成21年1月13日判決、東京地裁平成21年12月10日判決)
- 事故前の多年の業績、評価、人間関係、修練技術で障害を克服している(千葉地裁平成22年1月29日判決)
- 業務への支障をカバーするために残業をこなしている(名古屋地裁平成22年7月2日判決、大阪地裁平成22年10月26日判決)
勤務先の配慮、周囲の支援・協力
- 和室での接待が不便で他人に代わってもらっている(大阪高裁平成18年6月29日判決)
- 荷物を持っての移動が困難で他の職員の助けを借りている(京都地裁平成25年2月14日判決)
業務への支障の程度
- 自動車の運転が困難となり外回りの勤務に支障が生じている(大阪高裁平成18年6月29日判決、名古屋地裁平成23年11月18日判決、横浜地裁平成24年5月30日判決)
- 長時間自席に座り高度の知的判断作用を含む業務を遂行するについて、後遺障害により集中力が持続しないため能率や気力が低下している(東京地裁平成19年6月20日判決)
- 疼痛等により長時間上を見る姿勢を取ることや、脚立やはしごの昇降、前屈みの姿勢でハンマーを使う作業を長時間行うことなどが困難である(名古屋地裁平成19年10月26日判決)
- 患者と目線を合わせて話す姿勢がとれず、患者から助けを求められても対応が困難であり、調理の際に長時間立っていることも難しい(大阪地裁平成23年4月13日判決)
昇進・昇給における不利益
- 勤務先である市の給与体系が勤務実績をより反映させるようになってきており、被害者の定例の昇給も遅れていること(大阪地裁平成20年3月14日判決)
- 総合職として様々な部署を経験しながら昇進していくのが通常であるのに、後遺障害のため営業職や生産現場等を経験し難い(大阪地裁平成21年2月26日判決)
- 准看護師から正看護師やリハビリ看護の認定看護師になるのが困難となった(大阪地裁10月26日判決)
- 教師であるのに担任を持てず、クラブ活動や公式行事の引率もできない(京都地裁平成25年2月14日)
退職・転職の可能性
- 後遺障害部位が影響しない部署への配置転換希望が認められなかった(神戸地裁平成18年12月22日判決)
- 症状悪化により再度休職を余儀なくされ、分限免職処分を受ける可能性がある(大阪地裁平成24年9月19日判決)
勤務先の安定性・給与体系を含めた雇用の継続性
- 勤務先が世界的に有数の外資系金融機関であり、成績主義・能力主義を採用しており、労働能力の差が労働条件に大きく反映される雇用環境にある(東京地裁平成19年6月20日判決)
- 比較的規模の大きい工事の発注が続き売上が上昇したため、被害者の役員報酬も増額されたが、今後とも安定した業績を得られることが確実ではない(名古屋地裁平成19年10月26日判決)
日常生活上の支障の有無・程度
後遺症による逸失利益は、後遺障害が残存して労働能力が低下することにより将来発生すると認められる収入の喪失ですから、基本的には収入に関連付けられる労働能力の低下と結びつけて検討されます。
もっとも、裁判例においては、損害発生の有無や労働能力喪失の程度を認定するにあたり、従事する仕事上の支障に限らず、日常生活における不便や苦痛といった日常生活上の支障を認定しながら判断している例が多く見られます。日常生活上の支障が労働に影響を与えることは十分に予想されることでから、後遺障害による日常生活上の支障が及ぼす影響も考慮要素となるのです。
最初に紹介したように、赤い本が逸失利益の算定において「日常生活上の不便」を考慮要素の1つとしているのも、このためです。
事故後明白な減収がない場合、生活上の障害や不利益の存在があることを立証して、本人の格別の努力や周囲の協力があるために減収を免れていることを印象付けることが、逸失利益の認定につながります。
まとめ
後遺障害により、業務に支障が生じている場合や、昇進昇給に不利益が生じる可能性がある場合、あるいは、本人の努力や勤務先・同僚の配慮により減収が表面化していない場合など、特段の事情があるときは、事故後減収がなくても逸失利益が認められる可能性があります。
保険会社から逸失利益を否定され、納得のいかないときは、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
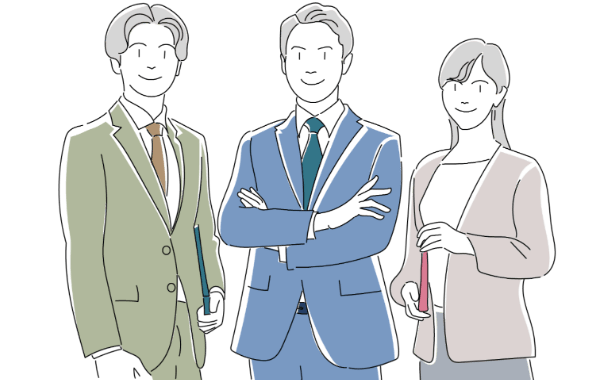
 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
関連
【参考文献】
・『別冊 判例タイムズ38』15ページ
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 181~187ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 148~151ページ
・『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい 36~38ページ、175~180ページ
・『交通事故紛争処理の法理』ぎょうせい 281~301ページ
・『交通事故損害賠償の新潮流』ぎょうせい 280~284ページ
・『交通賠償実務の最前線』ぎょうせい 109~116ページ
・『新版 注解 交通損害賠償算定基準』ぎょうせい 207~214ページ
・『交通事故賠償における補償・救済システムの現状と課題』保険毎日新聞社 70~90ページ
・『Q&A交通事故の示談交渉における保険会社への主張・反論例』日本加除出版株式会社 84~87ページ
・『要約 交通事故判例140』学陽書房 205~208ページ
・『被害者側弁護士のための交通賠償法実務』日本評論社 396~398ページ
・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 146~150ページ
・『交通賠償のチェックポイント第3版』弘文堂 149~151ページ
・『現代損害賠償法講座7』日本評論社 187~199ページ
・『三訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 127~129ページ、141~145ページ