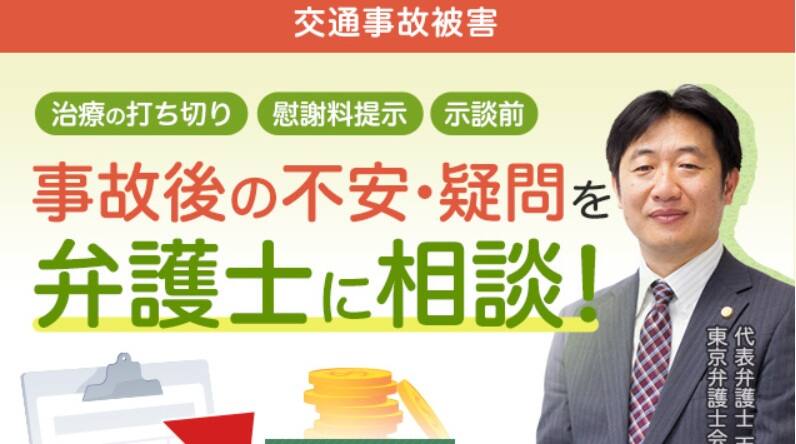※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
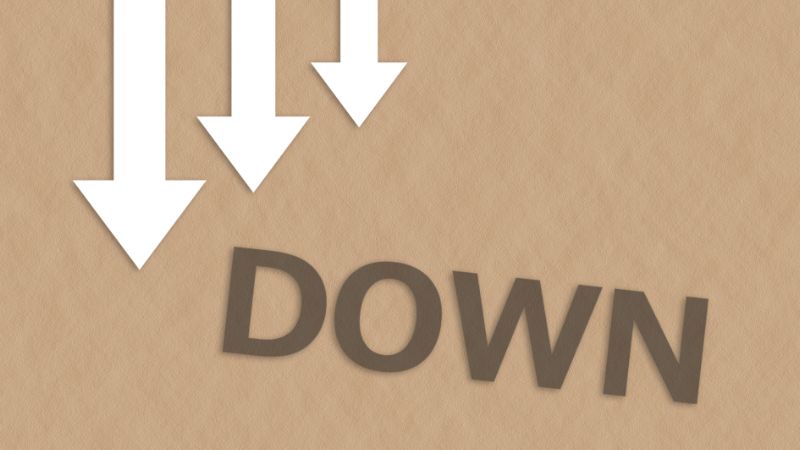
事故歴のある車両は、無事故車両に比べ、下取りや売却の際に評価が下がります。これが評価損です。ただし、車両の損害賠償において、常に評価損が損害として認められるわけではありません。どんな場合に評価損が認められるのか、評価損の判断基準や算定方法などについて、詳しく見ていきましょう。
評価損とは?
「評価損」とは、事故前の車両価格と修理後の車両価格の差額のことです。
事故車両は、たとえ十分に修理しても、修理後の車両価格が事故前の車両価格を下回ります。中古車市場において、事故歴のある車両は無事故車よりも減価します。これが評価損です。格落ち損とも呼ばれます。
評価損の発生原因
なぜ、修理後の車両価格が事故前の価格より下落するのか? すなわち「評価損の発生原因」として、次の4つが挙げられます(参考:東京地裁判決・昭和61年4月25日)。
- 修理技術上の限界から、顕在的に、自動車の性能・外観が低下すること。
- 事故による衝撃のために車体各種部品に負担がかかり、修理後間もなくは不具合がなくても、経年的に不具合が発生しやすくなること。
- 修理後も隠れた損傷があるかもしれないとの懸念が残ること。
- 事故に遭ったということで縁起が悪いと嫌われる傾向にあること。
①②は、使用価値の侵害に対応する「技術上の評価損」、③④は、交換価値の侵害に対応する「取引上の評価損」と、区別されます。取引上の評価損が「いわゆる評価損」です。技術上の評価損を含めて「広義の評価損」といいます。
技術上の評価損、取引上の評価損、それぞれ詳しく見ていきましょう。
技術上の評価損
技術上の評価損とは、修理技術上の限界から機能や外観に障害が残り、車両の使用価値が低下する場合の損害です。例えば、事故前に比べて、エンジンの調子が悪い、ドアの開閉に難がある、塗装ムラが目立つ、などの場合です。客観的評価損ともいわれます。
欠陥が残存している以上、車両価値は事故前と比べて低下していると考えられるため、技術上の評価損については、損害賠償の対象となることに、ほぼ争いはありません。
だだし、修理して走行性能は回復したものの外観の欠陥が残ったという場合は、車種によって評価損が認められる場合と認められない場合があります。
自家用車、タクシー、バスなど、美観が要求される車両の場合は、使用価値の低下が認められますが、トラックなど外観がそれほど重要でない車両の場合は、多少美観が損なわれても使用価値が低下するとはいえず、評価損が認められにくい傾向があります。
取引上の評価損
取引上の評価損とは、機能や外観上の障害はないものの、事故歴があるという理由で車両の交換価値が下落する場合の損害です。事故車であることの買主の心理的な不安感にもとづくもので、主観的評価損ともいわれます。
取引上の評価損については、実際に売却されない限り損害が顕在化しないことから、損害として認めるか否か、争いがあります。近時の裁判例は、取引上の評価損についても、損害として認める傾向にあります。
取引上の評価損を否定する見解
かつては、次のような理由から、取引上の評価損を否定する見解がありました。
- 修理によって原状回復され欠陥が存在していない以上、客観的には価値の低下はない。
- このような損害は事故車両を売却して初めて現実化するものであるが、事故後も事故車両を売却せず使用している限り、損害として現実化していない。
- 修理が可能であるから車両の買替えが認められないのに、買替えたと仮定して評価損を認めると、買替えを認められない場合に、買替えを認めたのと同一の利益を被害者に与えることになってしまう。
取引上の評価損を肯定する見解
中古車市場では、補修歴の表示義務があり、修理した車両は「事故歴車」「修復歴車」として販売されます。そのため、事故車両は、十分に修理しても、売却する場合や下取りに出す場合に、無事故者と比べ売却価格や下取り価格が低く評価されます。
現在は、次のように考え、取引上の評価損を肯定するのが一般的です
- 中古車市場において、事故歴や修理歴のある車両の価格が低下することは公知の事実。
- 評価損も他の損害と同様、事故時に発生していると評価でき、事故車両を売却して価格の低下が現実化していることまでは要しない。
こうして、取引上の評価損を肯定した上で、具体的な事情に応じて、評価損の有無・金額を判断しています。
取引上の評価損を肯定する理由としては、次のような点が挙げられます。
- 車両損害は、基本的には車両の事故前と事故後の価値(修理前の車両価値)の差額と考えられ、この基本的な考えからは取引上の評価損が認められることが合理的である。
- 下取りに出さなければ現実に損害は発生しないというが、自動車の交換価値の低下を積極損害とみれば、むしろ事故時に交換価値の減少が発生したとみることができる。
- 修理の後も隠れた損傷があるかもしれないとの懸念が残る。
- 事故に遭ったことで縁起が悪いこと等の諸点から中古車市場の価格が事故に遭っていない車両よりも減価される。
- 評価損には車両損害を機械的、算数的な計算ではカバーしきれない主観的・非合理的な部分を吸収して損害額を評価できて実際の解決に妥当である。
(参考:『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 264ページ)
評価損の判断基準と考慮要素
評価損の有無や程度の判断においては、次の要素が考慮されます。
| 市場流通性 | 損傷の車両価値への影響 |
|---|---|
|
|
高級車、車両の希少性との関連性
高級車は大衆車より、大衆車でも人気車は、評価損が認められやすい傾向にあります。希少車両も、評価損が認められやすい傾向にあります。
初度登録から事故時までの時間的経過の長短
「初度登録からの期間」「走行距離」については、次の期間あるいは距離を経過すると、評価損が認められにくくなる傾向があります。
| 車種 | 初度登録からの期間 | 走行距離 |
|---|---|---|
|
外国車 |
5 年 | 6 万㎞ |
| 国産車 | 3 年 | 4 万㎞ |
損傷、修理・修理費の程度
一般的には、損傷が大きく修理費が大きいほど、評価損が発生しやすく認められやすいと考えられます。
ただし、比較的小さな損傷や少ない修理費でも評価損の請求認められる場合があり、裁判例では、損傷や修理費の大小は、評価損の認定には、あまり影響を与えていない傾向にあります。
事故減価額証明書
一般財団法人日本自動車査定協会の事故減価額証明書は、1つの資料として考慮要素となり得ますが、減価額の査定基準が明確でないため、同証明書を提出しても、記載された減価額が認められるとは限りません。
なお、事故減価額証明書の取得費用(査定料)は、同証明書が評価損の立証に不可欠なものではなく、事故によって通常支出が予定される費用とはいえないことから、事故と相当因果関係のある損害とは認められず、賠償請求は否定されています(京都地裁判決・平成4年11月24日)。
評価損の算定方法
評価損の算定方法については、次のような4つの方法があります。
差額基準方式(減価方式)
事故時の価格と修理後の価格との差額(減価)を評価損とする方法。事故直前の車両売却価格と修理後の車両売却価格との差額です。
時価基準方式
事故時の価格の一定割合を評価損とする方法。妥当な時価算出が難しく採用する裁判例は少ないのですが、初度登録から数ヵ月しか経過していない極端に新しい自動車の場合に採用されることがあるようです。
総合勘案基準方式
諸要素を斟酌し、金額で示す方法。被害車両の車種、初度登録からの経過年数、修理金額などを総合勘案して、金額で決定する方法です。金額は、裁判官の職権によって決定されます。
修理費基準方式
修理費(裁判所が認容した修理費)の一定割合を評価損とする方法。裁判例の多くは、この方式を採用しています。修理費の何%とするかは、バラつきがあり、修理費の10~30%台とするのが多いようです。
一般に、損傷の程度が大きいほど修理費が高額になり、車両の価値の低下も大きくなります。このように修理費の金額と評価損は比例関係にあると考えられるので、実務における評価損の算定方法は、修理費の一定割合とする修理費基準方式が多いようです。
外国車は修理費の20%以上、国産車は10%台での肯定例が多く、新車同然の車両や希少価値のある高級車などでは、修理費の50%以上の認定例もあります。
評価損の請求権者
評価損は、車両価値の下落を損害として捉え、自動車の所有権侵害に対する損害賠償請求ということになるので、被害車両の所有者が正当な請求権者となります。
割賦販売の場合、評価損の請求権は、所有権留保者(販売店・信販会社)にあり、購入者(使用者)は、修理費を請求することはできても、評価損は請求できません。
リース契約車両も同様に、所有権はリース会社にあるため、評価損の請求権は、リース会社に帰属します。ユーザーは、修理費は請求できても、評価損を請求することはできません。
まとめ
事故車両を修理しても機能や外観に欠陥が残ったり、事故歴があることにより中古車取引市場での価格が低下したりすることがあります。このような事故による車両価値の低下を評価損といいます。
示談交渉で、損害保険会社が評価損を認めることはなく、たいていは裁判で判断されます。裁判所が認定する修理費の何%かを評価損として認める裁判例が多いようです。
また、裁判例の傾向としては、外国車または国産人気車種では、初度登録から5年(走行距離で6万㎞程度)、一般の国産車では、初度登録から3年(走行距離で4万㎞程度)を経過すると、評価損は認められにくくなります。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通関係訴訟の実務』商事法務 442~445ページ
・『物損交通事故の実務』学陽書房 48~50ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 177~179ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 89~93ページ
・『改訂版 交通事故実務マニュアル』ぎょうせい 197~200ページ
・『交通事故と保険の基礎知識』自由国民社 194~195ページ
・『事例にみる交通事故損害主張のポイント』新日本法規 265~269ページ
・『交通損害関係訴訟 補訂版』青林書院 237~240ページ
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 211~212ページ、249~269ページ
・『要約 交通事故判例140』学陽書房 285~286ページ
・『交通事故損害賠償保障法 第2版』弘文堂 340~341ページ
・『別冊判例タイムズ38』17~18ページ