

※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

ペットは、法的には「物」ですから、交通事故では、物損として扱われます。しかし、ペットには生命があり、家族の一員として大切にされているため、一般的な物損とは多少異なる扱いがされる部分もあります。
交通事故でペットが死傷したときの損害賠償請求について、詳しく見ていきましょう。
交通事故によるペットの死傷は物損
交通事故によるペットの損害を考える場合、ペットは、民法上「動産」に分類され、車両の損害と同じ物損(財産権の侵害に係る損害)として扱われます。
とはいえ、ペットには生命があり、単なる「物」とは異なります。しかも、飼主は、飼っているペットを家族の一員であるかのように大切にしているものです。
また、動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、「動物が命あるものであることにかんがみ、・・・適正に取り扱うようにしなければならない」と定めています。
動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
そのため現在では、ペットを単なる「物」として扱うことは相当ではない、という意識の高まりを背景に、ペットの死傷に対し、一般の物損とは異なる損害賠償が認められる場合があるのです。
ペットの死傷に対する損害賠償について、車両損害の場合と比較しながら見ていきます。なお、ペットの死傷はあくまでも物損です。飼主の方にとっては、表現が気になる部分もあるかもしれませんが、ご理解ください。
ペットが死亡したときの損害賠償請求
まず、ペットが交通事故で死亡した場合の損害賠償請求についてです。ペットの死亡は、車両損害でいえば物理的全損に相当します。
自動車の場合は、被害車両が全損と判断されると、買替えが認められ、被害車両の時価相当額(同等車両の再調達価格)が損害賠償額となります。ここでは、買替差額や買替諸費用など細かい部分は省略します。
ペットが死亡した場合も同様に、事故当時のペットの時価相当額(同種同等の動物の再購入費)が、損害賠償の対象となります。
ここで問題となるのが、時価額(被害物件の事故当時の価格)の算定方法です。自動車であれば、被害車両の時価額を中古車市場における同等車両の販売価格をもとに算定しますが、ペットの場合には、中古車市場に相当するような流通市場がありません。
ペットの時価額は、どう算定するか?
ペットの価格を把握できるのは、ペットショップにおける同種類の動物の価格ぐらいです。ペットショップで販売しているのは、生まれて間もない子犬や子猫。自動車でいえば、新車に相当します。
ペットの時価額を算定しようにも、飼育して数年経過したペットを売買する市場がないため、市場価格を把握することができないのです。そもそも、ペットには生命がありますから、飼っている途中でいらなくなったからと売ることは許されません。
そこで、ペットの時価額の算定には、次のような方法がとられます。
ペットの購入価格や年齢を考慮して時価額を算定
ペットの時価額(財産的価値)は、通常、ペットの購入価格や年齢を考慮して判断します。具体的には、購入価格を平均寿命で割り、平均寿命から死亡時の年齢を差し引いた年数を乗じて求めるのが一般的です。
交通事故による事案ではありませんが、例えば、こんな裁判例があります。
ミニチュア・ダックス(オス・5歳)が他の犬に噛み殺された事故で、死亡時の流通価格を、購入金額(15万3,157円)の約3分の1の金額(5万円)と算定しました。
ペットの時価額は低い
ペットの事故当時の価格(財産的価値)を把握できたとしても、その時価額は、飼い始めたときと比較して、著しく低廉化しているのが普通です。そのため、商業用の動物は別として、ペットそのものの財産的価値の損害賠償を請求し、認容された例は少ないようです。
特殊なケースとして、例えば、品評会での入賞実績がペットの財産的価値に影響を与えたり、ブリーディングに用いられる犬や猫の場合は、交配料という経済的利益が生じるため、死亡時の時価額が購入価格よりも高くなることがあります。
ペットの財産的価値(時価額)は低く評価されますが、その代わり、飼主の精神的苦痛に対して慰謝料が認められることがあります。
商業用動物の損害賠償
商業用の動物が死亡した場合は、その財産的価値が損害賠償において考慮される余地があります。例えば、こんな裁判例があります。
地方競馬の競走馬が死亡した事案において、休業損害として178万6,120円、逸失利益として784万4,382円の賠償が認容されました。
被害動物の社会的価値から時価額を算定した例
死亡した盲導犬の財産的価値(時価額)について、購入金額や市場価格を基礎とせず、盲導犬としての社会的価値を評価し、盲導犬育成に要した費用を基礎に財産的価値を算定した裁判例があります。
判決は、盲導犬の死亡自体による損害に関し、当該盲導犬の死亡時における客観的価値によるべきだとした上で、盲導犬の社会的価値を評価し、その能力を身に付けるために要した費用(当該盲導犬の育成に要した費用)を基礎に考えるのが相当としました。
個々の盲導犬の客観的価値の算定においては、基本的には、当該盲導犬の活動期間を10年とみた場合の残余活動期間の割合に応じて、当該盲導犬の育成費用を減じるのが相当というべきであり、盲導犬としての経験を積み重ねることによって、一般的、客観的にも盲導犬としての技能が貸与時より向上したと評価し得る場合には、この点をも考慮して算定するのが相当としました。
具体的な算定方法は、こうです。
盲導犬Aの育成に要した費用は、盲導犬Aが訓練を受けた年度に支出した育成費用の合計を、同年度に育成されていた盲導犬の頭数(10頭)で割った 453万1,037円と判断。その上で、盲導犬Aについては、残余活動期間約5.13年を基礎に、一般的、客観的な技能の向上も考慮して 260万円と算定しました。
盲導犬のように専門的な訓練を受け、特別な技能を取得し、活躍している動物は、他にも警察犬、聴導犬、介助犬、セラピー犬、災害救助犬など、たくさんいます。
こうした動物については、社会的価値を有していることから、比較的高い財産的価値が認められる可能性があります。
ペットの治療費の損害賠償請求
次に、交通事故でペットが怪我をして、治療費や入院費を損害賠償請求する場合です。ペットの治療費・入院費は、自動車でいえば修理費に相当します。
ペットの治療費には、経済的全損の考え方を形式的に適用しない
ペットの治療費の損害賠償で大事なのは、ペットの治療費には、経済的全損の考え方を形式的に適用しない、ということです。
物損には、経済的全損の考え方があります。自動車の場合、修理費が車両時価額を超えると経済的全損と判断され、買替えが認められますが、買替えをしても修理をしても、車両時価額が損害賠償額の上限となります。
ペットの治療費は、経済的全損の考え方を形式的に適用せず、ペットの時価額を超える金額が損害として認められる場合があります。
ペットの治療費に経済的全損の考え方を適用すると、治療費の上限が、ペットの時価相当額となります。ペットの治療費は、公的な医療保険がありませんから高額となります。その一方で、ペットの時価額は低廉です。
例えば、治療費が30万円かかっても、ペットの時価額が5万円であれば、損害賠償額は5万円です。ペットの治療費に経済的全損の考え方を形式的に適用すると、十分な損害賠償を受けられなくなるのです。
ペットの時価額を超える治療費を認めた裁判例
ペットには生命があり、飼主としても可能な限り生命を守りたいと思うものです。治療費が時価額を超えるからといって、必要な治療を断り、別の動物を購入するようなことはしないでしょう。
ペットを単なる「物」とみて、物損の損害賠償の考え方を形式的に適用することは相当ではないとして、時価相当額を超える治療費を認める裁判例も出てきています。
愛玩動物のうち家族の一員であるかのように遇されているものが不法行為によって負傷した場合の治療費等については、生命を持つ動物の性質上、必ずしも当該動物の時価相当額に限られるとするべきではなく、当面の治療や、その生命の確保、維持に必要不可欠なものについては、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認められる限度において、不法行為との間に因果関係のある損害に当たるものと解するのが相当である。
この裁判例は、後方から追突された被害車両に乗せていたペットの犬(ラブラドールレトリバー、購入価格6万5,000円)が、第二腰椎圧迫骨折の傷害を被り、後肢麻痺、排尿障害の症状が残った事案です。
裁判所は、治療費11万1,500円、車いす製作料2万5,000円、合計13万6,500円を損害と認めるとともに、飼主夫婦に20万円ずつ計40万円の慰謝料も認めました。
この名古屋高裁判決には、5つのポイントがあります。
- 被害犬の時価額を超える治療費を認めました。
- 「当面の治療費や、その生命の確保・維持に必要不可欠な費用」として、被害犬が入院し、症状が安定して光線治療を受けるようになるまでの間の治療費が該当すると具体的な判断を示しました。
- 被害犬の後肢麻痺などの症状に鑑み、車いす制作費についても必要性を認めました。
- 飼主への慰謝料を認めました。
- 犬用シートベルトなど動物の体を固定するための装置を装着していなかったことにつき、過失相殺を認定しました。
このように、ペットの治療費は、「当面の治療や生命の確保・維持に必要不可欠なもの」については、時価相当額を念頭に置いた上で、社会通念上、相当と認める限度において、事故との相当因果関係のある損害として認められることがあります。
ペットの死傷に関する慰謝料
物損については、財産上の損害を賠償することにより、精神的苦痛も慰謝されると解され、原則として慰謝料は認められません。物損事故の慰謝料請求はこちらをご覧ください。
ペットの死傷は物損ですから、ペットの死傷に対して慰謝料は認められません。ただし、ペットが死亡したり、重い傷害を負った場合は、飼主の精神的苦痛に対し慰謝料が認められることがあります。
人損と物損の慰謝料請求の違い
人身事故の場合は、被害者本人に慰謝料が認められます。被害者が死亡した場合は、被害者本人のほか、遺族の慰謝料が認められます。被害者が重篤な傷害を負った場合にも、被害者本人の慰謝料に加え、その家族にも慰謝料が認められます(近親者慰謝料)。
ペットは、基本的には「物」として扱われますから、ペット(人間でいえば被害者本人)の慰謝料は認められません。
しかし、ペットは生命を持ち、家族の一員であるかのように扱われ、飼主にとってかけがえのない存在です。ペットが死亡もしくは重傷を負い、飼主が甚大な精神的苦痛を受けたときは、飼主に慰謝料が認められる場合があります。
ペットが重傷を負った場合の慰謝料についての裁判所の判断
ペットが重傷を負った場合の飼主の慰謝料請求について、次のように判示した裁判例があります。
愛玩動物が不法行為により重い傷害を負ったことにより、当該動物が死亡した場合に近い精神的苦痛を飼主が受けたときは、飼主の精神的苦痛は、社会通念に照らし、主観的な感情にとどまらず、損害賠償をもって慰謝されるべき精神的損害として、飼主は、これを慰謝するに足りる慰謝料を請求することができるもとと解するのが相当である。
被害車両が停止中に追突され、その衝撃で、被害車両に乗せられていた被害犬が、後部座席から前方のカーナビゲーションに衝突。事故後、被害犬は、継続的に全身の震えや食欲不振といった症状を示すようになった事案です。
判決は、ペットが死亡するに至らなかった場合についても、飼主の慰謝料請求が認められる余地があることを認めました。
ただし、本事案については、被害犬が飼主にとってかけがえのない存在になっていることは認められるとしつつも、本件事故により、被害犬が負った被害は、全身の震えや食欲不振といった症状にとどまり、飼主の被った精神的苦痛は、社会通念上、損害賠償をもって慰謝されるべきものとまでは言い難いとして、慰謝料請求は否定しました。
ペットが重篤な傷害を負った場合に慰謝料を認めた裁判例として、先に紹介した名古屋高裁判決(平成20年9月30日)があります。
ペットの葬儀費用
ペットが死亡した場合の葬儀費用は、否定されることが多いようです。これは、ペットの葬儀をあげることが、社会通念上一般的とはいえないからです。
火葬代を認めた裁判例(札幌高裁判決・平成19年9月8日)がありますが、相手が争わなかったからのようです。火葬代も葬儀費用と同様に、認められることは困難です。
過失相殺
交通事故でのペットの負傷につき、管理者の過失が問われ、過失相殺されることがあります。例えば、次のような場合です。
- ペットを放し飼いにしていた場合
- ペットにリードを装着せず、ペットが路上に飛び出した場合
- 車に乗せていたペットに、ペット用のシートベルトを装着していなかった場合
先に紹介した名古屋高裁判決(平成20年9月30日)は、過失相殺について、次のように認定しました。
飼主は、動物を乗せて自動車を運転する者として、事故によって予想される危険性を回避し、あるいは、事故により生じる損害の拡大を防止するため、犬用シートベルトなどの動物の体を固定するための装置を装着させるなどの措置を講ずる義務を負うとし、これを怠った点に過失を認めて、被害者の過失割合を1割と判断しました。
まとめ
ペットは、法的には「物」に分類され、交通事故で死傷した場合は、物損として扱われます。
しかし、動物愛護法の施行等、ペットの社会的位置づけの変化にともない、今日では、ペットを単なる「物」として扱うことは相当でない、とする意識が高まっています。
裁判例でも、物損における経済的全損の考え方を形式的に適用することはせず、ペットの時価額を超える治療費を認める例や、物損では通常認められない慰謝料を認める例があります。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
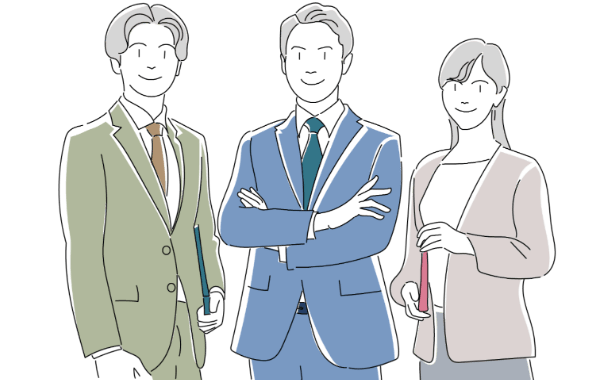
 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂 345~346ページ
・『新版 交通事故の法律相談』青林書院 307ページ
・『交通賠償のチェックポイント』弘文堂 191ページ
・『物損交通事故の実務』学陽書房 96~105ページ
・『Q&Aと事例 物損交通事故解決の実務』新日本法規 146~148ページ、246~258ページ





