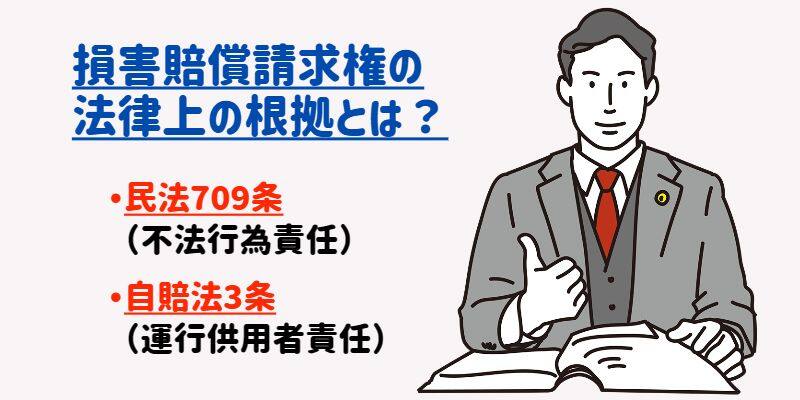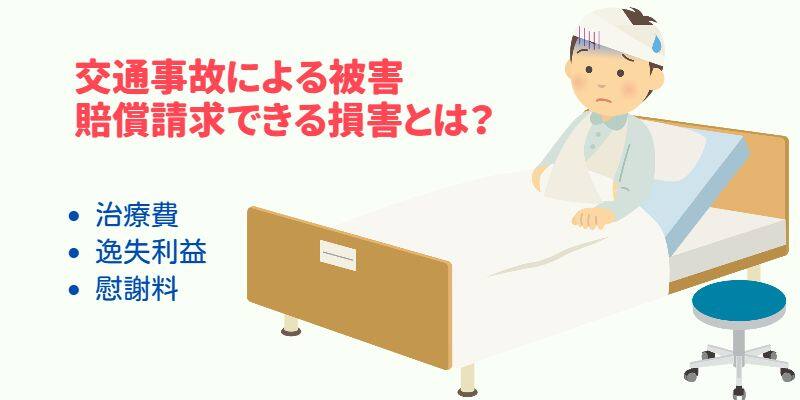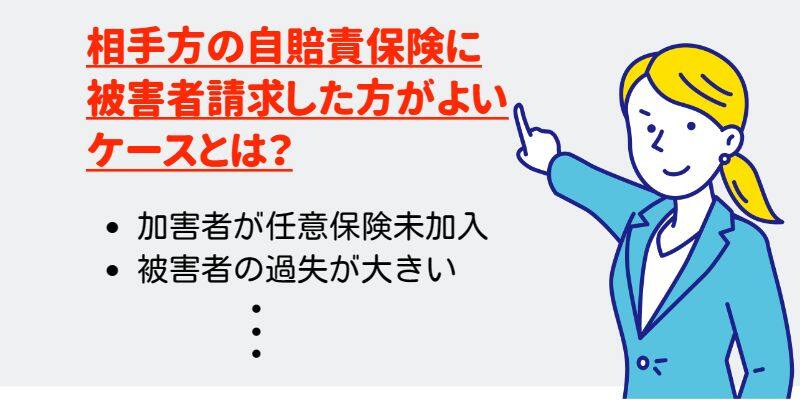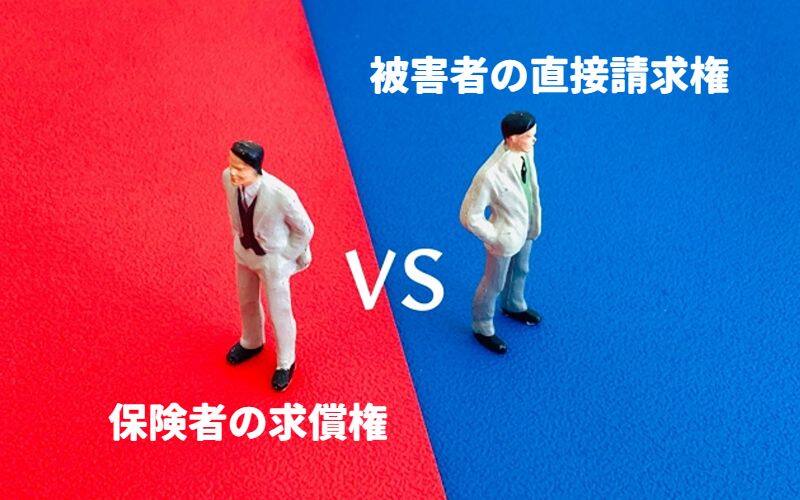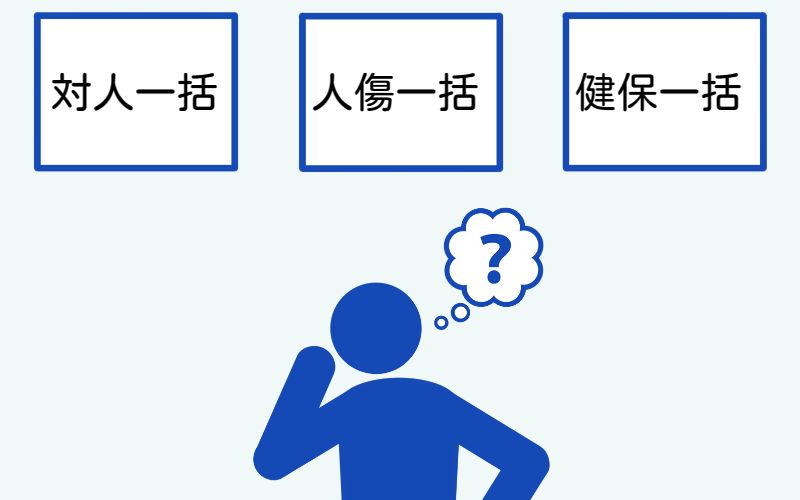※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

ここでは、労働能力喪失率とは何か、そもそも労働能力とは何をいうのか、労働能力の喪失率はどのように決められているのか、さらに、労働能力喪失率を判定するのに用いられる「労働能力喪失率表」の由来と問題点について解説します。
労働能力喪失率とは?
労働能力喪失率とは、交通事故による後遺障害のために、事故前と比べて「労働能力」が低下した割合のことです。後遺障害逸失利益の算定に用います。
ここでいう労働能力とは、一般的な平均的労働能力をいい、被害者の年齢・職種・知識・経験などの職業能力的諸条件については、障害の程度を決定する要素とはなっていません。
(『労災補償障害認定必携第17版』一般財団法人労災サポートセンター70ページ)
労働能力喪失率は、どのように決まるのか?
労働能力喪失率は、認定された後遺障害等級に応じて決まります。
自賠責支払基準の「別表Ⅰ 労働能力喪失率表」において、各後遺障害等級に対応する労働能力喪失率が定められており、自賠責保険では、後遺障害等級が決まれば、それに応じて労働能力喪失率も決まる仕組みです。
労働能力喪失率表とは?
労働能力喪失率表とは、次のようなものです。自賠責支払基準の「別表Ⅰ」より抜粋しておきます。
介護を要する後遺障害(自賠法施行令別表第1)の場合
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100/100 |
| 第2級 | 100/100 |
後遺障害(自賠法施行令別表第2)の場合
| 等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 第1級 | 100/100 |
| 第2級 | 100/100 |
| 第3級 | 100/100 |
| 第4級 | 92/100 |
| 第5級 | 79/100 |
| 第6級 | 67/100 |
| 第7級 | 56/100 |
| 第8級 | 45/100 |
| 第9級 | 35/100 |
| 第10級 | 27/100 |
| 第11級 | 20/100 |
| 第12級 | 14/100 |
| 第13級 | 9/100 |
| 第14級 | 5/100 |
いかにも意味のありそうな数値が並んでいますが、この労働能力喪失率表の数値(労働能力喪失率)には、科学的根拠はないといわれています。
では、後遺障害等級ごとの労働能力喪失率は、どのように決められたのでしょうか?
労働能力喪失率表の由来
自賠責保険の労働能力喪失率表には、「労働基準局長通牒 昭32.7.2基発第551号による」という但し書きが付いている場合があります。例えば、こちらの国土交通省のWebサイトに掲載している労働能力喪失率表をご覧ください。
もともと労働能力喪失率表は、昭和32年7月2日の労働基準局長通牒(基発第551号)において示されたもので、それが、自賠責保険の保険金支払い基準として使われているのです。
昭和32年7月2日の労働基準局長通牒(基発第551号)とは?
昭和32年7月2日付け労働基準局長通牒(基発第551号)は、労災保険法20条の規定の解釈について通達したものです。当時の労災保険法20条は、現行労災保険法12条の4にあたります。
労災保険法20条(現行12条の4)とは、第三者行為災害の事案の場合、労災保険の保険者である政府は、被災労働者に保険給付をすると、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する、というものです。
このとき、国が取得する損害賠償請求権の範囲は、①被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額が限度で、かつ②保険給付額が限度となります。
②の保険給付額は明らかですが、①の「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額」は、裁判所の判断を待たなければ確定しません。しかし、行政手続きを進めなければならないので、「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求権の額」を算出する基準が必要です。
そこで、国は、地方局署の事務取扱の便をはかり、かつ行政取扱いを統一化するため、「政府が取得する損害賠償請求権の範囲」や「損害賠償額の算定方法」等について基準を定め、通達しました。これが、昭和32年7月2日付基発第551号の通牒です。
(労働省労働基準局労災補償部『労災補償行政史』労働法令協会559ページ)
この中で、労働能力喪失率表が示されました。
つまり、労働能力喪失率表は、労災保険における第三者行為災害の事案で、保険者である国が、第三者(加害者)に求償するにあたり、代位取得する「被災労働者が加害者に対して有する損害賠償請求債権額」の目安をつけるために作成されたものなのです。
このように、労働能力喪失率表は、そもそも行政上の事務取扱を円滑に進めるための基準を示したものにすぎないのですが、民事損害賠償実務を前提とした「国としての損害算定基準」という性格をもつことになり、さらに、国の示した基準という性格上、一定の信頼性があるとの考えから、自賠責保険の保険金支払い基準や裁判における損害算定にも採用されるようになったのです。
労働能力喪失率表の数値(喪失率)はどう決まったのか?
それでは、労働能力喪失率表の数値(労働能力喪失率)は、どのようにして決められたのでしょうか?
昭和32年7月2日付労働基準局長通牒(基発第551号)の中で、労働能力喪失率については、労働基準法・別表第一の身体障害等級及び災害補償表(現行の労基法では別表第二)にもとづき、各障害等級の後遺障害につき障害補償日数を10分の1にしてパーセントを附し、かつ第3級以上をすべて100%としたものを労働能力喪失率表と称して用いることにし、ここに同表の成立をみた、とされています(『現代損害賠償法講座7』日本評論社200ページ)。
詳しく見ていきましょう。
昭和32年当時の労働基準法77条は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、なおったときに身体に障害が存する場合においては、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第一に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない」と定めています。ここでいう別表第一が、「身体障害等級及び災害補償表」です。
現行労働基準法77条も、言い回しが一部変わっているだけで基本的に同じです。「身体障害等級及び災害補償表」についても、現行法では「別表第二」となっていますが、その内容は当時と全く同じです。
身体障害等級及び災害補償表
| 等級 | 災害補償 |
|---|---|
| 第1級 | 1340日分 |
| 第2級 | 1190日分 |
| 第3級 | 1050日分 |
| 第4級 | 920日分 |
| 第5級 | 790日分 |
| 第6級 | 670日分 |
| 第7級 | 560日分 |
| 第8級 | 450日分 |
| 第9級 | 350日分 |
| 第10級 | 270日分 |
| 第11級 | 200日分 |
| 第12級 | 140日分 |
| 第13級 | 90日分 |
| 第14級 | 50日分 |
これと労働能力喪失率をあわせて1つの表にまとめると、こうなります。
| 等級 | 給付日数 | 労働能力喪失率 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1340日 | 100/100 |
| 第2級 | 1190日 | 100/100 |
| 第3級 | 1050日 | 100/100 |
| 第4級 | 920日 | 92/100 |
| 第5級 | 790日 | 79/100 |
| 第6級 | 670日 | 67/100 |
| 第7級 | 560日 | 56/100 |
| 第8級 | 450日 | 45/100 |
| 第9級 | 350日 | 35/100 |
| 第10級 | 270日 | 27/100 |
| 第11級 | 200日 | 20/100 |
| 第12級 | 140日 | 14/100 |
| 第13級 | 90日 | 9/100 |
| 第14級 | 50日 | 5/100 |
この表を見れば明らかでしょう。労働能力喪失率表の第4級以下の喪失率は、障害補償の給付日数を10で割った数値に「%」を付けると、喪失率のパーセンテージと一致する(給付日数を10で割った数値が喪失率の分子の数値と一致する)のです。
第3級以上が労働能力喪失率100%となっているのは、「終身労務不能」を第3級としているからです。そのため、第3級が労働能力喪失率100%となり、これより上の第1級と第2級は、100%を超える喪失率はあり得ないので、労働能力喪失率100%となっているのです。
当時の労災保険法施行規則・別表第二「身体障害等級表」では、第3級の3が「精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」、第3級の4が「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」と規定しています。
現行の労災保険法施行規則では、別表第一「障害等級表」で、第3級の3は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」となっています。第3級の4は変わっていません。
このことから、労働能力喪失率表は、後遺障害と稼働利益喪失との関係を科学的に調査・検討して作成されたものではなく、労災障害補償についての障害と補償額の関係を流用して作成されたものにすぎない、といわれているのです。
(梶本俊明・長崎地裁佐世保支部判事補「労働能力喪失・低下による損害」判例タイムズ№212号100ページ)
とはいえ、全く何らの科学的検討も経ないで決められたものともいえません。
労働能力喪失率表は、労働基準法・別表「身体障害等級及び災害補償表」にもとづいて作成されていますが、その淵源をたどると、昭和6年制定の労働者災害扶助法施行令の別表「身体障害等級及障害扶助料表」に行き着きます。
これは、当時の内務省社会局労働部において、医学専門家も交えて検討した結果、一般的な労働能力の喪失の程度に応じて各身体障害を格付けすることを原則として、「終身労務不能」を第4級(労働能力喪失率100%)、常時全面介護を要する最も重い障害を第1級(労働能力喪失率150%)、局所に神経症状を残す程度の軽微な障害を第14級(労働能力喪失率5%)とし、98種類の障害をその程度別に概ね10%刻み、14段階に配列した扶助料表を作成した、とされています。
その後、昭和11年には、労働者災害扶助法施行令の別表「身体障害等級及障害扶助料表」は一部改正されるとともに、工場法施行令にも同じ「身体障害等級及障害扶助料表」が取り入れられました。このときには、障害を120種類に増やし、精神神経系障害等内部障害を中心に一部修正したのみで、基本的には何ら変わっていません。
戦後、この「身体障害等級及障害扶助料表」の規定は、労働基準法77条、同法・別表第一「身体障害等級及び災害補償表」および同法施行規則・別表第一「身体障害等級表」に引き継がれましたが、その際にも、神経系統の障害、上下肢の関節障害、その他内臓障害等の点で若干の修正が加えられたのみで、基本的には当初の内容を踏襲しています。
なお、災害補償(旧法では障害扶助料)は、労働者災害扶助法や工場法では、賃金の3分の2を3年間、年利4分の複利で扶助を行うという計算により、障害等級1級の補償金額を賃金600日としていましたが、労働基準法では、平均賃金の3分の2を6年間、年利3分の複利で補償を行うという計算により、第1級の補償金額を平均賃金1340日分とし、以下各等級もこれに従って修正したうえで端数を整理して定められました。
こうした労働能力喪失率表の基礎にある労働基準法・別表の成立の経緯からすると、現在の労働能力喪失率表は、一応の科学的検討を経て出されたものと評価すべきものであろう、との指摘もあるのです。
(参考:加藤和夫「後遺症における逸失利益の算定」『現代損害賠償法講座(7)』日本評論社199~201ページ)
東京地裁民事27部(交通専門部)の判事も、労働能力喪失率表の数値は、「ただちに科学性・合理性を積極的に認めることができないとしても、実際に事件を担当していると『当たらずとも遠からず』という感じのする事例が多いことも事実」と話しています(『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい34ページ)。
裁判における労働能力喪失率表の取扱い
現在の民事損害賠償実務においても、この旧労働省の発した通牒で示された労働能力喪失率表を使っていますが、そもそも労働能力喪失率表は、労災保険手続き上の基準を示した通達にすぎず、民事損害賠償の権利義務に関して法的効力を持ちません。
したがって、現実の裁判実務では、労働能力喪失率表の数値を参考にしつつも、適宜数値を調整して損害算定する例もみられます。
東京地裁民事27部の河邉義典判事は、講演の中で、「他に代わるべき客観的な基準がない現状においては、判断の客観性、統一性を確保するため、第一次的には喪失率表を参考にするのが妥当であると思われるが、喪失率表の定める喪失率が後遺障害の実情に合致しない場合にまで、画一的、定型的に喪失率表にしたがう必要はない」と話しています。
(東京三弁護士会交通事故処理委員会編集『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい34ページ)
東京地裁民事27部(交通部)における労働能力喪失率表の取扱い
東京地裁民事27部(交通部)では、次のように取り扱っています。
後遺障害等級が認定されると、通常は、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率を認めているが、労働能力の低下の程度については、労働能力喪失率表を参考としながら、被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位・程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、具体的に評価することとなる。
(「東京地裁民事27部における民事交通訴訟の実務について」『別冊判例タイムズ38』15ページ)
裁判では被害者の具体的事情を考慮
裁判でも基本的に自賠責の判断した労働能力喪失率が尊重されますが、その労働能力喪失率が適当でない場合は、個別事情を考慮して、修正した労働能力喪失率が認定されます。
最高裁は、「労働能力喪失表にもとづく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できる」と判示しています。
事案は、小学校教諭を退職後、ピアノと書道の家庭教師として各家庭に出張教授し、毎月5万円の収入を得ていた男性が、交通事故に遭い、右膝関節屈曲障害(労災等級9級(喪失率35%)または10級(喪失率27%)該当)により、正座はもちろん、ピアノのペダルを踏むことも困難となり、家庭教師を辞めたというものです。
原判決が90%の労働能力喪失率を認定したところ、加害者側から、喪失率表に従わずに労働能力喪失率を認定したのは、法的安定性を破るものであるとして、上告したものです。
最高裁は、この上告に対し、次のように述べ、90%の労働能力喪失率を認めた原判決の判断を是認し、上告を棄却しました。
交通事故による傷害のため、労働能力の喪失・減退を来たしたことを理由として、得べかりし利益の喪失による損害を算定するにあたって、上告人の援用する労働能力喪失率表が有力な資料となることは否定できない。
しかし、損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を填補することを目的とするものであるから、被害者の職業と傷害の具体的状況により、同表に基づく労働能力喪失率以上に収入の減少を生じる場合には、その収入減少率に照応する損害の賠償を請求できることはいうまでもない。
労働能力喪失の実態について適切な立証を行うことにより、喪失率表所定の喪失率よりも高い労働能力喪失率を認めた判決も少なくありません。
まとめ
後遺障害によって労働能力がどの程度失われるのかという労働能力喪失率は、自賠責保険制度においては、後遺障害等級が認定されれば、その等級に対応した労働能力喪失率が認められます。
ただし、後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を定めた労働能力喪失率表は、科学的根拠のあるものではなく、しかも労災保険手続上の基準を示した通達において示されたものにすぎません。
したがって、労働能力喪失率表は、民事損害賠償実務において法的拘束力を持つものではありませんから、労働能力喪失率表により導かれる労働能力喪失率が、後遺障害の実情に合致しない場合には労働能力喪失率表に従う必要はありません。
労働能力喪失率表を参考としながら、被害者の職業、年齢、後遺症の部位・程度などから総合的に判断し、具体的に評価することが大切です。
労働能力喪失率をどう判断するかは、後遺障害逸失利益の算定において難しいところなので、交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『新・現代損害賠償法講座 5交通事故』日本評論社137~166ページ
・『現代損害賠償法講座7』日本評論社187~214ページ
・『新しい交通賠償論の胎動』ぎょうせい31~38ページ、169~174ページ
・『別冊判例タイムズ38』15ページ
・『労災補償障害認定必携』一般財団法人労災サポートセンター69~70ページ
・労働省労働基準局労災補償部『労災補償行政史』労働法令協会559ページ、606~617ページ
・梶本俊明「労働能力喪失・低下による損害」判例タイムズ№212号100~101ページ