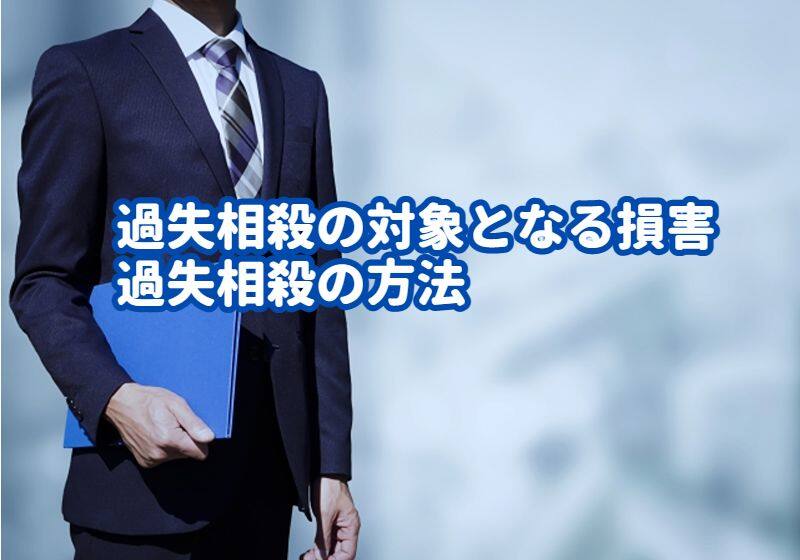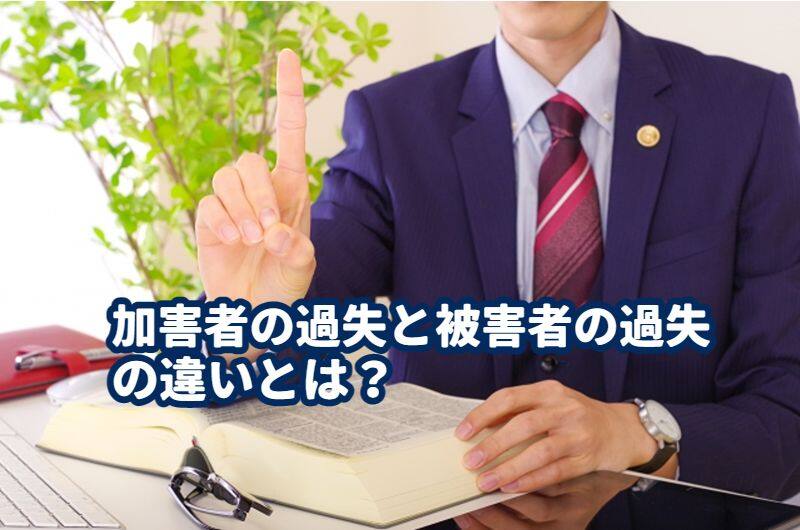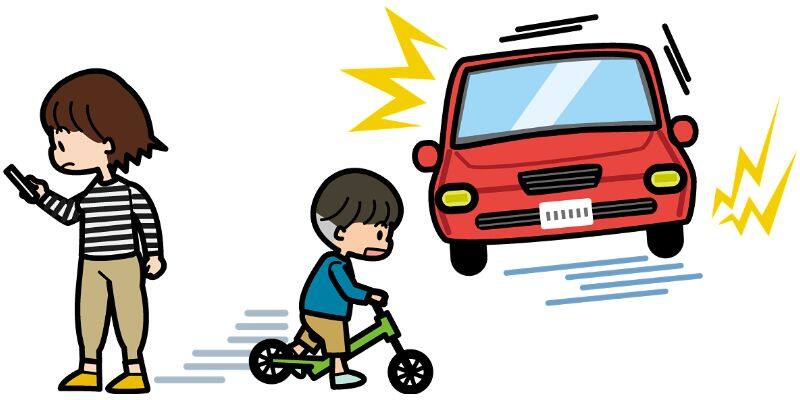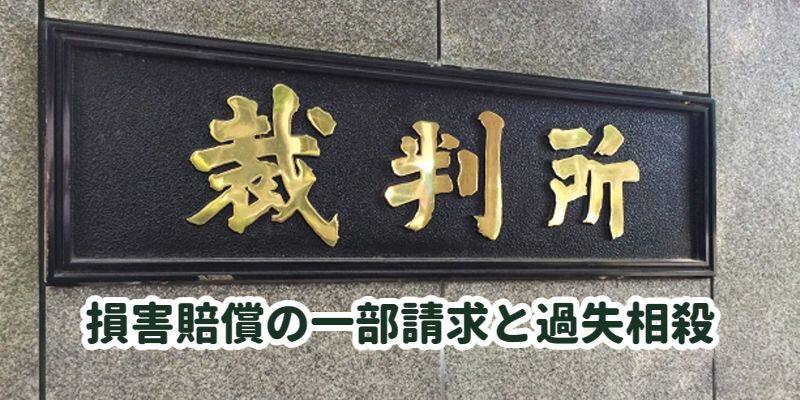※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

好意同乗・無償同乗とは、運転者の好意により無償で同乗させてもらうことです。
ここでは、好意同乗・無償同乗していた自動車が事故を起こし、同乗者が受傷したとき、同乗車両の運転者に対する損害賠償請求や過失相殺がどうなるのか、見ていきましょう。
好意・無償同乗者は同乗車両の運転者に損害賠償請求できる
知人等の自動車に好意・無償で同乗させてもらっていて交通事故に遭い受傷したとき、同乗車両の運転者に対して損害賠償を請求することができます。
多くは、自賠法(自動車損害賠償保障法)3条にもとづき賠償請求しますが、自賠法3条で請求できない場合でも、民法709条にもとづき請求できます。自賠法3条と民法709条の損害賠償請求権の違いはこちらをご覧ください。
自賠法3条は「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と、定めています。運行供用者は、自動車の運行によって「他人」を死傷させたときは、損害賠償責任を負います。ここで、同乗者が「他人」にあたるかどうかが問題となります
同乗者は、運行供用者の「他人」
運行供用者とは、マイカーの場合なら車両の所有者や運転者が該当し、たいてい同乗者は、運行供用者の「他人」にあたります。
最高裁は、「自賠法3条にいう他人とは、自己のために自動車を運行の用に供する者および当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいうと解するのが相当である」と同乗者の他人性を認めています(最高裁判決・昭和42年9月29日)。
つまり、好意・無償同乗者は、自賠法3条にもとづいて、同乗車両の運行供用者に対して、損害賠償請求することができるのです。
「他人性」が否定される場合
例外的に、好意・無償同乗者が共同運行供用者にあたる場合(同乗者が車両の所有者で自分の自動車を運転させていた場合など)は「他人性」が否定され、自賠法3条にもとづく損害賠償請求ができません。
この場合は、民法709条にもとづく損害賠償請求をすることになります。
好意同乗・無償同乗を理由に賠償額を減額されることはない
かつては、好意同乗・無償同乗という事実のみで損害賠償額が減額されていましたが、今はそんなことはありません。
従来、運転者の好意により無償で同乗させてもらいながら、一般の被害者と同じように損害の全部を賠償請求するのは、「信義に反する」「公平を欠く」と考えられ、好意同乗・無償同乗という理由だけで、損害賠償額を減額していました。
例えば、あなたが、たまたま同じ方向へ行く知人の車に便乗させてもらい、途中で交通事故に遭って負傷したとします。好意で乗せてもらいながら、知人である運転者に損害の全額を賠償請求することは躊躇するでしょう。実際、こういう場合は、好意同乗・無償同乗を理由に、損害賠償額が減額されていました。
タクシーに乗車中に交通事故に遭ったような場合は、好意・無償同乗減額はありません。
タクシーの運転手は、運送契約にもとづいて、乗客を安全に目的地まで送り届ける義務があります。もし、途中で交通事故を起こし乗客が怪我をしたのであれば、運送契約に基づいて乗客の損害を賠償する責任が発生します。
好意・無償同乗者の損害賠償額が減額される場合とは?
現在は、単に好意同乗・無償同乗であることを理由に、損害賠償額を減額されることはありません。
飲酒運転を知りながら同乗した場合など、同乗者に「過失相殺が適用されるような帰責事由」がある場合に限り、賠償額を減額する裁判例が支配的になっています。
好意同乗・無償同乗を理由に損害賠償額が減額されなくなった理由
好意同乗・無償同乗を理由に損害賠償額が減額されなくなった背景の1つに、自動車保険が整備され、賠償金が保険で手当てされるようになったことがあります。
車両の所有者は、事故を起こしたときの法的責任(損害賠償責任)に備えて自動車保険に加入しています。自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、加入が義務づけられています。
自動車保険は、加害者が被害者に損害賠償金を支払い、それによって加害者である被保険者に生じた損害を保険会社が填補する仕組みです。事実上、保険会社が被害者に損害賠償金を支払うのと同じです。
実際、任意自動車保険に加入していれば、保険会社が加害者(被保険者)の代わりに損害賠償額を計算し、被害者と示談交渉を行い、示談が成立すれば、保険会社が被害者に損害賠償金額を支払います。
自動車保険制度は、交通事故による被害者の救済が目的です。その趣旨からして、好意同乗・無償同乗を理由として、保険金(損害賠償額)の支払いを減額する保険会社の主張を認めることは不合理です。
被害者とすれば、好意で乗せてくれた人に「損害の全額を賠償してほしい」とは言いにくいかもしれませんが、適正な損害賠償を請求しないことは、保険会社の支払責任を軽減してしまうことになるのです。
好意・無償同乗の4つの類型
好意同乗・無償同乗は、次のような4つの類型に分類されます。
- 単なる便乗・同乗型
同乗者に事故発生の帰責事由がない場合 - 危険承知型
事故発生の危険性が高い客観的事情が存在することを知りながら同乗した場合
(運転者の無免許・薬物乱用・飲酒・過労など) - 危険関与・増幅型
同乗者が事故発生の危険性が増大するような状況を現出させた場合
(スピード違反を煽った場合など) - 共同運行供用者型
運転者に自賠法3条の運行供用者責任が否定され民法709条の損害賠償責任が成立する場合
①のように、同乗者に帰責性がない「単なる便乗・同乗」である場合は、単なる同乗者であることのみをもって、賠償責任者を保護するために賠償額を減額する必要性・合理性はないので、損害賠償額の減額は行われません。
②③のように、同乗者に事故の帰責性がある場合は、同乗減額が認められます。
④のように、同乗者が共同運行供用者となる場合には減額があり得ますが、②③のような事情が存在しないのに、単に運行供用者に当たり得るということのみをもって、賠償金額を減額した裁判例は見当たらないとの指摘もあります(『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 398ページ)。
好意・無償同乗減額と同乗者の過失割合の算定方法
好意・無償同乗減額が行われる「危険承知型」「危険関与・増幅型」「共同運行供用者型」について、同乗者の過失がどのように認定されるのか見ていきましょう。
具体事例を考えるにあたって、Aが同乗者、Bが同乗車両の運転者、Cが相手方運転者とします。
危険承知型
「危険承知型」は、同乗者が、運転者の無免許・薬物乱用・飲酒・過労など事故発生の危険性が高い客観的事実を知りながら、あえて同乗したケースです。
運転者に事故を起こす危険性が高い事実があることを分かった上で同乗したのですから、「みずから積極的に危険に接近して損害を被った」ことを理由に、損害の公平な分担の見地から、賠償額が減額されます。
同乗者の過失割合は、同乗車両の運転者の過失のうち、交通事故発生の危険性が高い客観的事実に係る過失割合の範囲内の一部です。事故発生の危険性が高い客観的事実を認容していた程度に応じて決まります。
例えば、Aが、Bの無免許運転を知っていながら同乗し、交差点内でCの運転する自動車と衝突した場合を考えてみましょう。
BとCの間の過失割合が[B40:C60]のとき、Aは、Bの過失割合40%の一部を自己の過失として問われます。
Bの過失割合40%のうち無免許を理由とする部分が20%であるなら、Aの過失割合は20%を上限に、AがBの無免許を認容した程度などから算定します。
Aの過失割合を10%とすると、A10:B30:C60の絶対的過失割合が認定されます。
危険関与・増幅型
「危険関与・増幅型」は、同乗者が、運転者のスピード違反や蛇行運転を煽ったり、運転者のブレーキ操作やハンドル操作を妨げるなどして、交通事故発生の危険性が増大するような状況を現出させたケースです。
こうした行為が、同乗者の過失(不法行為)として問われます。
同乗者の過失の影響を受けるのは、同乗車両の運行です。同乗者の過失割合は、同乗車両の過失割合を上限とし、みずからの行為が事故発生の危険性を高めた程度に応じて、その一部が自己の過失となります。
例えば、AがBの運転する車両に同乗してスピード違反を煽り、Aによるブレーキ操作の妨害行為もあり、交差点内でCの運転する自動車と衝突した場合を考えてみましょう。
BとCの過失割合は[B70:C30]とします。Aのスピード違反運転の煽り行為やブレーキ操作の妨害行為という過失は、Bの過失割合70%に反映されています。
Bのスピード違反を理由とする過失割合が20%で、そのうちAの煽り行為の部分が5%であったとします。さらにAのブレーキ操作の妨害行為による部分が15%であったとき、Aの過失割合は合わせて20%となります。
A20:B50:C30の絶対的過失割合が認定されます。
共同運行供用者型
「共同運行供用者型」とは、同乗者が車両の保有者であり、運転を交代でしていたようなケースです。
同乗者の運行支配の程度が運転者と同等程度以上で、自賠法3条の「他人性」が否定されるような場合は、同乗車両の運転者に対して自賠法にもとづく賠償請求はできず、民法709条にもとづき賠償請求することになります。
ただし、同乗者も、共同運行供用者として、交通事故の発生を抑制すべき立場にあり、損害の公平な分担の見地から、その程度に応じて過失相殺の規定の類推適用がなされます。
同乗者には共同運行供用者として交通事故の発生を抑制すべき立場にあったのですから、同乗者の過失割合は、同乗車両の運転者の過失割合を上限とし、その運行支配の程度に応じ、同乗車両の運転者の過失割合の一部を自己の過失とすることになります。
例えば、BとCの過失割合が[B20:C80]、AとBの運行支配の程度が1/2ずつの場合、同乗者の過失はBの過失20%の1/2なので10%となります。
A10:B10:C80の絶対的過失割合が認定されます。
同乗者の過失割合の算定方法は、東京地裁民事第27部判事 桃崎剛『好意同乗及び同乗者のヘルメット・シートベルト装着義務違反における共同不法行為と過失相殺』判例タイムズ№1213)を参考にしました。
ヘルメット不着用・シートベルト不装着による減額
同乗者には、ヘルメットの着用やシートベルトの装着が義務づけられていますから、好意・無償同乗減額される場合には、ヘルメット不着用・シートベルト不装着もあわせて減額割合が決められるのが一般的です。
なお、ヘルメット不着用やシートベルト不装着による過失相殺は、そのことが損害の拡大に影響していると認められる場合に適用されます。
好意・無償同乗減額が交通事故の発生に対する責任・過失であるのに対して、ヘルメット不着用やシートベルト不装着による減額は、損害の拡大に対する責任・過失である点が異なります。
ヘルメット不着用やシートベルト不装着を理由とする過失割合は、損害を拡大させた程度により決まります。
損害を拡大させた程度を厳密に認定することは困難で、交通事故発生の原因の場合と異なり損害を拡大させた割合が直ちに同乗者の過失割合になるわけではないので、その割合は控えめに算定すべきであるとされています。
実際、これまでの裁判例では、ヘルメット不着用の場合で多くは5~10%、最大でも30%程度、シートベルト不装着の場合で5%から最大でも20%程度に止まっているようです。
(参考:上記判例タイムズ№1213)
例えば、Aが、Bの運転するバイクに同乗し、Cが運転する自動車と衝突。Aの損害が1,000万円。BとCの過失割合が[B30:C70]、Aのヘルメット着用義務違反による過失割合が10%とします。
Aは、BとCに対し、1,000万円から自己の過失割合10%を控除した900万円を賠償請求することができます。BとCの負担割合は、過失割合B30:C70に応じて、Bが270万円、Cが630万円となります。
好意・無償同乗減額の裁判例
最後に、好意・無償同乗減額についての裁判例を紹介しておきます。
好意・無償同乗者の減額を否定した裁判例
好意同乗者・無償同乗者に帰責事由が認められないとして損害賠償額の減額が否定された裁判例には、次のようなものがあります。
レンタカーで旅行中、時速50㎞制限のところを時速100㎞から120㎞に加速して先行車を追い越し、進路変更しようとして急ハンドルを切ったため制御不能となり縁石に衝突して横転し、同乗者が死亡した事案について、同乗者に無謀な運転を誘発するような行為は認められず、運転に危険性が高いことを承知ないし予測できたような事情もないとして、同乗減額を認めなかった。
一緒に買い物に行くためバイクに同乗し事故にあった事案について、好意同乗減額が認められるには、運転者が事故を惹起しかねないような具体的事情を認識しながら任意の意思で同乗したことが必要であるが、本件ではそのような事情は認められないとして、同乗減額を認めなかった。
路面凍結によりスリップしてトンネル壁に衝突し、助手席で仮眠中の同乗者が負傷した事案について、同乗者は、事故発生の危険が増大するような状況を自ら積極的に現出させたり、事故発生の危険が高い事情が存在することを知りながらこれを容認して同乗した等の事情はないとして、同乗減額を認めなかった。
好意・無償同乗者の減額を肯定した裁判例
好意同乗・無償同乗という理由で減額されるわけではありません。同乗者にどのような具体的な帰責事由があれば好意・無償同乗減額がされるのか、裁判例を紹介します。
ドライブの誘いを受けて同乗中、酒酔い運転で高速道路を制限速度を倍の速度で暴走し、分岐点のクッションドラムに衝突して死亡したケースについて、飲酒の可能性は多少認識していたにとどまるが、暴走行為の認容はあったことから、シートベルト不装着も考慮して35%減額した。
加害者を呼び出して一緒に飲食店で飲酒した被害者が助手席に同乗中の事故について、自ら事故発生の危険性が高い状況を招来し、そのような状況を認識したうえで同乗したとして同乗減額を認め、シートベルト不装着とあわせて25%減額した。
加害車両に同乗して飲酒目的で居酒屋へ向かい、飲酒後、助手席に同乗中ハンドルを取られてトンネル内で側壁に衝突横転して被害者が受傷した事案について、加害者が飲酒運転をすることを認容し、飲酒していることを承知で同乗したとして同乗減額を認め、シートベルト不装着も考慮して20%減額した。
まとめ
現在は、好意同乗・無償同乗という理由で賠償額が減額されることはありませんが、同乗者に過失があるときはその程度に応じて過失相殺されます。
例えば、運転者が飲酒しており事故発生の危険性が高いことを承知で同乗した場合や、スピード違反を煽り事故の発生に関与した場合など、同乗者に過失がある場合には、その程度に応じて賠償額が減額されます。
ヘルメット不着用やシートベルト不装着が損害の拡大に影響している場合は、あわせて減額されます。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・東京地裁民事第27部判事 桃崎剛『好意同乗及び同乗者のヘルメット・シートベルト装着義務違反における共同不法行為と過失相殺』判例タイムズ№1213
・『プラクティス交通事故訴訟』青林書院 397~402ページ