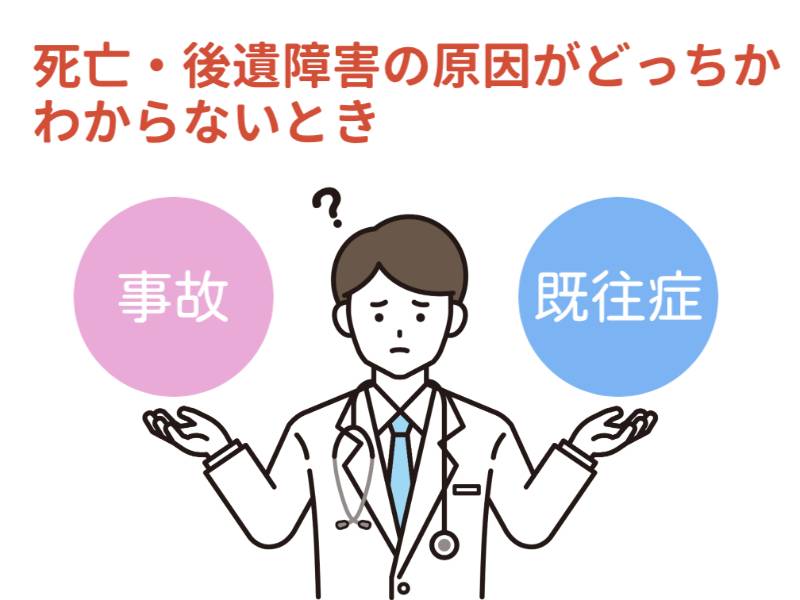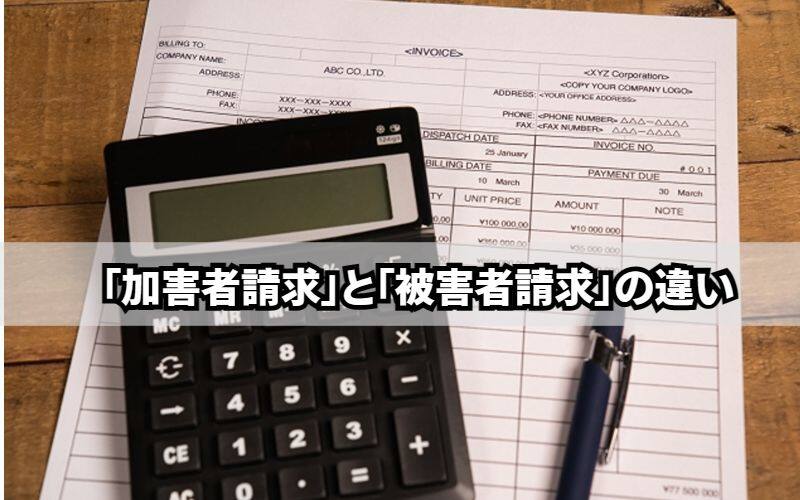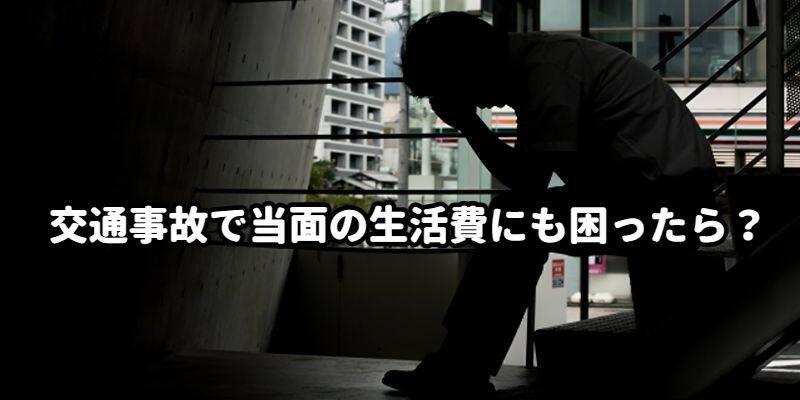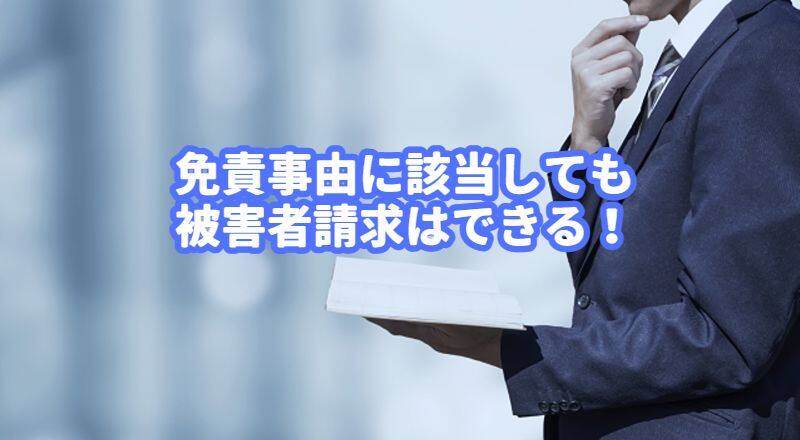※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

自賠責保険は、「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」に対し、保険金の支払基準・支払限度額が定められています。自賠責保険は、人身損害が対象で、物損は対象となりません。
自賠責保険の支払基準・支払限度額について、見ていきましょう。
自賠責共済も、支払基準・支払限度額は、ここで示した自賠責保険の支払基準・支払限度額と同じです。自賠責保険と自賠責共済の違いはこちらをご覧ください。
民法一部改正による法定利率の変更にともない、逸失利益の算定に用いるライプニッツ係数が変更になります。また、平均余命、物価水準、賃金水準の変動を踏まえ、2020年4月1日より、自賠責保険の支払基準が一部改正されました。
傷害による損害の支払基準と支払限度額
傷害による損害は、積極損害(治療関係費・文書料など)、休業損害、慰謝料です。
傷害による損害に対する自賠責保険からの支払限度額は、積極損害・休業損害・慰謝料を合わせて、被害者1人につき 120万円です(自賠法施行令第2条第1項)。
| 損害 | 内容・支払基準 |
|---|---|
|
治療費 |
診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料など |
|
通院費等 |
通院、転院、入院、退院に要した交通費 |
|
看護料 |
入院中の看護料 自宅看護料まはた通院看護料 |
|
諸雑費 |
入院中に要した諸雑費 |
|
柔道整復等の費用 |
柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用 |
|
義肢等の費用 |
義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用 |
|
診断書等の費用 |
診断書、診療報酬明細書などの発行手数料 |
|
文書料 |
交通事故証明書、印鑑証明書、住民票などの発行手数料 |
|
休業損害 |
事故のため仕事や家事を休業し、その間の収入を得られなかった損害を補償 |
|
慰謝料 |
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
後遺障害による損害の支払基準と支払限度額
後遺障害による損害は、逸失利益と慰謝料です。後遺障害等級に応じて、支払限度額が定められています(自賠法施行令2条1項2号3号、別表第一、別表第二)。
適正な損害賠償を受けるには、適正な後遺障害等級の認定を受けることがカギです。なお、等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う、とされています。
後遺障害に至るまでの傷害による損害については、120万円の支払限度額の範囲で保険金が支払われ、それにプラスして、後遺障害による損害に対する保険金が支払われます(自賠法施行令2条1項2号3号)。
後遺傷害による逸失利益と慰謝料とは、次のようなものです。
| 損害 | 内容・支払基準 |
|---|---|
|
逸失利益 |
後遺障害がなければ得られたはずの利益 |
|
慰謝料 |
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償 |
後遺障害等級ごとの支払限度額は、次の通りです。
重度後遺障害(介護を要する後遺障害)の等級と支払限度額
| 障害等級 | 支払限度額 | うち慰謝料 | |
|---|---|---|---|
| 従来 | 2020年4月1日以降 | ||
|
第1級 |
4,000万円 |
1,600万円 |
1,650万円 |
|
第2級 |
3,000万円 |
1,163万円 |
1,203万円 |
※神経系統の機能や精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護を要する場合が該当します。第1級は常時介護を要する場合、第2級は随時介護を要する場合です。
※被扶養者がいるとき、慰謝料が、第1級は1,800万円(→1,850万円)、第2級は1,333万円(→1,373万円)となります。赤数値は、2020年4月1日以降の金額です。
後遺障害の等級と支払限度額
| 障害等級 | 支払限度額 | うち慰謝料 | |
|---|---|---|---|
| 従来 | 2020年4月1日以降 | ||
|
第1級 |
3,000万円 |
1,100万円 |
1,150万円 |
|
第2級 |
2,590万円 |
958万円 |
998万円 |
|
第3級 |
2,219万円 |
829万円 |
861万円 |
|
第4級 |
1,889万円 |
712万円 |
737万円 |
|
第5級 |
1,574万円 |
599万円 |
618万円 |
|
第6級 |
1,296万円 |
498万円 |
512万円 |
|
第7級 |
1,051万円 |
409万円 |
419万円 |
|
第8級 |
819万円 |
324万円 |
331万円 |
|
第9級 |
616万円 |
245万円 |
249万円 |
|
第10級 |
461万円 |
187万円 |
190万円 |
|
第11級 |
331万円 |
135万円 |
136万円 |
|
第12級 |
224万円 |
93万円 |
94万円 |
|
第13級 |
139万円 |
57万円 |
変更なし |
|
第14級 |
75万円 |
32万円 |
変更なし |
※被扶養者がいるとき、慰謝料が、第1級は1,300万円(→1,350万円)、第2級は1,128万円(→1,168万円)、第3級は973万円(→1,005万円)となります。赤数値は、2020年4月1日以降の金額です。
後遺症が複数の部位で残る場合、複数の部位で後遺障害等級が認定されると、後遺障害等級が繰り上がる仕組みです。
死亡による損害の支払基準と支払限度額
死亡による損害に対する支払限度額は、被害者1人につき 3,000万円です(自賠法施行令2条1項1号)。葬儀費用、逸失利益、死亡本人の慰謝料と遺族の慰謝料が支払われます。遺族慰謝料の請求権者は、被害者の父母・配偶者・子です。
葬儀費用と慰謝料は、支払金額が定められていますが、逸失利益は、死亡本人の収入額や就労可能年数などによって決まります。例えば、収入のない高齢者が事故で死亡した場合には、逸失利益はほとんどなく、おおむね葬儀費用と慰謝料ということになります。
なお、死亡に至るまでの治療費など傷害による損害に対しは、別途120万円を上限に保険金が支払われます(自賠法施行令2条1項1号)。
| 損害 | 内容・支払基準 |
|---|---|
|
葬儀費 |
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く) |
|
逸失利益 |
生きていれば得られたはずの利益 |
|
慰謝料 |
死亡本人⇒ 350万円(2020年4月1日以降は 400万円) 遺族請求権者1名⇒ 550万円遺族請求権者2名⇒ 650万円 |
※例えば、一家の大黒柱の夫が、妻と子2人を残して死亡したときの慰謝料は、400万円+750万円+200万円=1,350万円となります。赤数値は、2020年4月1日以降の金額です。
減額
自賠責保険には、過失相殺や素因減額はありません。なので、被害者の過失割合に応じて損害賠償額が過失相殺されることも、被害者に既往症等があったからといって損害賠償額が減額されることもありません。
ただし、まったく減額されないわけではありません。次の2つの減額の制度があります。
重過失減額
自賠責保険は、被害者に7割以上の重大な過失があった場合にのみ減額されます。減額割合も、傷害に係るものは2割、後遺障害・死亡に係るものは最大で5割にとどまります。
因果関係不明の減額
被害者に既往症等があったため、死因または後遺障害発生原因が、事故によるものなのか既往症等によるものなのか明らかでなく、事故と死亡または後遺障害との因果関係の有無の判断が困難な場合には、支払基準にもとづき積算した損害額(その額が保険金額以上となる場合は保険金額)から5割減額する、というものです。
なお、これは「5割減額する」というよりも、通常は因果関係の立証ができなければ損害として認められませんから、因果関係が立証できない場合でも5割支払いましょう、という被害者にとって有利な制度なのです。
被害者・加害者が複数いる場合の支払限度額
自賠責保険の保険金の支払限度額は、被害者1人あたりの金額です(自賠法施行令第2条第1項)。1事故あたりの限度額ではありません。
被害者が複数の場合や加害者車両が複数の場合、自賠責保険金の支払限度額は、次のようになります。
被害者が複数の場合
複数の被害者を出した場合は、被害者ごとに限度額まで保険金が支払われます。
例えば、車の衝突事故で、被害車両に3人が乗車していて受傷した場合、被害者3人に、それぞれ120万円を限度として、加害車両の自賠責保険から保険金が支払われます。
加害車両が複数の場合
加害車両が複数ある場合は、加害車両それぞれの自賠責保険に保険金を請求できるので、支払限度額は、加害車両の数に応じて増えます。自賠責保険は、車両ごとに付保されるものだからです。
つまり、被害者の損害額を限度に、[自賠責保険の支払限度額]×[加害車両数]が、自賠責保険の支払限度額となります。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合、いずれかの車に同乗していて負傷した被害者には、両方の車の自賠責保険から保険金が支払われます。この場合、自賠責保険の支払限度額は、被害者1人につき、120万円×2台=240万円になります。
ただし、これは支払限度額が加害車両数に応じて増えるのであって、支払基準は変わりません。
つまり、加害車両2台による傷害事故の場合、支払限度額は240万円(120万円×2)になりますが、例えば、傷害慰謝料が支払基準の2倍の1日8,600円(4,300円×2)になるわけでなく、1日4,300円で変わりません。
保険期間中なら何度でも保険金が支払われる
自賠責保険は、事故を起こして保険金が支払われた後、また別の事故を起こした場合でも、保険期間内であれば、同じ限度額で保険金が支払われます。
自賠責保険には、「自動復元制度」が採用されているからです。したがって、自賠責保険は、保険期間中であれば、何度事故を起こしても契約が失効することはなく、何度でも支払限度額内で支払いを受けることができます。
とはいえ、事故を起こさないのが一番です。
まとめ
自賠責保険・自賠責共済は、傷害による損害、後遺障害による損害、死亡による損害について、保険金・共済金の支払基準・支払限度額が決められています。
自賠責保険・自賠責共済の支払限度額を超える損害が発生した場合は、その超過する損害については任意保険から支払われます。
自賠責保険は、自賠法(自動車損害賠償保障法)にもとづき設けられた保険です。自賠責保険を取扱う損害保険会社が、勝手に契約内容を決めることはできません。約款に規定のない場合は、自賠法が適用されます。
支払基準についてもっと詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください。
※損害保険料算出機構のWebサイトにリンクしています。
保険会社の提示額に疑問はありませんか?
交通事故の損害賠償問題に詳しい弁護士に相談すれば、保険会社が提示する示談金の額が適正かどうか分かります。賠償金額を大幅アップできる可能性があります。
一度、無料相談を試してみてはいかがでしょうか?
実際に依頼するかどうかは、相談してから考えても大丈夫です。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。