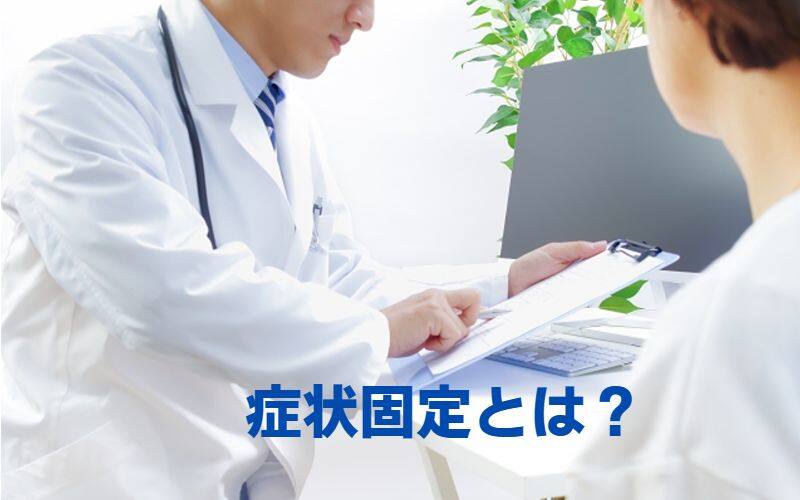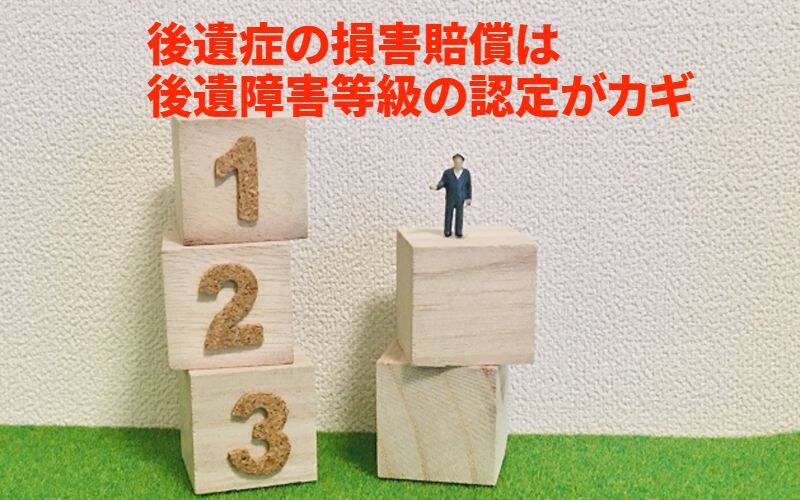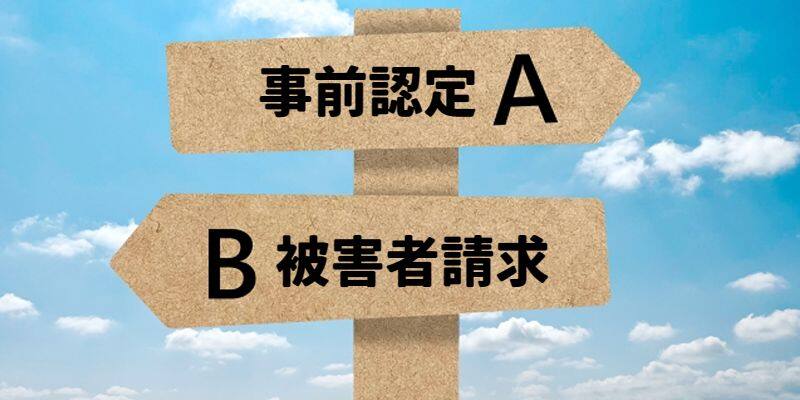※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
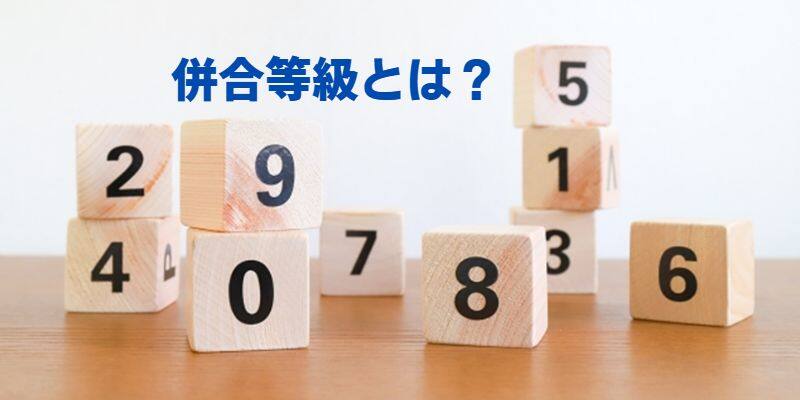
複数の部位で後遺障害が残ったときは、一定のルールに従って等級が繰り上がります。これを等級の「併合」といいます。ただし、第14級については、いくつ認定されても繰り上げになりません。
複数の後遺障害が残った場合に自賠責保険から支払われる保険金額は、併合等級に対応する額となりますが、その額が併合前の等級に対応する保険金の合算額を超える場合は、合算額が支払われます。
後遺障害等級の「併合」とは?
自賠責保険制度では、2つ以上の後遺傷害の等級認定を受けた場合、一定のルールに従って等級が繰り上がる仕組みになっています。繰り上がった等級を「併合等級」といいます。
併合による等級繰り上げのルールは、自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められています(自賠法施行令第2条1項3号)。なお、自賠法施行令では、介護を要する後遺障害が「別表1」、後遺障害が「別表2」で定められていますが、併合等級があるのは「別表2」の方だけです。
併合による「等級の繰り上げ」のルール
併合による等級の繰り上げのルールは、次のように定められています。
- 第5級以上が2つ以上存する場合、重い等級の3級上位の等級に繰り上げ。
- 第8級以上が2つ以上存する場合(上記の場合を除く)、重い等級の2級上位の等級に繰り上げ。
- 第13級以上が2つ以上存する場合(上記の場合を除く)、重い等級の1級上位の等級に繰り上げ。
後遺障害の13級以上が2つ以上ある場合、上のルールに従って等級が繰り上がります。これ以外の場合は、重い等級が後遺障害の等級となります。
なお、第14級は、いくつ等級認定されても、繰り上げになりません。
例
- 4級と5級が認められた場合は、4級が3つ繰り上がって、併合1級。
- 7級と8級が認められた場合は、7級が2つ繰り上がって、併合5級。
- 11級と12級が認められた場合は、11級が1つ繰り上がって、併合10級。
- 5級と13級が認められた場合は、5級が1つ繰り上がって、併合4級。
- 12級と14級が認められた場合は、等級の繰り上げはなく、12級。
併合等級の保険金額(自賠責保険から支払われる金額)
後遺障害に対して自賠責保険から支払われる保険金の限度額は、後遺障害等級に応じて決められています。
2つ以上の後遺障害が認定された場合は、原則として、一番重い等級の保険金額が適用されます。ただし、複数の後遺障害が併合により等級が繰り上がった場合は、併合等級に対応する保険金額が、自賠責保険の支払限度額となります。
なお、併合等級の場合は、注意しなければならない点があります。
併合等級の保険金額の決定ルール
併合等級に対応する保険金額が、併合前のそれぞれの後遺障害等級の保険金額の合算額を超える場合は、合算額が支払われます。
つまり、「併合等級に対応する保険金額」と「併合前のそれぞれの等級に対応する保険金額の合算額」の少ない方の金額が、自賠責保険から支払われる保険金額となる仕組みです。
(例1)12級と13級で、併合11級の場合
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 11級 | 331万円 |
| 12級 | 224万円 |
| 13級 | 139万円 |
※後遺障害等級表「別表2」より抜粋。
12級と13級の保険金額の合算額は363万円ですから、併合11級の331万円の方が少ないので、支払われる保険金額は、併合等級の331万円となります。
(例2)10級と13級で、併合9級の場合
| 等級 | 保険金額 |
|---|---|
| 9級 | 616万円 |
| 10級 | 461万円 |
| 13級 | 139万円 |
※後遺障害等級表「別表2」より抜粋。
10級と13級の保険金額の合算額は600万円ですから、併合9級の616万円の方が高いので、支払われる保険金額は、合算額の600万円となります。
併合等級の労働能力喪失率をどうするか
併合等級の場合、後遺障害逸失利益の算定にあたって、労働能力喪失率をどうするかという難しい問題があります。これについては、判例も分かれ、確定した手法がありません。
裁判では、併合等級に対応する労働能力喪失率を認定するもの、併合前の最も重い後遺障害等級に対応する労働能力喪失率を認定するもの、併合等級を下方修正するもの、逓減方式をとるものなど、判例が分かれています(『交通事故損害賠償法 第2版』弘文堂)。
自賠責保険の支払基準では、後遺障害等級に対応して労働能力喪失率が決まっています。
単一の後遺障害の場合は、その等級に応じた労働能力喪失率を採用すればよいのですが、複数の後遺障害の場合は、単純ではありません。
自賠責保険では、労働能力喪失率が問題となることはありません。支払限度額があるからです。逸失利益は高額になるため、自賠責保険は支払限度額いっぱいを支払えばよいのです。
上で見たように、併合等級が関わる場合でも、「併合等級に対応する保険金額」と「併合前のそれぞれの等級に対応する保険金額の合算額」の少ない方の金額を支払うというように、保険金額を決めておけば足りるわけです。
それに対して、実際に損害額を算定するときには、労働能力喪失率をどうするかが大きな問題となります。
単一の後遺障害の場合でも、裁判では、自賠責保険の支払基準に定められた労働能力喪失率に準拠しながらも、具体的状況を考慮し、適宜これを修正します。
それが併合等級の場合なら、労働能力喪失率をどうするかは、非常に難しい問題なのです。
過去の判例も参考にしながら個別に判断することになるので、被害者個人ができることではなく、詳しい弁護士に相談するしかありません。
まとめ
13級以上の後遺障害が2つ以上認定されると、一定のルールに従って等級が繰り上がり、併合等級となります。自賠責保険から支払われる保険金額(賠償額)も単一の後遺障害に比べて多くなります。
ただし、複数の後遺障害が残った場合、損害賠償請求額の算定にあたっては、逸失利益の算定で労働能力喪失率をどう決めるかといった難しい問題があります。交通事故の後遺障害に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。