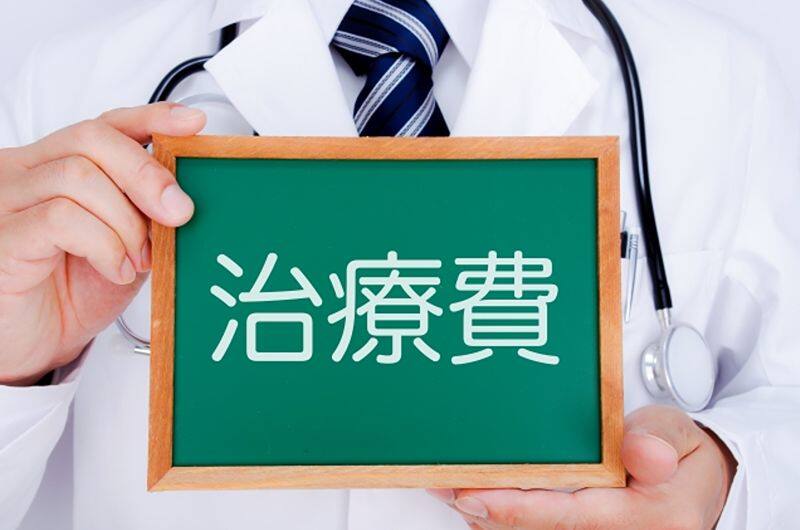※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
治療関係費
治療関係費とは、治癒または症状固定までの、病院の治療費、整骨院の施術費、薬局の調剤費などのことです。治療関係費は、「必要かつ相当な範囲」で、実費を全額請求できます。請求には、次のものが必要です。
| 請求に必要なもの | |
|---|---|
| 入通院先が病院 |
|
| 通院が整骨院等 |
|
| 薬局 |
|
注意点
- 自由診療で必要以上の治療が行われた場合は、過剰診療と判断される場合があります。特別室料や差額ベッド料は、救急車で搬送されたときに一般病室に空きがなかった場合や医師から指示があった場合など、特別な理由がない限り認められません。
- 整骨院等の施術証明書に、病院の診断書に記載されていない傷病名が記載されている場合、その施術費の回収が困難となるので、注意が必要です。
- 鍼灸、マッサージ、温泉療養費なども、医師の指示がある場合は認められます。揉めることが多いので、「マッサージの必要あり」「湯治の必要あり」という医師の診断書を取っておくことが大切です。
付添看護費
付添看護を必要とする場合には、付添人費用を損害額として賠償請求できます。
職業的付添人を雇った場合は、支払った金額の実費を請求できます。家族や近親者が付き添った場合も、実際に金銭の支払いはありませんが、提供した労務を金銭に換算して請求できます。
付添看護費は、医師が付添人の必要性を判断した場合に請求できます。なお、被害者が小学生以下の場合は、医師の指示は必要なく無条件で認められます。
| 職業的付添人 | 実費 |
|---|---|
| 近親者付添人 |
入院付添 1日5,500円~7,000円(自賠責基準は4,200円) 通院付添 1日3,000円~4,000円(自賠責基準は2,100円) |
通院交通費
被害者本人が治療を受けるために通院する場合の交通費は、原則実費を請求できます。
電車やバスを利用した場合は、費用を請求するのに領収書は必要ありませんが、通院日と運賃を書き留めておきましょう。
自家用車で通院した場合は、ガソリン代、駐車場代などの実費が認められます。請求には領収書が必要です。有料道路代・高速道路代は、有料道路を通らないと病院に行けない、専門医がいる病院が遠くて高速道路を利用したなど、必要性があれば認められます。
タクシーの利用は、重症で緊急を要する場合、足の怪我の治療で歩けない場合、体が衰弱している、タクシー以外に交通手段がないなど、相当性がある場合に限られます。請求には領収書が必要です。
通院日、通院方法、金額、医療機関名を記録しておくことが大切です。
| 公共交通機関 | 片道運賃 × 2(往復分)× 通院日数(入退院日を含む) |
|---|---|
| 自家用車 |
距離(㎞)× 2(往復分)× 通院日数 × 15円 |
| タクシー | 実費(領収書の金額を合計する) |
被害者が救急搬送され、家族に自家用車で迎えに来てもらって病院から帰宅した場合、往復のガソリン代を請求できます。被害者自身は退院時の片道乗車でも、迎えに行った家族は往復しているので、往復分のガソリン代が認められます。
入院時に家族が送迎した場合も、往復のガソリン代を請求できます。
雑費
交通事故に遭わなければ必要とならなかった次のような諸費用について、必要かつ相当な範囲で損害と認められます。
入院雑費
病衣代、タオル代など、入院中の生活消耗品や通信費、テレビの貸借料などを請求できます。
金額は日額で定額化されているので、領収書は必要ありません。
逆に、それ以上の出費があり、領収書を添付して請求しても、特別に必要があったもの以外は認められません。
入院1日につき、1,400円~1,600円(自賠責基準は、1日1,100円)
次のようなものが、入院雑費で賄えます。
| 日常雑貨品 | 寝具、パジャマ、洗面具、ティッシュペーパー、文房具、食器などの購入費 |
|---|---|
| 栄養補給費 | 牛乳、お茶、茶菓子などの購入費 |
| 通信費 | 電話、電報、郵便代 |
| 文化費 | 新聞・雑誌代、テレビ・ラジオ貸借料など |
よく問題になるのが、電気ポットや電気毛布、テレビなどですが、これらの購入費は認められません。レンタル料は請求できます。
損害賠償請求関係費用
損害額を算定するために必要となった費用です。
文書料(医療機関関係)
後遺障害診断書、後遺障害等級申請に必要な検査画像のコピー等を発行してもらうためにかかる費用です。自賠責診断書、自賠責診療報酬明細書の文書料は、通常は治療関係費に含んで計算します。
文書料(その他)
後遺障害等級申請に必要な印鑑証明書代、交通事故証明書代、過失割合の検討に必要な刑事事件記録の取り付けにかかる費用、謄写代等。
その他
医学鑑定料、事故状況の鑑定料など、損害額の算定に必要で支出した費用。
相手方任意保険会社が、示談交渉段階で、刑事記録の取得費用や鑑定書の作成費用の支払いに応じることはありません。
裁判では、刑事記録を用いて過失の有無や過失割合を認定するのが一般的なので、刑事記録の取得費は、被害者に通常生じる損害として認定される傾向にあります。
工学鑑定や医学鑑定は、それにもとづいて過失の有無や過失割合、被害者の後遺障害を認定するのが裁判で一般的とは言えず、鑑定書の作成費用は、損害認定されない傾向にあります。
(参考:『交通事故事件処理の道標』日本加除出版株式会社63ページ)
被害者が、自身の傷害保険の保険金を請求するために、診断書を取った場合、診断書を取得するのに要した費用は、損害賠償請求のためではなく、保険金請求のためにかかった費用なので、加害者から賠償を受けることはできません。
その他
その他、こんな費用も損害として認められます。
装具費用
義肢、義足、義歯、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子、かつら、身障者用パソコンなど
医師が必要と認めた装具費用は、実費相当額を請求できます。
義肢、義足、義歯、義眼などの身体的補助器具は、一度作れば一生もつものではないので、数年おきに作り直す必要があります。その費用も請求できます。
ただし、その費用を一度に請求するとなると、医師の診断書が必要なことは言うまでもありませんが、中間利息を控除して請求することになります。
その他の費用
学生が治療のため、留年・入学延期した場合の授業料、受傷した子どもの学習の遅れを取り戻すための補習の費用、子どもを預けなければならなくなった費用(保育費)などの実費相当額を請求できます。
そのほか、自賠責保険の支払基準には明記されていませんが、後遺障害が残った場合の家屋や自動車の改造費も、裁判所基準では実費相当額を請求できます。
まとめ
傷害事故の積極損害の賠償額の算定は、これらの損害額を積み上げる作業です。
定型化・定額化されているとはいえ、事故ごとの個別事情を考慮する必要があります。被害者自身が行うには大変な作業になりますから、漏れなく算定するには、詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。