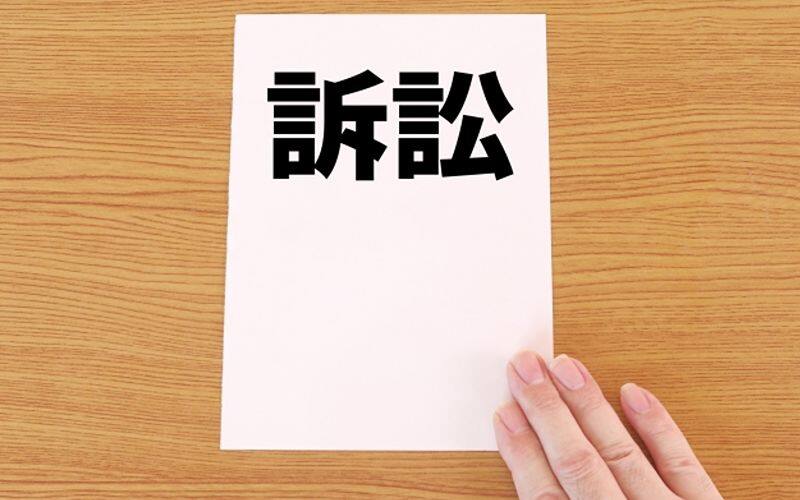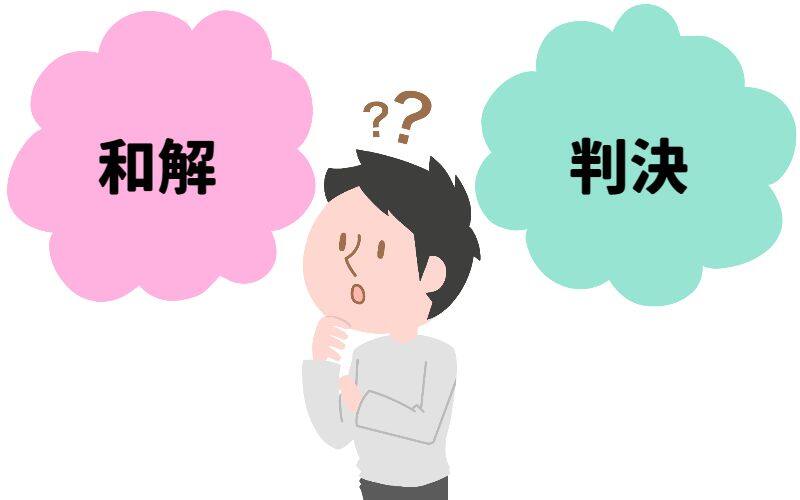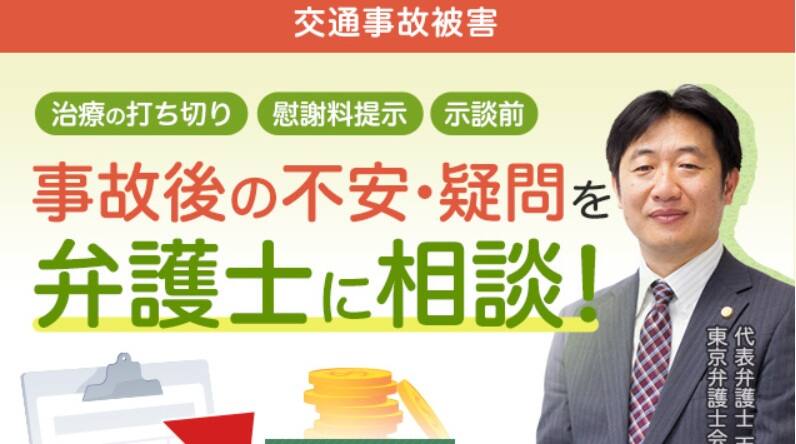※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

突然、裁判所から訴状が送られてきたら、誰だって驚くでしょう。
「えっ? これ何? どうして訴えられるの? こっちは被害者なのに!」
「何かの間違い? それとも新手の詐欺?」
ここでは、債務不存在確認訴訟とは何か、加害者側(保険会社)から債務不存在確認訴訟を提起されたらどう対応すればいいのか、についてまとめています。
債務不存在確認訴訟とは
交通事故の民事訴訟は、普通、被害者が加害者に対して損害賠償金の支払いを求めて起こすものです。しかし、ときに加害者側が、訴訟を提起することがあります。それが、損害賠償債務の不存在確認訴訟(債務不存在確認訴訟)です。
損害賠償債務とは、加害者が被害者に対して支払い義務を負う損害賠償金のことです。債務不存在確認訴訟とは、「加害者が被害者に対して支払う損害賠償債務は金○○万円を超えて存在しないことを確認する」ことを求める裁判です。
つまり、交通事故の損害賠償についての債務不存在確認訴訟とは、加害者(保険会社)の側が、保険会社が賠償金として提示している金額以上は支払う責任がないことを裁判所に確認してもらうために起こす裁判です。
この場合、損害賠償請求訴訟と逆で、加害者が原告、被害者が被告となります。
債務不存在確認訴訟は、どんなときに提起されるのか
ところで、あなたは、激しい口調で保険会社の担当者やその代理人弁護士に抗議をしませんでしたか?
もし、心当たりがあるなら、それが訴えられた原因です。「そんなバカな!」と思うかもしれませんが、債務不存在確認訴訟が提起されるのは、多くはそういうケースです。
「強い口調で抗議した覚えはないんだけど?」という方もいるでしょう。保険会社が、賠償金の支払いを抑えようとして、債務不存在確認訴訟を提起することもあります。
保険会社が債務不存在確認訴訟を提起する 3つのケース
保険会社は、主に次のような場合に債務不存在確認訴訟を提起します。
- 被害者からの法外で執拗な要求を排除し、損害賠償債務の存否や適正な損害額の確定を求めようとする場合
- 被害者の治療や休業による損害の拡大を阻止しようとする場合
- 将来の損害賠償請求を封じようとする場合
被害者を黙らせるため
①は、主に当たり屋のような人物からの不当な要求の場合です。
不当な要求でなかったとしても、被害者が感情的に激しく責め立てるような場合にも、債務不存在確認訴訟を提起することがあります。債務不存在確認訴訟の提起は、被害者を黙らせるための保険会社の常套手段なのです。
保険会社は、被害者からガンガン責め立てられ「厄介な相手」と判断すると、弁護士委任案件とします。「弁護士に委任したので、これからは弁護士を通してください」と、被害者からの抗議の矛先を弁護士に向けさせます。
さらに弁護士に激しい口調で抗議を続けると、弁護士は、その抗議を封じるために債務不存在確認訴訟を提起します。「言いたいことがあるなら法廷で言ってください」というわけです。
賠償金の支払いを抑えるため
②は、早期に治療費や休業補償の支払いを打ち切り、損害賠償金の支払いを抑えるため、③は、後遺障害に関わる損害賠償を免れようとするのが狙いです。
とはいえ、治療を継続している段階にもかかわらず債務不存在確認訴訟を提起することは、被害者の適正な治療を受ける権利を侵害するものです。
治療を継続中など、損害を確定できる段階でないのに債務不存在確認訴訟が提起されたときは、裁判所が「確認の利益」がなく不適法と判断することがあります。
債務不存在確認訴訟が提起されたときの裁判所の対応
債務不存在確認訴訟が提起されると、裁判所は、被告である被害者の側に「交通事故による損害が確定しているか」「治療終了や症状固定により損害を確定できる状態か」を尋ねます。
被害者側の主張により、裁判所の対応は異なります。
損害が確定しているとき
損害が確定しているのであれば、裁判所は、被害者側に反訴の提起を促します。反訴とは、原告(加害者側)から提起された債務不存在確認訴訟(本訴)に対し、反撃となる損害賠償請求訴訟を提起することです。
被害者側から反訴(損害賠償請求訴訟)が提起されると、本訴(債務不存在確認訴訟)については「確認の利益がない」ということになるので、裁判所は、本訴原告に対し、本訴を取り下げるように促します。
損害が確定していないとき
被害者が、まだ治療を継続中なら、治療費・休業損害・入通院慰謝料などの金額は流動的で、損害を確定できません。
また、後遺症が残るときは、症状固定の診断を受け、後遺障害等級が決まらなければ、後遺症についての損害(後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料)を確定できません。
まだ被害者が治療を継続中という場合には、今後の見通しとして、次の2つのケースがあります。
- まもなく「治療が終了する・症状固定とする」見通しの場合
- 被害者が「当面は治療を継続する」意向の場合
まもなく治療終了あるいは症状固定とする見通しの場合
まもなく「治療が終了する」あるいは「症状固定として後遺障害等級の認定を受ける」見込みである場合は、それを待って反訴を提起する考えであるなど、被害者側としての見通しや意向を裁判所に示します。
それを受けて、裁判所は判断します。
被害者が当面は治療を継続する意向の場合
被害者側が、当面は治療を継続する意向で、反訴を提起しない場合、裁判所は本訴の審理を進めることになります。
裁判所は、本訴原告側に、治療の終了または症状固定の事実が認められると判断した資料の提出を求めます。原告(加害者)側は治療終了・症状固定を主張し、被告(被害者)側は治療継続の必要性を主張し、争います。
その結果、裁判所において「治療は終了していない」「症状は固定していない」という判断に至った場合は、損害を確定できませんから、債務不存在確認の判断をすることは時期尚早、つまり確認の利益(即時確定の利益)がないということになり、訴えの却下となります。
裁判所が「治療は終了している」「症状は固定している」と判断した場合は、被害者側に反訴の提起を促します。それでも被告(被害者)側が反訴を提起しない場合は、裁判官が、治療の終了や症状固定の時期を認定した上で損害額を算定し、判決を下すことになります。
裁判所が「症状は固定している」と判断して反訴を促している場合に、被告(被害者側)が「症状は固定していないから損害は確定できない」と主張し、反訴しない場合は、深刻な問題が起こります。
「症状は固定していない」という前提だと、「後遺障害がない」ということになってしまいます。
つまり、後遺障害について何ら主張する機会もなく、本訴(債務不存在確認訴訟)の審理が進められ、損害賠償額について判決が下されてしまうのです。弁護士とよく相談して、慎重な対応が必要です。
債務不存在確認訴訟が提起されたときの裁判所の対応については、東京地方裁判所判事・俣木泰治氏の講演「民事交通事故訴訟の基礎」(『交通事故の法律相談と事件処理』ぎょうせい)を参考にしました。
債務不存在確認訴訟が提起されたとき、被害者の取れる対応
債務不存在確認訴訟が提起されたときに、被害者側が取れる対応は、反訴(損害賠償請求訴訟)を提起するか、「損害を確定できない」と応訴するか、の2つです。
上で紹介した債務不存在確認訴訟が提起された場合の裁判所の対応から分かるように、反訴を提起するタイミングは、いくつかあります。
- 損害を確定できる状態なら、債務不存在確認訴訟が提起されたとき、ただちに反訴を提起する。
- 近々損害を確定できる状況になるのなら、その時点で反訴を提起する意向であることを裁判所に告げる。
- 裁判所が審理を進めて損害を確定できる状態にあるとの判断に至り、反訴の提起を促してきたとき。
裁判所が「症状が固定している」と判断したにもかかわらず反訴しない場合は、後遺障害についての損害賠償が認められない結果になることがあるので注意が必要です。
債務不存在確認訴訟が提起されたときの対応は、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士とよく相談して、慎重に対応を検討することをおすすめします。
債務不存在確認訴訟の提起が不適法となる場合とは?
債務不存在確認訴訟が提起されたときは、「確認の利益(訴えの利益)の有無」が問題となります。債務不存在確認訴訟の提起に「確認の利益がない」と、裁判所が判断した場合は不適法となり、裁判所は訴えの取り下げを促します。
どのような場合に「確認の利益がなく不適法」となるか、裁判所の判断が示されていますので、参考にしてください。
東京地裁(平成9年7月24)
損害賠償債務に係る不存在確認訴訟は、被害者側が、種々の事情により、訴訟提起が必ずしも適切でない、或いは時期尚早であると判断しているような場合、そのような被害者側の意思にかかわらず、加害者側が、一方的に訴えを提起して、紛争の終局的解決を図るものであることから、被害者側は、応訴の負担などの点で過大な不利益が生じる場合も考えられる。
このような観点に照らすならば、交通事故の加害者側から提起する債務不存在確認訴訟は、責任の有無及び損害額の多寡につき、当事者間に争いがある場合には、特段の事情のない限り、許されるものというべきであるが、他方、
- 事故による被害が流動的ないし未確定の状態にあり、当事者のいずれにとっても損害の全容が把握できない時期に訴えが提起されたような場合
- 訴訟外の交渉において加害者側に著しく不誠実な態度が認められ、そのような交渉態度によって訴訟外の解決が図られなかった場合
- 専ら被害者を困惑させる動機により訴えが提起された場合
などで、訴えの提起が権利の濫用にわたると解されるときには、加害者側から提起された債務不存在確認訴訟は、確認の利益がないものとして不適法となるというべきである。
※東京地裁・平成9年7月24日・中間判決(判例タイムズ№958号)より
この東京地裁の中間判決は、結論としては、交通事故による損害賠償債務の不存在確認訴訟において、確認の利益が肯定された事例ですが、「債務不存在確認訴訟の確認の利益の有無について判断した重要な事例判決」(判例タイムズ№958号)とされています。
まとめ
債務不存在確認訴訟の提起は、被害者を黙らせ、賠償金の支払いを抑制するための保険会社の常套手段です。債務不存在確認訴訟は、増加傾向にあるといわれています。保険会社の「払い渋り」が強まっていることの表れです。
被害者側が反訴(損害賠償請求訴訟)を提起すれば、債務不存在確認訴訟(本訴)は意味を失い、取下げとなります。
しかし、まだ治療を継続する必要があるなど、損害を確定できない場合は、反訴できません。そういう場合は応訴することになりますが、確認の利益(訴えの利益)がないと裁判所が判断すれば、訴えが却下されることがあります。
なお、被害者側が対応を誤ると、後遺障害が認定されないまま損害額が確定されるなど、取り返しのつかない事態を招く恐れがありますから、慎重な対応が必要です。
裁判所から、訴状が送られてきたのなら、すぐに交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人ステラは、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績17,000件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。もちろん弁護士保険にも完全対応。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-221-274
0120-221-274
( 24時間・365日受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談予約フォームをご利用ください。
※ 「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
【参考文献】
・『交通事故の法律相談と事件処理』ぎょうせい
・判例タイムズ№958号