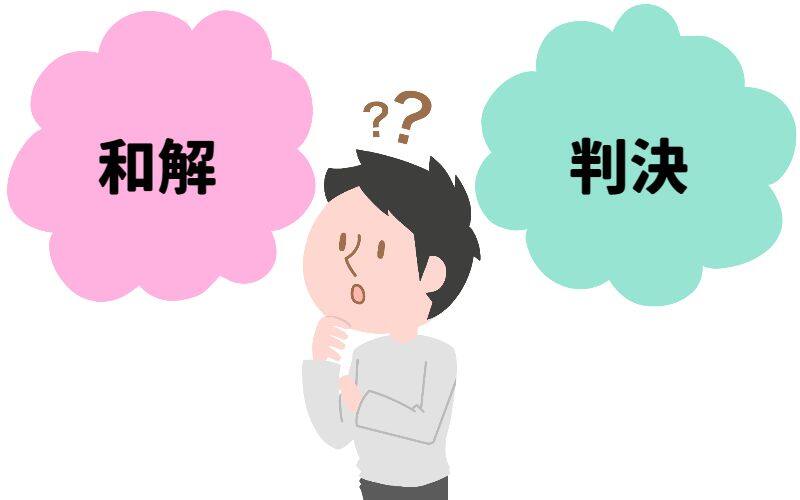※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。
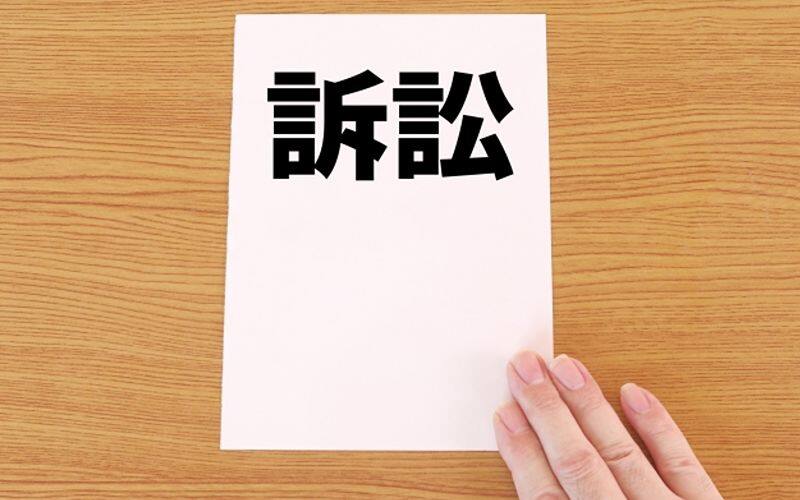
裁判では、裁判所基準で損害賠償額が認定されます。示談交渉のように被害者側が譲歩する必要はありません。そのうえ、示談の場合には支払われない「遅延損害金」や「弁護士費用」が認められます。裁判は、示談交渉や調停に比べ、時間も費用もかかりますが、最大限の賠償金を取得することができます。
損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を提起して、裁判で解決する場合のメリット・デメリットをまとめておきます。
【裁判のメリット①】最大限の賠償金を取れる!
損害賠償請求訴訟(民事訴訟)を提起する最大のメリットは、最大限の賠償金を取れることです。裁判では、示談交渉と違い、被害者側が譲歩する必要はありません。また、示談では支払われない弁護士費用や遅延損害金も認められます。
損害賠償額は裁判所基準で算定
裁判所は、損害賠償額を裁判所基準で算定します。
示談による解決の場合でも、弁護士に頼めば裁判所基準で損害額を算定して、相手方と交渉してくれます。しかし、示談を成立させるには双方が譲歩しあう必要がありますから、被害者側も請求金額からいくらかは値引きに応じなければなりません。
裁判では、被害者側が譲歩する必要はありません。裁判所基準にもとづき算定した正当と考えられる賠償金額を請求し、その根拠を立証すればよいのです。もちろん、請求額全額が認められるとは限りませんが、裁判所は、裁判所基準にもとづき正当な損害賠償額を算定します。
つまり、示談では、例えば「裁判所基準で算定した額の 8割程度」で合意せざるを得ないのに対して、裁判では「裁判所基準で算定した額そのもの」で判決が出るのです。
さらに、裁判の場合には「弁護士費用」や「遅延損害金」も認められます。
弁護士費用が一部認められる
交通事故の損害賠償請求訴訟では、被害者が弁護士に支払う費用も損害として認め、加害者に支払いを命じる判決が出されます。
ただし、弁護士費用の全額が認められるわけではありません。一般的に弁護士費用として認められる額は、裁判所が認める損害額の10%程度です。
例えば、裁判所が認める損害額が1億円だったとすれば、その1割の1千万円の弁護士費用が認められます。
なお、弁護士費用が認められるのは「判決」の場合で、「和解」の場合は認められません。
訴訟費用は、敗訴した者が負担するルールになっています(民事訴訟法61条)。訴訟費用とは、訴状に貼る印紙代と裁判所に収める郵送料など訴訟手続きにかかった費用です。
弁護士費用は、訴訟費用に含まれません。ですから、本来は勝訴しても、自分で頼んだ弁護士費用まで相手に請求できません。
ただし、近年、交通事故などの損害賠償請求訴訟では、弁護士費用の請求も認められるようになってきています。
遅延損害金が認められる
裁判では、遅延損害金が認められます。ただし、弁護士費用と同じく、判決の場合だけです。遅延損害金とは、賠償金の支払いが遅れたことによる利息です。
裁判所が認めた賠償金額に対し、事故発生日を起点として法定利率にもとづく遅延損害金が加算されます。
遅延損害金の計算方法
遅延損害金は、弁護士費用を加えた損害額をもとに算出します。
例えば、事故発生日から2年経過後に判決が出たとします。裁判所が認定した賠償金額が1億円とすれば、これに1割相当の弁護士費用を加算し、遅延損害金は、法定利率が年5%の場合、
(1億円+1千万円)× 5% × 2年 = 1,100万円
となります。
遅延損害金は交通事故の発生日から付加されます。
最高裁は、「不法行為に基づく損害賠償債務は、なんらの催告を要することなく、損害の発生と同時に遅滞に陥るものと解すべきである」との判断を示しています(最高裁第3小法廷・ 昭和37年9月4日)。
和解の場合は「調整金」を加算
裁判上の和解の場合は、紛争の早期解決の趣旨から、弁護士費用や遅延損害金を計上しないのが通例です。
ただし、人身損害に関する事件の場合には、被害者保護の観点から、遅延損害金の一部を「調整金」という名目で加算し、和解案が提示されることが多いようです。
例えば、上の例と同じく、事故発生日から2年経過後に、裁判所が提示した和解案で和解が成立したとしましょう。裁判所が認めた賠償金額が1億円、調整金を遅延損害金の50%とします。
この場合の調整金は、
1億円 × 5% × 2年 × 50% = 500万円
となります。遅延損害金と異なり、調整金の計算に弁護士費用は含みません。
【裁判のメリット②】事実関係に争いがあっても解決できる
損害賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級などで争いがある場合、示談交渉や裁判外紛争処理手続(ADR)による解決は困難です。
それに対して裁判なら、賠償責任の有無や過失割合、後遺障害等級など、事故態様や事実関係に争いがある場合でも解決できます。訴訟の提起は、示談交渉やADRで解決できない場合の最終的な解決方法です。
【裁判のデメリット】解決までに時間や費用がかかる
裁判は、解決までに時間や費用がかかるのがデメリットです。実態を見てみましょう。
審理期間
最高裁判所が公表している「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書 第6回」(2015年7月10日)によれば、交通損害賠償事件の審理期間は、平均で約1年です。
また、和解での解決が7割近くあり、判決にまで至るのは3割足らずです。和解は判決に比べ、早く解決します。
裁判費用
裁判費用としては、訴訟費用(裁判所に支払う手数料)のほか弁護士費用(弁護士に支払う報酬)があります。特に大きいのが、弁護士費用です。
訴訟費用は、主に訴状に貼る印紙代です。訴訟費用は訴額によって決まります。例えば、訴額が500万円なら印紙代は3万円、訴額が1千万円なら5万円、訴額が5千万円なら17万円です。
弁護士費用は、各弁護士事務所が報酬基準を設け、依頼者と協議の上で決めます。例えば、訴額1千万円の場合、着手金は5%なら50万円、裁判でその請求額が満額認められたとすれば、成功報酬は10%なら100万円です。訴訟費用よりはるかに大きな金額です。
こうした費用が負担となり、裁判は敬遠されてきたのですが、近年は弁護士保険が普及してきたこともあり、裁判を利用しやすくなっています。
交通事故の民事裁判が、訴えの提起から終結までどれくらいの審理期間を要するのか、費用はどれくらいかかるのか、詳しくは次のページをご覧ください。
まとめ
裁判は、ADRや調停でも解決できない場合の最終的な解決手段です。裁判となると、費用も時間もかかります。必ず勝利できるとは限りませんが、勝訴すれば最大限の損害賠償金額を取ることができます。
裁判を検討しているのであれば、一度、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
その際、重要なのは弁護士選びです。このサイトでは、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士事務所をご紹介しています。示談交渉や民事訴訟で実績豊富な弁護士事務所ですから安心です。弁護士選びの参考にしてみてください。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!

 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。