

※当サイトでは記事内にアフィリエイト広告を含む場合があります。

会社員や公務員など、給与所得者の休業損害・逸失利益を計算するときの基礎収入額には、原則として「事故前の実際の収入額」を用います。
ただし、逸失利益については、将来の長期間にわたる収入の問題ですから、事故時の収入額によるのが相当でない場合は、平均賃金を用いることもあります。
ここでは、給与所得者の基礎収入の算定方法について説明しています。基礎収入を用いた休業損害や逸失利益の計算方法については、次のページをご覧ください。
基本的な取り扱い
休業損害は、怪我の治療や療養のため休業したことにより「現実に喪失した収入額」です。事故前の現実の給与額を基礎収入として計算します。
逸失利益も、基本的には休業損害と同様、実収入額によるのが原則ですが、逸失利益は、将来の長期間にわたる収入の問題です。
そのため、被害者が若年労働者の場合のように、事故当時の実収入額によるのが相当でない場合は、平均賃金を用いる場合もあります。
- 収入は、手取額でなく、支払金額(税金等控除前の金額)です。収入の証明には、源泉徴収票か納税証明書・課税証明書が必要です。
- 給与以外に家賃等の不動産収入や利子、配当などの「不労所得」があっても、労働の対価といえないので基礎収入には含まれません。
若年労働者の収入算定
若年労働者は、現実の収入が低い場合が多いので、それを基礎として逸失利益を算定すると、過少に計算されてしまいます。
また、仕事を長く続けていけば、収入が上がっていくと考えられます。事故前の実収入を用いると、将来の給与の上昇を逸失利益に反映することができません。
そのため、若年被害者(おおむね30歳未満)については、現実の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回るとしても、将来、平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合は、全年齢平均賃金または学歴別平均賃金を基礎収入とします。
非正規労働者の収入算定
契約社員・嘱託社員・派遣社員・パート・アルバイトなどの非正規労働者は、一般に正社員より給与が低く、雇用が不安定ですから、事故当時の収入を基準として逸失利益を算定することは困難です。
しかし、事故当時に非正規であったとしても、これから先もずっと非正規のままとは限りません。経済状況が好転したり、一定の条件を満たすときは、正社員になる場合もあります。
そういったことから、判例では、賃金センサスの平均賃金またはその一定割合を基礎収入として、逸失利益を算定する事例があります。
収入に含まれるもの
収入には、本給のほか、諸手当、賞与など労働の対価として受け取るものが該当します。これら以外にも、昇給や退職金も含めることができます。
諸手当
諸手当については、扶養家族手当などは基礎収入に含めることができますが、通勤手当(交通費やガソリン代の支給)のような実費手当は、所得の対象とならないので、損害には含まれません。
また、残業手当については、企業の業績や担当する業務内容に左右され、将来も継続するとは限りません。そのため、事故前の残業手当が多かったとしても、そのまま認められるとは限りません。
ボーナス(賞与・期末手当)
ボーナスは、給与規定などによって支給基準が決められ、安定・継続して支給されている場合は、それが損害として認められます。
しかし、ボーナスの支給基準を定めた給与規定がなく、業績によって年ごとに開きがある場合は、事故前にボーナスの支給を受けていたとしても、そのまま認められるとは限りません。
大企業の社員や公務員は、支給基準にもとづいて算出した賞与額が認められやすいのですが、中小企業の場合は、立証が難しいところです。
昇給
定期昇給については、勤務先に昇給規定などがあり、それに従って昇給する可能性がある場合は、昇給を考慮して基礎収入を算定できます。
昇給規定がなくても、将来の昇給が「証拠にもとづいて相当の確かさをもって推定できる場合」は、昇給を考慮して基礎収入を算出することができると最高裁が判断を示しています。
最高裁判決(昭和43年8月27日)
死亡当時安定した収入を得ていた被害者において、生存していたならば将来昇給等による収入の増加を得たであろうことが、証拠に基づいて相当の確かさをもつて推定できる場合には、右昇給等の回数、金額等を予測し得る範囲で控え目に見積つて、これを基礎として将来の得べかりし収入額を算出することも許されるものと解すべきである。
ベースアップ
物価上昇にともなうベースアップ分については、一般的に認められません。
和解成立時または口頭弁論終結時までに行われたベースアップ分については考慮されますが、将来のベースアップ分については、不確定で予測しがたいことなどから、認められない傾向にあります。
退職金
退職金については、勤務先に退職金規定があり、交通事故に遭わなければ退職金をもらえたと考えられる場合は、退職金を損害に算入できます。
死亡時あるいは事故の後遺症が理由で退職したときに勤務先から支給された退職金と、定年まで勤務すれば得られたであろう退職金(中間利息控除後の額)との差額が逸失利益となります。
退職金差額が損害として認められるための要件としては、次の3つが指摘されています(『交通事故損害賠償法・第2版』弘文堂145ページ)。
- 交通事故による受傷(死亡または後遺障害)と退職との間に因果関係があること
- 被害者が定年退職時まで勤務を継続する蓋然性があること
- 定年退職時に退職金が支給される蓋然性があること
例えば、60歳まで勤務すれば1,000万円の退職金がもらえたのに、55歳で交通事故に遭って死亡し、600万円の死亡退職金の支給を受けたとします。中間利息を控除した現価は、ライプニッツ係数を乗じて計算します。
5年(60歳-55歳)のライプニッツ係数は0.8626(ライプニッツ式係数表・現価表より)ですから、
1,000万円×0.8626-600万円=262万6,000円
となります。この差額を逸失利益として損害賠償請求できます。
ここから生活費を控除するかどうかについては、判例が分かれています。
定年退職後の収入
就労可能年数は67歳まで認められますが、給与所得者の場合、60歳前後で定年退職するのが一般的です。ただし、最近は、定年後に再就職し、何らかの収益を上げて生活するのが普通になっています。
定年退職後の収入については、賃金センサスの年齢別平均賃金を基礎とする場合と、退職時の収入の一定割合を基礎とする場合があります。
まとめ
給与所得者の休業損害・逸失利益を算定するときの基礎収入には、事故前の実際の収入額を用いるのが基本です。
若年労働者のように、事故前の実収入を基礎とするのが相当でない場合は、平均賃金を用います。
ボーナス、昇給分、退職金を含めることはできますが、難しい問題もあります。
交通事故問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人・響は、交通事故被害者のサポートを得意とする弁護士事務所です。多くの交通事故被害者から選ばれ、相談実績 6万件以上。相談無料、着手金0円、全国対応です。
交通事故被害者からの相談は何度でも無料。依頼するかどうかは、相談してから考えて大丈夫です!
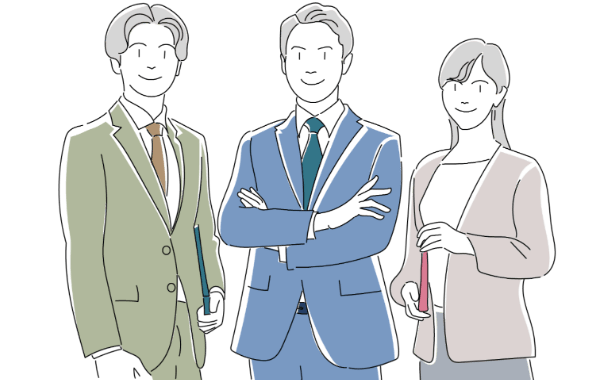
 0120-690-048 ( 24時間受付中!)
0120-690-048 ( 24時間受付中!)
- 無料相談のお申込みは、こちらの専用ダイヤルが便利です。
- メールでも無料相談のお申込みができます。公式サイトの無料相談受付フォームをご利用ください。
※「加害者の方」や「物損のみ」の相談は受け付けていませんので、ご了承ください。
関連
休業損害や逸失利益の計算方法は、次のページをご覧ください。








